日本シェイクスピア協会会報
Shakespeare News
Vol. 45 No. 2
December 2005
学 会 特 集 号
| 第44回シェイクスピア学会を終えて | 楠 明子 |
学 会 特 集
パネル・ディスカッション(要旨)
研究発表(要旨)
19 世紀シェイクスピア絵画に見る男装のヒロイン ――ジェンダーと生物学的性差の観点から
鏡のイメージで読む『十二夜』――エコーとナルキッソス達
パラス誕生−『ゴーボダック』の黙劇と助言の作法
ルーシオウの悪ふざけ――『尺には尺を』における裁きと認識
ジョン王をめぐる二つの劇・反乱のテーマを考える
祈りのドラマツルギー ――『リチャード三世』における宗教と政治
The Tragedy of Hoffman とエリザベス朝末期の王位継承問題
Perkin Warbeck における詩の真実
ある未亡人の変容 ――王政復古期のWebster 改作劇とエロティックな描写
<不在>を読む――The Island Princess における東インド表象
『ローマの俳優』における範例的寓意表現――劇中劇の破綻は何を表象するか
英国国教会Homilies と『テンペスト』
女王をもてなす――宮廷劇としての『恋の骨折り損』
“What see’st thou in the ground?”―― 裸体と風景、あるいはエピリアの読者について
セミナー(要旨)
19 世紀シェイクスピア絵画に見る男装のヒロイン ――ジェンダーと生物学的性差の観点から
鏡のイメージで読む『十二夜』――エコーとナルキッソス達
パラス誕生−『ゴーボダック』の黙劇と助言の作法
ルーシオウの悪ふざけ――『尺には尺を』における裁きと認識
ジョン王をめぐる二つの劇・反乱のテーマを考える
祈りのドラマツルギー ――『リチャード三世』における宗教と政治
The Tragedy of Hoffman とエリザベス朝末期の王位継承問題
Perkin Warbeck における詩の真実
ある未亡人の変容 ――王政復古期のWebster 改作劇とエロティックな描写
<不在>を読む――The Island Princess における東インド表象
『ローマの俳優』における範例的寓意表現――劇中劇の破綻は何を表象するか
英国国教会Homilies と『テンペスト』
女王をもてなす――宮廷劇としての『恋の骨折り損』
“What see’st thou in the ground?”―― 裸体と風景、あるいはエピリアの読者について
第44 回シェイクスピア学会を終えて楠 明子
2005 年度シェイクスピア学会が10 月9 日(日)・10 日(月)、日本女子大学目白キャンパスで催された。観光シーズンの連休であったにも拘らず、またほぼ一日中雨にたたられ悪天候であったにも拘らず、多数の協会会員の参加を得、大盛況の学会であった。会員の皆様のご協力に心より感謝申し上げたい。
目白駅からバスで10 分と地の利は実によいが、校門から一歩入ると緑多き閑静なキャンパスの別世界が広がる。日本女子大学は、周知の通り我が国で最初に女子高等教育を始めた学校の一つで、100 年以上の歴史を誇る。学会の研究発表、セミナーが行われた「百年館高層棟・低層棟」は、創立当時の学生が学んだ校舎を記念した建物なのであろう。百年前に女性が学問を志すということは、どんなに多くの困難を伴ったことであっただろう。現代の女性が一生の仕事として学問の道を自由に選べるのは、100 年前にこのキャンパスで学んだパイオニアたちの勇気と努力のおかげでもある。因みにシェイクスピア協会の現会員数は約700 名、そのうち半数弱が女性会員である。
学会初日の午後に行われた研究発表は、どの部屋にも多くの聴衆が集まった。長年研究に携わってこられた10 人の研究者に4 人の大学院在籍発表者を加え、14 本の刺激的な発表が行われ、その後活発な質疑応答がなされた。
2 日目には、チューダー朝のグレイト・ホールを思わせる由緒ある成瀬記念講堂において、シェイクスピアの翻訳と受容に関するパネルディスカッションが多くの聴衆を迎えて行われた。実際に現場の仕事に携わっておられる4 人の翻訳家・研究者による議論はさすがに現実的で、むずかしい問題を浮き彫りにする。フロアの温度も一気に上がり、休憩時間には質問を書くための白紙の調達に苦労するほどだ。学会でこんなに白熱したパネルディスカッションが行われたのは、ずいぶん久しぶりのように思われる。午後のセミナーのテーマは多岐にわたるが、どの部屋も熱心な聴衆で一杯。誠にうれしい限りであった。
懇親会は、かの有名な日本女子大学同窓会館の桜楓館で開かれた。予想をはるかに超える数のさまざまな世代の会員が全国から参加してくださり、一時の懇談に花が咲いた。協会とは長いご縁のある、Woolf 研究の権威であり卒業生でもある出渕敬子日本女子大教授もご出席くださり、日本女子大学の学生によるシェイクスピア劇上演の歴史等についての大変興味深いスピーチを聞かせていただくことができた。今回の学会の成功は、なんといっても開催校日本女子大学のご支援と、先生方、アルバイトの学生さんたち、事務の皆様の献身的なご尽力の賜物である。深く御礼申し上げる。
来年は協会創立45 周年記念の学会が開催される。すでにご案内してあるように、Shakespeare Institute のDirector、Kathleen McLuskie 教授を招聘し、「学会講演」「セミナー」を行う。セミナーリーダーはセミナーペイパーの投稿者のなかからMcLuskie 教授自身が選んでくださる。さらに、「記念論文集」刊行も企画している。会員の皆様には「セミナー」および「論文集」にどうぞふるってご投稿いただきたい。また、来年4 月に行われるシェイクスピア・ワークショップには、たくさんの大学院生が応募してヴェテランの研究者のアドヴァイスを励みに21 世紀の研究を進めてほしいと強く期待している。
第44 回 シェイクスピア学会報告
2005 年10 月9 日(日)・10 日(月・祝日)
会 場: 日本女子大学目白キャンパス
パネル・ディスカッション (要旨)
日本におけるシェイクスピアの翻訳と受容
 |
|
学会の参加者が一堂に会するパネル・ディスカッション形式は、東京でシェイクスピア国際会議が開催された1991 年の翌年に、現在のような複数のセミナー形式が始まって以来ごくまれなものとなっている。一度、第40 回学会(九州大学)において、「シェイクスピア研究、この100 年」(司会:柴田稔彦)という大きなテーマでパネルが行なわれており、ある意味で今回のパネルはその続編として、「シェイクスピア受容、この100 年」といった企画でもあろうかと理解される。とりわけ、シェイクスピアの受容にとって不可避の問題でありながら、これまで学会であまり取り上げて来られなかった「翻訳」が正面に出されたわけだが、ともすれば拡散しがちなこの話題、あえて「翻訳の現場」に焦点を合わせてパネリストを依頼した。打ち合わせはわずかのメールと2回の顔合わせのみであるにもかかわらず、当日の発言はそれぞれの豊かな経験と洞察を見事に示しながら、議論は相互にごく自然にかみ合って、まことにパネル・ディスカッションの成否はパネリストの顔ぶれによって決まるという、極めて当たり前の事実をあらためて思い知らされた次第。
フロアを交えての後半も活発で──上演を前提にした翻訳を教育の現場で用いることの可否は? 演出によって翻訳が影響を受けたことは?翻訳するテクストはQかFか折衷か、あるいは翻案の翻訳は? フェミニズム、ジェンダー批評が翻訳に影響を与えているか?──等々、縦横に議論が飛び交い、さらには──翻訳作品にいかに芸術性を求めるか? 昔の翻訳の方が芸術的個性にあふれていたのではないか?──といった刺激的かつ挑発的な意見も出され、不慣れな司会としては、与えられた時間の短さを惜しむばかりであった。
***
シェイクスピアの日本語翻訳の評価は、特に私のような外国人にとって、大変難しいものだが、翻訳の音楽性(musicality)、演劇性(theatricality) 、又は正確さ(accuracy)を三つの基準として考えるのも一つの方法だろう。音楽性は翻訳者がシェイクスピアの韻律をどのように解釈するかという点において効果的である一方、演劇性は取り分けサブテクストに関連している。正確さの問題は翻訳者に原典の間テクスト性(intertextuality) を考慮させる。又、社会性(relevance)という第四の基準は翻訳者自身のコンテクストを強調する。こうした基準は日本におけるシェイクスピア史上の初期の間に活躍していた夏目漱石や坪内逍遙の様々なコメントに実現されているが、逍遙自身は十分なシェイクスピア翻訳をすることに対して悲観的なようだった。しかし戦前の日本においても、シェイクスピアは確実な意味をもっているし、その意味は翻訳を通して伝えられると言える。 新しい学問の翻訳学(translation studies) でも、この四つの基準はフェミニズムやポストコロニアリズムのような理論的な批評に適用されるだろう。1928 年、小山内薫らが帝国劇場で、坪内逍遙訳『夏の夜の夢』を上演したとき、19 歳の村瀬幸子が、女役パックを演じて話題を呼んだようであるが、逍遙は翻訳の際に、シェイクスピアの女性登場人物を、情婦や(現代的には)ホステスではなくするために、苦労したようである。そして、シェイクスピア翻訳は、確かに、「新しい日本女性」のイメージを作り上げるのに多大な貢献をしている。ポストコロニアリズムにおいては、戦前、日本が海外理想や文学に門戸を開いたことは、ある意味で、日本文化を西洋の帝国主義から保護することに貢献した。シェイクスピア翻訳は、「空想の空間(imaginary space)」であり、土着の文化が過去やその他の空間と交渉するのを可能にする。しかし、日本におけるシェイクスピア翻訳と受容には──特に日本語自体の変容の中で──多くの研究課題が残されている。
わが国には、翻訳劇の台詞は何よりもまず《こなれた》ものでなければならないとする考え方がある。原作の文体はさまざまなのだから、こなれた日本語を選ぶことは必ずしも原作に忠実なやり方にはならないのに、この考え方は実に広く受容れられている。こういう奇妙な現象の背後には、劇の言葉そのものについての根本的な誤解があるのではないだろうか。科学の言葉の場合と違って、文藝の言葉においては語義(外延)だけでなく含蓄(内包)も重要である――時には語義よりも含蓄の方が重要である――のに、そのことに気づいていないひとがあまりに多い。近年の文楽の上演では、浄瑠璃の詞章が舞台上方に字幕として示される。しかし、どんな言葉が語られているかを目で確認しただけでは、文楽の鑑賞は成立しない。大夫が三味線の助けを借りて詞章をどう解釈し、その解釈をどのように表現するかを確認するのが、鑑賞という行為のいちばん重要な部分なのである。
シェイクスピア劇の台詞は浄瑠璃の詞章に劣らず難しい。たとえば、現代の英語圏の観客も容易には理解できない歴史的・宗教的状況についての言及が頻出するし、同じ単語でも現在とは異る意味をもっていることが珍しくない。しかも、基本的には韻文になっている。こういう台詞をこなれた日本語にするのは、一種の誤訳である(単語の誤訳よりも文体の誤訳の方が致命的だとさえ私は思う)。もちろんシェイクスピア劇を七五調を用いて翻訳するのは無意味である。だからシェイクスピアの日本語訳は散文にならざるをえないのだが、ただ、七五調を音数律だけを手がかりにして理解しなくてもいいのではないか。歌舞伎の台詞を語る時には、七音であれ五音であれ、ひとつのフレーズにふたつのストレスをおくのが原則であるようだ。音節の数ではなくてストレスの配列に規則性をもたせたら、リズム感に富んだシェイクスピアの邦訳が生れるのではないだろうか。
これまでのシェイクスピアの受容のされ方には、上演と読解という二項対立があった。翻訳においても、読者のために訳すのか、舞台のために訳すのかによって違うとされてきた。しかし、シェイクスピアの戯曲は演じられるためにある。テクスト対パフォーマンスという対立を超えて、音として認知されるシェイクスピアの言葉を考えたい。それは、シェイクスピアは声に出して味わい、聴いて楽しむものだという立場である。音読して初めてその美しさ、意味の深さ、リズムなどを総体として味わえるのだ。
「シェイクスピアの原文に忠実に訳す」という命題を立てたとき、何を以って「忠実」と言えるかは難しい。さまざまな意味やニュアンスを汲み取り、言葉が持つ力、響き、リズムに気を配ることすべてを完璧にすることは無理であり、ブランク・ヴァースを日本語で表現することはできない。翻訳者は常に絶望にあえぎながら、シェイクスピアを傷つけ、日本語という血液型の違う血を流し込んで、それでもなんとか生かそうと無謀な手術を試みるようなものだ。但し、英語の血が失われてしまうことだけを嘆くのではなく、日本語の血が入ることで、新たな命が与えられるのだと考えたい。
全作品が40 作になるということも含めてシェイクスピアのテクスト(原典)とは何かという問題がある。編纂のときと同じようにCopy-text(底本)の決定をしなければならず、特に底本がQ とF と両方ある面倒なケースに対処しなければならない。
翻訳には、正確さと日本語の表現力のほか、台詞として鍛え直す作業も必要だ。これは決して俳優が言いやすいように平易にするということではなく、三島由紀夫が仏文学者と共に行なった共同作業に匹敵する。シェイクスピアの言葉を、日本語として鑑賞に堪えるような台詞にするための努力が必要だ。
最後になるが、このシンポジウムで得た多くのご指摘やご質問に対して深く感謝したい。
これまで上演と出版のために17 本のシェイクスピア劇を翻訳してきた過程で、幾つもの課題が出てきた。たとえば原文の三位一体(多層な意味・イメージ・音韻)を生かす、先行訳では比較的軽視されがちだったイメージをつぶさないよう務める、解釈はするが演出しすぎない(原文をパラフレーズすることの必要と危険の自覚)、台詞に埋め込まれたト書きやきっかけに留意する、シェイクスピアの言わんとすることを先取りしない(「旅」の近道禁止)、人物ごとの文体の特徴を生かす、などである。
最近新たに加わった課題はシェイクスピアの台詞のmemorability =憶えやすさ(The Genius of Shakespeare におけるJonathan Bate の指摘がきっかけ)。なぜメモラブルなのか。理由としてイメージの鎖(連想)、音とリズムが考えられる。その完璧な例はMacbeth の ‘tomorrow speech’ である。To-morrow が「あした」と同時に「朝へ」を意味し、from day to day の後半が「today (今日)」に聞こえ、次行のall our yesterdaysを速やかに引き出す(明日―今日―昨日という連想)。「昨日」の集積が前方の死への道を照らす、ということからその光源たるcandle→ shadow→ player へ、then is heard no more のhear→tale へとイメージがつながる。さらに頭韻の適切な使用が挙げられよう。こうした特長に留意し、訳文もメモラブルになるよう努めたい。
台詞に対する「民主主義」を心がけると、小さなひと言から大きなことが見えてくる。オセローがデズデモーナの亡骸に向かって発するmy girl がその一例。他のシェイクスピア劇のmy girl はすべて父親から娘に向かって言われている。オセローとデズデモーナの年齢が父娘ほど離れていることの傍証にならないだろうか。
言葉の職人という自覚をもって翻訳に当たり、舞台人と読者と次世代に手渡したい。

第45回 シェイクスピア学会
2006年10月8日(日)・9日(月・祝)
東北学院大学土樋キャンパス(宮城県仙台市青葉区)
において 開催予定
研究 発 表 (要旨)
19 世紀シェイクスピア絵画に見る男装のヒロイン ――ジェンダーと生物学的性差の観点から高木 範子
本発表の目的は、シェイクスピアの男装のヒロインがヴィクトリア朝絵画の中でどのように解釈し直され、表現されたのかを考察することにあった。男装のヒロインが他の時代より女性らしく、また幼く描かれている段階を追って分析し、これらの絵画が19 世紀英国社会によっていかに利用されたのかを検証した。
はじめに、19 世紀に描かれた男装のヴァイオラが帯びている女性性を、当時の身体上の性差の概念や、理想とされた女性の内面や顔の造作、髪の色というジェンダーの観点から分析した。ヴィクトリア朝の男装したヒロインの絵画には、当時信じられていた生物学的性差や女性らしさの概念が投影された。社会の抑圧からの解放手段の一つとされている男装を施したヒロインは、19 世紀絵画において逆に窮屈なジェンダーに縛られているのである。
次に、18 世紀末から19 世紀にかけてのイモージェンの絵画を考察した。女性の体のしくみについての当時の認識や、弱々しい女性性への憧れというジェンダーの観点から論じ、男装をしているはずのイモージェンが多くの絵画のなかで仮死状態の女性の姿をとる理由を導き出した。画家はイモージェンを幼く描くことに飽き足りず、男装という設定を覆した上彼女の仮死という最も衰弱した姿を描き女性のか弱さを極限まで強調したのである。
19 世紀半ばに自らの権利を主張する女性たちが男性優位の社会秩序に挑もうとする傾向をみせ始めたので、当時の男性たちは危機感を覚え、科学者は男性の優位性を保つため女性を未熟な性と位置付けた。この時代に男装のヒロインを少しも男性らしく描くことができなかったのは明確な性差の概念があったからである。人を道徳的に教化する役割を絵画に担わせた時代のシェイクスピアの男装絵画は、両性の相違を表す道具となり、中産階級の女性のあり方を教え導いたと言えるだろう。
鏡のイメージで読む『十二夜』――エコーとナルキッソス達
金山 愛子
Twelfth Night を「エコーとナルキッソス」のコンテクストで解釈し、鏡のイメージを取り込んだ作品として分析した。Viola を特にMalvolio に代表されるナルキッソスたちの間に送られたエコーと解釈し、テキストの視覚的、聴覚的反射のイメージに着目した。その結果、 M.O.A.I. はMalvolio 自身の自己愛をあらわす外から内へ向かうアナグラムという読みが可能になる。
TN には鏡や、‘that is, and is not’(V.i.215) を体現する要素が数多く存在する。「三人目の阿呆」の絵も、Olivia とMaria の筆跡、そして変装のViola もそうであるが、Sebastian の出現で大団円を迎える。神話ではエコーはナルキッソスに拒絶されて肉体を失ったが、ここではSebastian の登場を契機に、エコーはSebastian の影であるCesario を辞めてViola となったのである。Twelfth Night というタイトルの意味については諸説があるが、Sebastian というもう一人の実体のepiphany により、絡まり合った恋のもつれがほどかれる様を暗示しているとも言えよう。
エリザベス朝のWindsor 城では、浴室の羽目板に鏡を張っていたという記録がある。またElizabeth I が最期に ‘a true looking glass’を所望し、これまで女王を褒めそやしてきた鏡を呪ったという記録もある。この場合の ‘true’ とは、鮮明に対象を映すガラス鏡を指すのではないか。Orsino の台詞 ‘the glass seems true’(V.i.263) を想起させる形容詞である。ここではtrue は幻影などではなく、生身の人間である実体を表す。それほど確かにglass はその前に立つ人間の姿を映す精度を持っていたと考えることができよう。TN を「エコーとナルキッソス」の物語に照らして、鏡のイメージに注目しながら読んできた。双子の出現を喜ぶ場面での鏡への言及は、ルネッサンス期にガラスで作った明晰な鏡がEngland にも入ってきて、鏡のイメージに進化があったことを表していると言える。
パラス誕生−『ゴーボダック』の黙劇と助言の作法
小林 潤司
『ゴーボダック』が法学院インナー・テンプルの降誕祭祝典 (1561/2) の余興として初演された際、この特殊な文脈の中で享受されることによって、今日悲劇だけを切り離して読んでも汲みとることが困難な特定の意味を発信したらしいことが、最近の研究の展開のなかで明らかになってきた。
個々の部分は、容易に一意的な解釈を許さない「謎」として提示され、他の部分と、もしくは部分の集積としての全体と、相互参照されることではじめて特定の意味を生成する。このような祝典の仕掛けを念頭に置きつつ『ゴーボダック』を読み直してみて再確認できることは、この悲劇自体が実は、これと共通する構成原理にもとづいて形づくられているという事実である。最初の二つの黙劇とそれぞれの後に続く劇本編の展開を対照してみると、享受者が相互を参照することによってはじめて意味が明確になるように仕組まれていることがわかる。
ベイコンがその「助言論」の中で紹介しているユーピテルとメーティスの寓話(懐胎したメーティスを出産前に呑みこんだユーピテルが頭からパラスを出産する)は、顧問集団の助言を賢く利用する法を君主に指南するとともに、臣下に対しては、一定の結論を最初から顧問集団の総意として上奏することが君主の威厳と体面を損ないかねない不適切なやり方であることを暗示している。これと同じ「助言の作法」が『ゴーボダック』においても示されていると考えられる。
意味の確定を遷延することによって示される、解釈を行なう享受者の主体性を尊重しているかのような身ぶりは、芸術的な技巧である以前に、絶対的な権力者の輔弼の任に当たる臣下が当然心得ておくべき助言の作法の実演として理解されなければならない。『ゴーボダック』は、作品の内容に注目すれば、助言を受ける君主の心得を説く芝居になっているが、同時に、その形式によって、君主に助言を授けようとする臣下に向かって範を垂れてもいるのである。
ルーシオウの悪ふざけ――『尺には尺を』における裁きと認識
高田 茂樹
本発表では、Measure for Measure の Vincentio 公爵について、彼が一面として Shakespeare の劇作家としてのありようを担っている点に着目して、その基本的な行動パタンとして代理の介在と窃視症的な認識様式が見られるということを論じ、そこから翻って、当時の Shakespeare が直面していたドラマトゥルギー上の課題と、それが内包する人間学的な意義を考察した。
公爵は、上記のようなやり方で、Vienna の町の風紀をただして、Angelo に自分の道徳的な不備を認識させることにそれなりに成功する。しかし、公爵のそういったやり方は、結局、彼にさまざまな事態に直接対峙して自分の行動に対して自ら責任を取ることを回避させて、彼が Angelo に対して求めるような自己認識を自分には免れさせるように作用しているように思われる。しかも、その一方で、彼は自分のシナリオをいっそう見栄えのするものにするために、過剰な演出を施そうとするのだが、そういった内実の伴わない演出は、むしろ、観客から見て、その技巧性を露わにして、彼の内的な確信の乏しさを浮かび上がらせることになる。
そういう Vincentio に対して、Shakespeare は、Lucio のようなとりわけ不埒な道化を当てて彼を当惑させることによって、自分のありようを託したペルソナの小賢しさを暴いてゆくのだが、しかし、そうやって公爵の小賢しさを暴く劇作家やそれに立ち会う観客も、そうすることで新しい認識の地平に至るということはなく、やはり同様の小賢しさの連鎖から脱け出せていない。
そういった人間の認識に必然的に伴う小賢しい自己正当化の悪循環から脱却する一つの方途は、劇の中で公爵を自らの代理である修道僧として人々の許に遣わす神の配剤に思いを致すことであろう。その神の配慮をすら小賢しいものと捉えるのか、それを人間的な理解を超えたものとしてそのままに受け入れるのか、二者択一的な答えのない問いを反芻しつづけるところに、この作品の一つの最終的な意義が認められよう。
ジョン王をめぐる二つの劇・反乱のテーマを考える
李 春美
本発表は、ジョン王をめぐる二つの劇における反乱のテーマに着目し、1580 年代後半から90 年代前半という時間枠の中で注視される主題が変化していることを明らかにする試みであった。ジョン王を王位簒奪者として前景化するアーサーの死を契機として始まる両作品の反乱のテーマは、王権の正当性を問題化するものではなく、アーサー問題を大義名分として貴族たちを反乱へと駆り立てた教会の扇動を危険視するものであると考えられる。それ故、両作品ともに反乱貴族をおおむね否定的に表象しているのだが、これは、1570 年以来、教会の説教壇から『不服従と意志ある反乱を戒める説教』が説いてきたものと同じメッセージ、即ち、反乱を戒め、国家的団結を説く目的があったと考えられる。しかしながら、シェイクスピアは、やがて仏皇太子の裏切りを知って改心 しジョン王のもとへ帰順する反乱貴族たちの表象を『乱世』のイメージとは異なるものとすることによって、両作品が触れても語らなかったマグナ・カルタ政争が後世において再評価されることになった、立憲君主制的メッセージをも発しているのではないかとの可能性を指摘した。つまり、シェイクスピアは、社会秩序の維持のため国王主権を強化するテューダー朝の支配的イデオロギーに抗うマグナ・カルタ政争を反乱貴族の表象の中にあからさまに書き込むことを避けてはいるが、国家の福利を思う反乱貴族への共感を加えることによって、国王主権を主張する女王に助言の重要性や、間接的ながら、法の上に位置する絶大な主権をもった国王の公正性に着目したと思われる。
祈りのドラマツルギー ――『リチャード三世』における宗教と政治
村井 和彦
本発表では、『リチャード三世』におとして表現されているかを考えた。『リいて、宗教と政治の関わりがいかに演劇チャード三世』はキリスト教の神という意味で使われる‘God’という言葉がシェイクスピアの全作品中、最も頻出する作品である。その点でこれは非常に素朴な意味で宗教劇であると言える。シェイクスピアはこの作品で祈祷書を小道具として用いた。それが可能となった歴史的背景として、16世紀から英訳版祈祷書が普及してきたこと、さらに、やはり16 世紀に盛んに使われた‘I pray you’、‘I pray thee’といった表現に見られるように「祈る」という行為そのものが世俗化していたことが原因と考えられる。これらの表現は単に‘please’の意味で用いられたのである。ふたりの聖職者を従えて祈祷書を持つリチャードの姿はチューダー朝の観客には生々しい政治性が感じられただろう。とは言っても、政情不安定な時代に自国の近過去の宗教と政治を劇化することは危険な行為であった。そこでシェイクスピアは、登場人物間の政治的関係を曖昧にする一方で、祈祷書を単なる小道具としてばかりではなく、その言語的構造を、作品のドラマツルギーの道具として利用したのではないかと論じた。「主の祈り」に見られるような、文法的法の転換、繰り返しのレトリック、直喩による論理の補強といった特徴は、作品の文体的特徴でもある。また、祈るという行為は呼びかける相手が眼前に存在せず、祈りを実際に聞くのは教会に集まった信者であるという隠れた構造も持っている。これらが作品の悲劇的アイロニーを観客に印象づける装置として、幾重にも仕掛けられている様を論じた。作品は呪いによる予言が次々と実現していく過程を辿るが、その中で登場人物たちは自らの呪いを祈祷文に近づけることで正当化しようとする。しかし、その努力がかえって劇の皮肉な成り行きを観客に予感させるのである。作品は‘holy communion’ の対象であるはずの神がマリノフスキーの言う‘phatic communion ’の道具へと変質する様を垣間見せてくれる。そして、芝居は‘Amen’という言葉で終わるのだ。
The Tragedy of Hoffman とエリザベス朝末期の王位継承問題
本多 まりえ
本発表ではHenry Chettle (c.1560-c.1607) 作のThe Tragedy of Hoffman(c.1602 )における「王位継承問題」を、エリザベス朝末期の社会状況と絡めて考察した。本作品は、復讐悲劇の一つとして軽視されてきたが、復讐のみならず、王位継承を始めとする政治問題をも扱ったという点で注目すべきである。
Hoffman の3 幕2 場で、外国人王子(Luninberg 公の王子Otho に扮する主人公Hofman)の王位継承を巡り、Prussia 公国で内乱が生じる。なぜなら2 幕1 場でPrussia 公が、実の息子Jerome を「愚鈍」という理由で勘当し、代わりにPrussia 公の甥、Otho に扮するHoffman を後継者としたからである。Jerome を支持する民衆は、Otho ( Hoffman )を“vnlawfull” (3.2. 1166- 67)、“false Prince” (1206) とみなし、“an arrant arrant Alien”(1239) と言って、彼の外国人としての立場を強調し、公国は二派に分断される。
王位継承の正統性を巡る問題は、当時の社会にも存在した。Scotland 王James 6 世が次期England 国王として有力視されていたが、外国人であったこと、母Mary が反逆罪でElizabeth に処刑されたことなどの問題があった。実際、民衆によるJames 批判は、裁判記録や幾つかの劇作品において表れていた。また、王位継承に伴う内乱への恐怖は、Dekker のThe Wonderfull Yeare(1603)の中で言及されており、人々はElizabeth 死後に宗教戦争が勃発することを恐れていたようである。こうした背景を考慮すると、Hoffman は、この劇を観た当時の多くの観客に、現実の王位継承という大問題を想起させる重要性をもっていたと言えるのではないだろうか。
Perkin Warbeck における詩の真実
石橋 敬太郎
John Ford 作Perkin Warbeck をめぐる批評史は、真の国王がHenry VII なのか、それとも詐称者Perkin Warbeck なのかに二分して展開してきた。しかし、このような批評ですら、ヘンリーの治世を再現する上で、なぜこれほどまでに劇作家が詐称者をクローズアップしなければならなかったのかという、本劇の成立と関わる本質的な問題について明白な回答を与えていない。この問題を考える上で、着目したのは、Perkin の主張する王国がもはや史実を離れて、詩的想像力の領域に属していることである。そのような手法に劇作家を導いたのは、Sir Francis Bacon のThe Advance-ment of Learning, Book II の詩に関する見解だったのではないか。Bacon によれば、イマジネーションを通して、感覚的な世界の上に築かれる詩は、真の歴史よりも人間の精神を高め、かつ威厳に満ちている。しかも、Perkin が何度も「言葉」としてエンブレム化されることを考慮すれば、Ford が目指したのは、英国史劇というジャンルの中に、人間の精神を満たすための詩的想像力の世界を復活させることだったと考えられる。その際に劇作家の意識にあったのは、Jonson 的な歴史意識からイングランドの政情を探り、王権が制限される前例を示すのを主眼とするステュアート朝に創作された、詩的想像力に乏しい英国史劇だったかもしれない。そうだとすると、妻Katherine を王妃とするPerkin の想像上の王国は、言葉が放つ魅力によって詩の真実を作り出そうとする演劇上の試みとして機能する。逆に、新王朝を整備する際にリアルなものだけを真実とみなして、Perkin の倫理的な王国を破壊しようするHenry の試みは、詩に対する演劇上の挑戦として位置づけられる。発表では、妻に対する愛と忠誠という倫理的な価値観を帯びたPerkin の想像上の世界を創造することにより、このジャンルにおける詩的想像力の重要性を主張する劇作家の試みを確認してみた。
ある未亡人の変容 ――王政復古期のWebster 改作劇とエロティックな描写
撫原 華子
James Shirley 作『枢機卿』(1641) は、劇場閉鎖の前年に上演許可が下り、王政復古以降も国王一座のレパートリーのひとつとして上演されていた芝居で、その種本として考えられている芝居のひとつに、John Webster 作の『モルフィ公爵夫人』(1614) がある。本発表において着目したのは、このふたつの芝居の趣が、若い未亡人である公爵夫人のエロティックな描写という点に関して、大きく異なっているということである。具体的にいえば、『モルフィ公爵夫人』の台本では描かれていた夫人のセクシュアリティ表象が、『枢機卿』の台本においては描かれない傾向にあるのだ。 本発表では、王政復古期に上演された芝居の一つのケース・スタディとして、『モルフィ公爵夫人』の公爵夫人と『枢機卿』の公爵夫人Rosaura という、ふたりの公爵夫人のセクシュアリティ表象の間にみられる変容を、王政復古期における、商業劇場への女性俳優の登場と結びつけて論じた。たしかに、『枢機卿』はShirley が少年俳優によって演じられることを前提に、劇場封鎖の前年に書いたものだ。しかしながら、『枢機卿』は、約20 年後の王政復古期の演劇界にみられる流れのひとつ、つまり、「女性登場人物のセクシュアリティが台本中から消えてゆくという、『枢機卿』以降のWebster 改作群中にみられる流れ」を先取りしているようにも思われる。「女性俳優が、女性登場人物を演じるようになった王政復古期の商業演劇の舞台においてもなお依然として上演されていた」という事柄に着目して、改めて『枢機卿』という芝居を読み直すとき、王政復古期の演劇におけるセクシュアリティ表象をめぐる事情の一端、つまり、エロティックな描写が「台本」ではなく、「女性俳優の演技」を、すなわち女性の身体性そのものを媒体として表現されていた可能性、が垣間見えてくるように思われるのである。
<不在>を読む――The Island Princess における東インド表象
末廣 幹
初期近代イングランドの演劇に見られる地理的想像力に関する研究は豊かな成果を残すいっぽうで、『テンペスト』のポストコロニアル的読解に見られるように、〈大西洋〉パラダイムへの偏重という弊害も生み出している。本発表では、このような不均衡を是正するために、John Fletcher のThe Island Princessを取り上げ、〈東インド〉表象の特異性を分析した。この芝居が上演された1621 年という時期は、〈東インド〉においてイングランド人とオランダ人とが緊張関係を高めている最中であったのだが、Fletcher は、物語の時代をオランダ人が〈東インド〉に進出する以前に設定することで、劇中ではポルトガル人と現地の住人しか登場させていない。つまり、この芝居は、イングランド人とオランダ人とを〈不在〉にすることで、同時代に深刻な問題となっていたイングランド人とオランダ人との対立を表象していない。また物語の構造に注目してみると、Ruy Dias やArmusia らポルトガル人たちが主要登場人物とされ、二人の決闘が芝居の中間部に挿入されてはいるのだが、この芝居は、ヨーロッパ人同士の対立に焦点を当てるよりも、むしろヨーロッパ人と〈東インド〉の人々との交渉をドラマ化していることがわかる。つまり、〈東インド〉は、ヨーロッパ人同士が香料という富をめぐって争う場ではなく、ヨーロッパ人が異教への改宗の恐怖を克服して異人種間結婚を成就するロマンス的空間として表象されているのだ。1620 年代には、国王ジェイムズ一世が親スペイン的な外交政策を推したために、国民感情がかえって親オランダ的な方向へと傾いていたので、Fletcher は、〈東インド〉におけるイングランド人とオランダ人との対立を表象することを回避したのではないだろうか。すなわち、テクスト中で表象されるポルトガル人は、イングランド人やオランダ人を〈不在〉として表象するための、不在証明、つまりアリバイにほかならないのだ。
『ローマの俳優』における範例的寓意表現――劇中劇の破綻は何を表象するか
内丸 公平
『ローマの俳優』における範例的寓意表現――劇中劇の破綻は何を表象するか Philip Massinger のThe Roman Actor(1626 年)は三本もの劇中劇を含む特殊演劇的な戯曲であるが、その特殊性を際立たせるのは演じられる劇中劇全てが何らかの形で破綻する/させられるからである。第一の劇中劇The Cure of Avarice は強欲の化身Philargus を改心させるために演じられるが、失敗に終わってしまうのだ。この劇中劇は人文主義的演劇弁護論を熱弁するローマの筆頭俳優Parisがその演劇思想を実践する場でもあり、Massinger 自身もこの演劇実践を意識していたことは彼の戯曲群から明らかである。にもかかわらずなぜ劇中劇は破綻してしまうのか。そしてその意味は何か。
範例として呈示される劇中劇の破綻の原因は当時起きていた範例的寓意の凋落にある。個が強調される近代化の過程の中で、個々の解釈を超越した場で成立可能な範例という形式の不可能性への意識が芽生えていたのである。The Cure of Avarice は実は当時擡頭していた「エンブレム」からの引用であるが、「エンブレム」は範例的寓意の凋落を背景として、伝統的認識コードが危機に曝された視覚藝術の危機への不安を象徴的に胚胎するものであった。この文脈に位置付けてみると、Philargus を初め各々の劇中劇の観客が劇の寓意を認識出来ないのは、彼らが恣意的なコードで劇を誤読するからであり、それが劇の表象行為と寓意内容との間に楔を打ち込むからだ。劇中劇の破綻は範例的寓意の表象不可能性に対する不安を表象するものなのである。
こうして演劇表象の危機を強烈に示す一方で、範例的演劇を目指したMassinger は、Massinger 的想像力と呼ぶべき彼固有の劇的意匠を凝らし範例的寓意を取り返すことを志向する。その手法は登場人物の性格の道徳的観点からの徹底した描写、表象行為の過剰な描写と劇構造の徹底した二元論化であった。この意味でThe Roman Actor は恣意的読みによって範例が失効するかもしれないという演劇表象の抱える問題とそれを取り返そうとする力の葛藤の表象であり、その批評的中心点が劇中劇の破綻にあったのである。
英国国教会Homilies と『テンペスト』
郷 健治
この発表はまずエリザベス朝の英国国教会欽定『説教集』のテクストが一定ではなく、版が重ねられるたびに誤植が混入し、本文の改訂が部分的に施されたこと、特に1582年版において多数の誤植と170カ所余りの本文改訂があった事実を指摘した。また、研究者が頻繁に引用する1623年(CERTAINE SERMONS OR HOMILIES appointedto be read in Churches, in the time of the late Queene Elizabeth of famous memory )が、この82年版を基にした上に多数の誤植を加え、更に300カ所に及ぶテクスト変更を施した改訂版であり、シェイクスピア研究には不適当である、と論じた。次に、この誤植の一例として‘Homily against Excess of Ap-parel’の中にある ‘a fit stale to blind the eyes of carnal fools’ のstale が1582年版以降17世紀末の版までずっとstable と印刷されていたことを報告し、このstale とその直後の ‘glittering shew of apparel’が『テンペスト』4幕の舞台で活躍する衣装 ‘stale to catch these thieves’/‘glistering apparel’ (Orgel 版4.1.187; 193 SD) に呼応している可能性を指摘した。そして、当時教会で続けて説教されていたこの‘Homily against Excess of Apparel’ と‘Homily against Gluttony and Drunkenness’とが『テンペスト』の4幕・5幕の筋書きの下敷きになっている可能性を、この2つのHomily と『テンペスト』との間に見受けられる幾つかの注目すべき類似点に着目して考察し、この観点から4幕の衣装が現在舞台で使用されているようなヒラヒラした安ピカの‘carnival costume’ の類ではなく、実は君主Prospero の豪華絢爛たる人の目を眩ますような ‘Rich garments’ (1.2.164) だったのではないか、と新解釈を提起した。最後に、『テンペスト』をMontaigne の随想 ‘Of the Cannibals’ 全体を材源にした作品として読み直す、という新しい試みを論じ始めたところ、残念ながら時間切れとなってしまいました。
女王をもてなす――宮廷劇としての『恋の骨折り損』
米谷 郁子
同時代のRoyal Entertainment や宮廷劇との関わりから、Love’s Labour’s Lost (LLL) について再考した。鹿狩りへのアリュージョン、ソネット作り、マスクとカウンターマスクの応酬、歌まじりのパジェント。これらのエンターテイメントとのつながりを強く意識させる諸要素やスタイルが、LLL では直線的プロット仕立てではなく、狭い範囲内の異なる場所で同時多発的に起こるドタバタとして繰り広げられる。LLL は、「エンターテイメント」というスタイルそれ自体に自覚的であっただけでなく、この確立されたスタイルを過剰に演じ直し反復するやり方には、エンターテイメントという制度への懐疑もうかがえる。芝居の中で女性たちはペトラルカ風スタイルを徹底的に拒否し、男性たちにとっての「秩序」を悠然と撹乱しつつも、エンターテイメントには積極的に参加する。男性たちはといえば、あの「誓い」は最初から破られてしかるべきものだったと居直り、女性から拒否され続けることで逆説的に芝居の中心に留まる。Bevington は、この芝居に女性恐怖を見てとり、女性の「正しいセクシュアリティ」獲得の場、あるいは安定したジェンダーシステムを約束する場となるはずの「結婚」という望ましい結末の破綻に、男性側の不安を読み込んだ。が、失敗続きの催し物を繰り返した末に結婚という大団円にたどり着かないことそれ自体、「女性嫌悪」論をはるかに超える意味をもつ出来事なのではなかろうか。結婚という結末へ向かう目的論的予定調和の枠組みのパロディ化。女王への求愛の成就不可能性。結婚を祝すであろう「花嫁の父」の永遠の不在。老いた女王をもてなすエンターテイメント、及びそのようなエンターテイメントを描く芝居としてのLLL が目指した世界とは、女王をもてなし崇拝するためにこそ、あらゆる誓いや求愛行為を、もともといずれは破綻する装置として芝居に仕込むことへの自虐を伴う楽しみにあったのかもしれない。
“What see’st thou in the ground?”―― 裸体と風景、あるいはエピリアの読者について清水 徹郎
官能文学の女性読者について確実な記録が残るのは17 世紀もかなり時代が下る。Venus and Adonis の「女性読者」の記録も初期のものはおおかた男の不安を映す幻想であった。ではV&A に想定される本来の読者とテクストとの関係はどのようなものだったのか?
ここで考慮すべきはElizabeth I 治世後期のVenus 像の変貌と読者層の変質である。
女王の婿選びが現実的政治課題だった70 年代まで、異教神話の女神たちは個々の属性を強調し差別化されたが、80 年代からその差異は意味を失い始めた。Hero and Leander のMarlowe を経て、喜劇詩人Shakespeare が登場するに及んで、Venus はDiana とも明確な区別がつきにくくなる。カトリック信仰の女神をも連想させつつ様々な神格の属性を兼ね備えるVenus 像は、宗教改革後の不安な時代精神を映す新しい神話に相応しく、原初の複雑で豊穣な神格に似た。それはまた、新プラトン主義風のイメージを詩人が戯れに用いたものだったかもしれない。
さてエピリアの読者層は、もとは大学や法学院の学生を中心とする限られた男性サークルにあったと推測される。だが出版を見込んだSh のV&A などが想定する読者の男たちは、多分に流動的だったのではないか?若い女あるいは男の裸体を読者が覗き見するのがエピリアに多いスタイルであったとすれば、Sh の読者も、語り手の詩人に導かれ、Venus の滑稽な姿態を覗き見し笑うように誘われる。だがVenus の裸体とその風景は、他でもない読者自身の住まうイングランドの田舎の風景だ。それはまた女王の身体が象徴する国の風景でもあった。問題は、女神の裸体と風景を覗き見する読者の身に起こるべき変容であろう。いつしか女神の目を通してAdonis を見る読者は、知らずして女性に変身する。女性化による国の弱体化を憂える人々によって加えられた詩・演劇への批判をものともせずに、詩による女性化を謳歌したのがAll Ovids Ellegies の翻訳者Marlowe であったとすれば、V&A の詩人も同じ路線を進んだ。「変身」させられる読者は、やがて劇場再開を待って花開くSh 喜劇の理想的な観客になるであろう。現役女王の君臨とともに、そのような読者の存在が、劇場という虚構の場においてSh 劇のヒロインたちが活躍することを可能にした。実質上、Diana 神話と合体したVenus の神話は詩と劇場の究極のパトロネスたる女王への特異な讃歌として機能した。
セミ ナ ー (要旨)
殉教史とエリザベス朝演劇
 |
|
近年、シェフィールド大学のデイヴィッド・ローズ教授を中心に、Acts and Monuments の校訂版を作るプロジェクトが進められ、その一環として、ジョン・フォックスの歴史叙述を様々なコンテクストから捉え直し、そこからイギリス宗教改革後の文化全体を再考するという試みが盛んに行われている。近代初期イギリスの演劇においても、殉教史・殉教物語(Martyrology)という視点は極めて有用なはずなのだが、殉教史と演劇との関係性を扱った研究はそれほど多くないという印象がある。そこでこのセミナーでは、殉教史や殉教物語を演劇文化というコンテクストから捉えることにより、殉教史はエリザベス朝演劇に何をもたらしたのか、さらにはそこから、演劇と宗教とはどのような結びつきをしていたのかということへの理解を目指した。勿論、殉教史と演劇の関わりはジョン・フォックス全盛のエリザベス朝に始まるわけではない。むしろその歴史は長く、少なくとも聖人の生涯や殉教を扱った中世の聖人劇(Saint Plays) にまで遡ることができる。そこで先ず、聖人崇拝と聖人演劇の両面にわたるプロテスタント的開拓に着手した宗教改革者ジョン・ベイルの1530 年代から1540 年代にかけての仕事を隠れた出発点として設定した上で、それが新たな展開を迎えたと思われる1570 年代から考察をはじめた。
具体的な手順としては、まず司会者が1570 年代にノリッジで執筆されたナサニエル・ウッズの道徳劇The Conflict of Conscience を扱い、プロテスタント・インタールードにおける聖人劇の新たなる展開について考察、続いて山田雄三氏が、1580 年代から1590 年代にかけての大衆演劇、特にシェイクスピアのTitus Andronicus とクリストファー・マーロウのEdward II に注目し、ジョン・フォックスのActs and Monuments に窺える肉体的苦痛に大衆演劇が目を付け、戦慄のリアリズムを獲得していく様子を論じた。その後、森祐希子氏がベイルなどの劇作家によって取り上げられているサー・ジョン・オールドカースルに焦点を当て、The Famous Victories of Henry V、シェイクスピアのHenry IV, Pt. 1 & Pt. 2, そしてSir John Oldcastle, Pt. 1 を中心に、オールドカースルが年代誌やシェイクスピアらの劇作家によってどのように扱われたかを考察し、さらに小野功生氏が、その後内乱あたりまで、トマス・ヘイウッドのIf You Know Not Me, You Know Nobody, Pt. 1 & Pt. 2 などの演劇やパンフレットを中心に、殉教物語が様々な形で領有され、世俗化されていく様子を論じた。最後に玉泉八州男氏が1590 年代から1620 年代までのActs and Monuments を題材にとったフォックス的な演劇群を総括的に扱い、その興隆と衰退について具体的に論じた。
これらの発表によってセミナー・メンバーは、大きな文化的コンテクスト、或いは限定的なコンテクストの中で、演劇における殉教者表象を捉えつつ、それがいかに多様性と重層性を持っていたかを明らかにした。例えば、小野氏や司会者が指摘したように、演劇が様々な利用価値を帯びた殉教者の言説を領有しながら、政治的なプロパガンダとしてイングランドの国家形成に貢献したこと、或いは玉泉氏、森氏が指摘したように、フォックスのActs and Monuments と同様、演劇が反教皇主義という世界観を提供する歴史叙述として貢献したことなど、これらの点は十分に検証することができる。しかしその一方で、少数派は抵抗運動のために演劇というメディアが殉教史を領有し、国家形成を阻害する可能性をおびてしまう(司会者、小野氏)。また演劇が殉教物語の空欄に独自の形を与えることにより、フォックスでは描かれなかった戦慄のリアリズムを獲得する(山田氏)、或いは、職業劇作家が相対立する歴史認識のmulti-vocal な声を舞台に乗せる(玉泉氏)ことで、殉教者の真正さの微妙な揺らぎを描き、歴史記述という行為そのものに冷めた視線を向けてしまう(森氏)など、結果的に演劇は、政治=宗教の一枚岩的な歴史を描くことを不可能にしている。そういう意味では、演劇と殉教史との緊密な関わりあいは、国家形成において必ずしも有益なものとばかりは言えなかったのかもしれない。
70 年代からしばしばカトリック的・偶像崇拝的な娯楽施設として攻撃されていたことからも窺えるように、劇場は、書物の図版と同様、迫害を受ける殉教者の身体を視覚的に、衝撃的に観客に提示することのできる空間であった。異端審問のディベートのような教育的な、或いは歴史認識的な言説もさることながら、視覚的なリアリズム、或いはセンセーショナリズムを提供できる施設だった(山田氏、小野氏)。そういう空間が殉教史と結びつくときに、劇場は絵画と同様観客の世論を操作する強力なメディアとなる。視覚化され、衝撃的リアリズムで描かれる殉教者が、見ている者の感情に直接的に訴えて、イデオロギー運動への参加・協力を促すという社会的役割を持ったのである。しかしながら1600 年前後、殉教者物語がプロテスタントとカトリックの双方から次々と編み出され、それが飽和状態に達すると、殉教者の真正性や聖性自体には意味を失いはじめ、またフォックスに食傷気味の人々の間に「殉教アレルギー」が急速に浸透する(玉泉氏)ということになる。そこでは、真の殉教者が誰かという問題は、政治的な立場や誰が領有の主導権を握るか(小野氏)、或いは誰が歴史叙述をするのか(森氏)によって、異なる様相を呈するようになるし、演劇のレベルでは、それが早い段階から起きていたように思われる。おそらくそれは職業劇団が客入りのために党派性を薄めたエキュメニカルなフォックス劇を提供せざるを得なかった(玉泉氏)ことと関係があるのかもしれない。殉教者の真正性や聖性が意味を失いはじめるということは、すなわち歴史や宗教が教える死の意味が曖昧になる(山田氏)ということでもある。おそらく演劇はそこから新しい聖性を帯びた英雄、或いは新しい世界観を吹き込んでくれる英雄を模索することになったのであり、そこに至って殉教史が本来帯びていた鮮烈な宗教的熱狂のエネルギーは、エリザベス朝演劇から次第に失われていったと思われる。
当日はフロアから有意義な質問を数々頂いた。この場を借りて御礼を申し上げたい。
(文責:井出 新)
書誌学・本文研究の現在
 |
|
発表者は、それぞれが関心を持つ書誌学の領域で最新のオリジナルな成果を披露し、日本では比較的馴染みが薄い書誌学という研究分野が持つ「意外な面白さ」をお伝えできればと考えた。既存の先行研究を踏まえ独自に調査した研究の成果を、多くの画像をごらん頂きながらなるべく視覚的でわかりやすく工夫して発表した。今後この分野に関心をお寄せいただく方が少しでも増えれば、との願いも込めてのことであった(以下発表順)。
英は、Thomas Creede が印刷したThe Famous Victories of Henry V のQ1(1598) とQ2 (1617) の印刷工程と出版事情について論じた。作者不詳の劇作FV は、Shakespeare の1 Henry IV 、2 Henry IV 、Henry V のソースの一つとして広く知られ、またbad quarto の代表例としても認知されているが、その一方で独立した書物としての研究は依然手薄である。その意味で、この発表はその不足を補う狙いで行われた。
はじめにtitle-page imprint 、collation、フォント、現存するコピーなど基本的な書誌学情報を示したのち、ファクシミリを使った校合の落とし穴になりうる例を二点図示した。また先行研究によって発表されている植字工分析について、再調査した結果に基づき、より詳細な論拠を提示して従来の説を補強。さらにQ2 のtitle-page がキャンセルされているというこれまでの説を、不規則に現れるwatermark を検出することにより書誌学的に立証した。またCreede 以来の版権の委譲を調査した結果、Q2 は版権に関して明らかに違反のある出版であることを指摘。Q2 を印刷したBernard Alsop に関する資料から、彼が書籍業組合のルールを無視して罰金も覚悟の上でQ2 を敢えて出版した可能性があることを示唆した。最後にQ1 とQ2 に見られるヘッドラインがどのようにして再利用されていったか、そのパターンを分析し、それに従来提唱されている一般的な植字・印刷のスピードを加味して、二つの書物の印刷工程の仮想モデルを推測した。
池田は、「The Book of Fayttes of Armes & of Chyualrye (1489) の印刷工程――Set-off (裏移り)が示すもの」と題して、以下の発表を行った。英国初の印刷人William Caxton が1489 年に印刷出版したThe Book of Fayttes of Armes and of Chyualrye (STC7269) には、調査した7コピーに平均して10%を超えるページ数のset-off「裏移り」(裏が透けて見える「裏写り」は除く)が残されている。一方、Shakespeare のFirst Folio (F1) には、Peter Blayney の研究を中心に3 ページのset-off が報告されている。それらは、Favyn, The Theater of Honour and Knighthood (STC 10717) からのtympan-cloth による裏移りであり、同じ工房の同時印刷を証明するものとされている。また、今回のセミナーをきっかけにThird Folio (F3)にも、これらとは異なった経緯で出来たset-off があることが発見された。これまでほとんど研究されてこなかったset-off という「印刷の不規則性」を示す現象に着目して精査することで、この現象が未だ不明であったCaxton の印刷工房における一工程、特に印刷直後から製本に至るまでがどのように行われていたのかを示唆していることがわかった。Set-off は、印刷による印字やインクが乾くまでのごく短時間に何らかの理由による接触があって別のページに印字やインクが移ることをいう。そうした非常に限られた短い時間にのみ起こりうるという事実を考えると、まさにこの現象はその印刷工房で起こった事柄を如実に示した結果であり、書誌学研究において見過ごすことの出来ない事実の集積であると思われる。
Caxton がこの書物を、国王Henry VII の命を受け仏語写本を英語に翻訳して印刷出版したのは彼の晩年に近い頃であった。調査結果を分析すると、F1 やF3 のset-off と異なり、印刷時ではなく印刷後のset-off であることが明らかとなった。木製手引き印刷機を使った印刷では、インクのうつりをよくするため紙を予め水に浸していたが、両面を印刷した後、乾かし、今度は紙を伸ばすためにインクが生乾きの間に強い圧力をかけたとみられる。それこそがset-off を作った原因であろう。その上、調査したコピーのset-off された文字は何れも濃淡の不規則性が少なく、判読可能な明瞭さを持って裏移りしており、人的な力や偶然の産物というよりはむしろ機械的な圧力を意図的に掛けた結果とみられる。しかもそれがCaxton 印刷工房における通常の作業工程であったと考えられ、このことは今後の研究に貢献しうるものと考えた。
長瀬は、「Hengist − Stage Directions が示唆する本文の起源」というタイトルで、次のような発表を行った。Thomas Middleton によるHengist には二人の異なるscribe によって筆写された二つのマヌスクリプト、Portland MS、Lambarde MS と1661 年にHenry Herringman によって出版されたQuarto(以下Q)がある。マヌスクリプトとQ のテクストを比較した際に、大きな相違を呈しているのがstage directions (以下SD)である。本発表では二つのマヌスクリプトとQ のSD の相違に着目し、それぞれの機能を分析することでSD が変化した理由とそれぞれのテクストが何を目指して作成されたものであるかという目的を本文の起源に求め、考察を行った。
マヌスクリプトに筆写されているcostume 、property、music など舞台裏あるいは舞台袖の仕事に関するSD は、舞台上に存在しないmusicians や劇団員への指示を表しているが、Q にはその大半が存在しない。Q は台本の改訂後に書き換えの行われたテクストから印刷された可能性が極めて高く、costume 、property、music に関しては改訂者が敢えてSD に含めない選択を行っている。二つのマヌスクリプトの呈するSD は、上演に際して舞台上の役者への指示と舞台裏への指示を兼ね備えた実用性の高いものであり、上演の視覚的、聴覚的演出を総合的に意図している。
Q では、舞台裏への指示を意図したSD が改訂者によって削除されている一方で、読み手の便宜を図るSD が多く付加され、台詞だけでは理解しがたい場面の描写を行う。また、マヌスクリプトにおいて実際の登場より数行前に早めて記入されているentrance SD の多くが、Q では実際に登場すべきタイミングと同じ行に位置が修正されている。Q のみに存在する役者のaction を描写するSD は実際のパフォーマンスの視覚的要素をことばによって記録したことで、読者に上演の臨場感を与えていると言っても過言ではない。これらはHengist の上演に精通した人物が出版に際して、読者を意識したテクスト改訂を行う際に付加したものであると考えられる。
最後に住本は、「シェイクスピア・サード・フォリオの18 世紀マージナリア」と題して、明星大学図書館所蔵サード・フォリオの一冊に残された18 世紀読者の書き込みの事例について報告した。この書き込みはSir Thomas Hanmer のエディションからその脚注と巻末のグロッサリーをフォリオ本体とフライリーフにそれぞれ書き写している。発表では本体への書き込み全体の転写資料とHanmer 本との校合作業から得られたデータをふまえ、マージナリア筆者の転写行動の特徴を見極め、彼[女]の意図について推測を試みた。
本事例を報告する意味を、本書き込みが転写行動をcopy text と転写結果とを同時に広げて吟味・分析することができる資料であってひろく書誌学的関心の対象になりうることと、18 世紀におけるシェイクスピア版本の流通について考察する端緒になりうること、の2点に見出し、まずは転写ぶりの特徴2 点について実物の画像を紹介しながら論じた。(1)「忠実に」――書き込みは、ハンマー注全278 件(本文関係の注を除く)中241 件を転写対象に取り上げ、そのうちの190 件は原注の非常に忠実、正確な転写である。転写行動に一定のアクシデンタルズ(パンクチュエーション、省略形、大文字など)が観察される一方、書き損じに気づいた書き込み筆者が削除訂正したあとが残っている4箇所では、単語の置き換えといった転写作業で起こりがちな間違いの実例が確認されると同時に、筆者の正確な転写への意志が看取される。(2)「美しく」――グロッサリーを転写しているフライリーフでもレクトのみが使われているが、フォリオの紙質上避けがたい裏写りが転写を醜く/見にくくしないようにという筆者による細心の注意は随所で観察される。本来D2v (Wives )に書き込むはずの‘Nuthook’ についての注釈をLl1r(2H4) (同単語の唯一別の出現箇所)に移している事例はその最たるものであろう。
フォリオの方が複数巻仕立ての「現代版」に比して価格の点でも(読者によっては一冊本である点でも)有利であった可能性の高い18 世紀中期から後期にかけての時代においては、手持ちのフォリオをカスタマイズするこうした作業が手間に見合う価値を帯びていたことは容易に推測されるのではないか、と考察して発表を閉じた。
『テンペスト』を読む
 |
|
『テンペスト』は、万華鏡のように多様な解釈や改作を生み出す劇作品であり、王政復古期改作劇群、Browning やAuden の詩、Mannoni 著 Prospero and Caliban 、 映画 Forbidden Planet や Prospero’s Books 、蜷川『テンペスト』など、詩・演劇・評論・映画など、多岐にわたる分野において豊かなアフターライフを紡いできた。後の作家・批評家達にとって改作・解釈への強力な衝動につながってきたこの劇の魅力とは何か。本セミナーでは、インターテキスチュアル・リーディングを基本とし、参加メンバーの個々の視点からテキスト解釈の新たな可能性を探った。このような試みが必要であると考えたのは、Stephen Greenblatt 、Paul Brown、Francis Barker 、Peter Hulme らに端を発する新歴史主義・ポストコロニアリズム批評による『テンペスト』解釈は、斬新で刺激的なアプローチを示してくれたが、反面、その一般化の過程において植民地主義・新世界表象の側面が強調されて劇の豊かな原型・神話的意味作用に制限を加えてしまったように思われたからである。両イズム批評の嵐が過ぎ去った今、インパクトが強烈であったが為に、「言うべき事は言われ尽くした」というような閉塞感も漂っているのではなかろうか。そこで『テンペスト』の豊かな意味作用を見つめ直す糸口として大島序論「テキストとインターテキスチュアリティ」は、近年の『テンペスト』批評の多様性を取り上げながら、言説とテキストが生み出すインターテキスチュアル・リーディングの可能性をメタ批評的に検討した。特に、Barbara A. Mowat が論じたインターテキスチュアル・システムの詩学は、“Shakespeare’s books” だけではなく、劇作品を取り巻く諸言説との相互作用が重要であることを指摘し、そのようなインターテキスチュアリティの視点から、国王座付劇場詩人として作者が王権に関するメッセージとして劇冒頭に置いた政体論的エンブレム「嵐に遭遇した国家としての船」等の政治的意味を考察した。
道行論「モンスターと奇怪な出産」は、モンスター・怪奇出産言説から作品解釈に取り組んだ。『テンペスト』にはモンスターについての言及が多い。キャリバンや怪鳥ハーピーといったモンスターが舞台上に現れ、台詞やイメージにもモンスターの概念がたびたび使われる。奇怪な身体のモンスターはスペクタクルとしての存在感が大きいが、その存在意義が秩序回復の問題と絡めて考察された。唯一人の女性登場人物であるミランダは、後継者誕生の期待を一身に背負い、劇中には出産を期待する言葉が繰り返し語られる。しかし、出産への期待に影を落とすのが、モンスターの存在である。同時代に世間を賑わせた「怪物誕生奇談」を思わせるキャリバンとトリンキュローの合体シーンや、奇怪な出産のイメージは、後継者誕生と秩序安定への期待に不安を投げかける。モンスターは、観客の目を楽しませるスペクタクルであるとともに、大団円で終わるこの芝居に、暗い影を落とすダークな存在でもあることが論じられた。
政治的な不安は、王政復古期改作群にもつきまとう。松田論「スペクタクルと政治性」は、Thomas Shadwell によるオペラ版The Tempest or the Enchanted Island(1674)の仮面劇の機能を検討した。オペラ版『テンペスト』において、仮面劇は政治的和解を予見しない。仮面劇に登場するのは、風神イーアラスと、それを従属させる海神であり、イーアラスは、海神の持つ強大な力に膝を屈し、嵐を静める。オペラ版『テンペスト』が、政治的対立の調和というアレゴリーを捨て、不和を題材に選ぶのはなぜか。この問いに答えるために、同時代的状況に目をむけ、仮面劇に表されている不安が、1674 年当時の英蘭戦争と、それによって誘発される対カトリック社会反応を反映していることを確認した。英蘭戦争に対する同時代的言説と同様に、オペラ版『テンペスト』の仮面劇において、外部からの脅威と内部への不安は常に連動した形で可視化される。プロスペローが劇の結末で述べるように、王政復古期の「魔法の島」は今や楽園ではなく、「避難所」である。ここにこそ、仮面劇がスチュアート朝から、王政復古期に「移動」した際のスペクタクルの政治的変容を見て取ることができると松田氏は論じた。
勝山論「植民地経営と内政問題」は、上演当時の植民地言説と労使言説を再確認しながら、劇の意味作用の原点に立ち返る。近年の『テンペスト』批評は、ポストコロニアリズムの立場から、劇中に帝国主義的植民地支配と原住民との間の文化の衝突や摩擦を読み取ろうとしてきた。しかしヴァージニア植民に参加したJohn Smith の報告が物語るように、新大陸への植民政策が始まったばかりの17 世紀初頭における植民者と原住民の関係は、明確な支配・被支配の関係を形成するにはいたらず、むしろ驚異と困惑に満ちたものであった。当時のイングランド人にとっての最大の関心事は、原住民との遭遇をとおして自分たちの内面に生ずる恐怖や不安をいかに克服し、受容していくかという精神的葛藤であったにちがいない。劇は、新大陸の労働に、本国イングランドの主従関係や徒弟制度をあてはめ、他者を本国の労働階層へと組み込むことにより、人々の内なる精神的葛藤を克服しようとする試みに他ならない。1609 年、植民地計画が思うように運ばないことに苛立ちを覚えた植民会社は、初期の植民地政策を見直す必要から、植民者たちの自由を制限し労働を強化することを謳った第二憲章を発布している。このような経済効率を優先した植民地経営方針は、劇中に描かれた主従関係をとおして糾弾され、より理想的な伝統的主従関係のあり方への希求が、劇の結末で再確認されているのである。勝山論は、『テンペスト』は、ユートピアという名の現実を見つめ、あらためて観客にその意味を問いかけていると主張した。
高森論「記憶と語り」は、「記憶」と「語り」を手がかりに、プロスペローによる支配の構造を明らかにするとともに、各登場人物の記憶に焦点を合わせながら、記憶を媒介として自己と他者が、過去と未来が築く関係性について論じた。卓越した語りの能力で他者の記憶を操るプロスペローは、ミランダの空白の記憶を形成し、エアリエルから領有したシコラックスの記憶をもとに、逆にエアリエルの記憶を支配して服従を誓わせる。キャリバンには記憶操作は失敗するものの、アロンゾー一行には罪の記憶を蘇らせ、良心の呵責に苛ませることで復讐を果たす。そもそも敵の一行を島に呼び寄せたこの度の企てそのものが、プロスペロー自身の王位簒奪の過去を再現し、修正するための試みであったのではないか。劇中二度にわたって繰り返されるクーデターを、今度はプロスペローが未然に阻止する。反逆者たちを赦す行為は、プロスペローにとっては自らの過去との、苦い記憶との和解の行為でもあることが指摘された。
最後に、古屋論「プロスペローと複合的イメージ」は、筋の展開と劇的状況に深く関わり、しかも他の劇中人物に対して圧倒的優位に立つ主人公プロスペローの複合的イメージを検証した。曖昧さを漂わせながらも筋の展開の中で確実に構築されているプロスペローの “project” をめぐって、劇全体に見られるその関連語と文脈、および特に彼が多用する “my 〜” の用語に注目して、その効果を分析した。妖精エアリエルや愛娘ミランダ、さらに弟アントニオへの呼びかけの多さによって、プロスペローの彼らへの特別の思い入れが感知される。嵐を起点とするプロジェクトについては、その中核をなす娘と敵王の王子との結婚、12 年前の加害者アロンゾー一行への復讐(懲罰)から赦しへの劇的展開、そして和解を見据えたロマンス劇としての大団円の結末を読み解いた。
セミナー後半では、約五ヶ月間のメール討議で問題意識を共有してきた「モンスターとスペクタクルの政治的意味」、「政治世界の位置 新大陸orアイルランドor地中海」、「プロスペローvs. キャリバン言葉と記憶」という3トピックに関するメンバー間の討議の後、フロアからの質疑も交えて活発なディスカッションが行われた。「モンスターとスペクタクルの政治性」については、アンチマスクからマスクへという通常の順番が劇では逆転していることなどにより不安が強調されていること、王政復古期においては女優の登場などとも関連しキャリバンのモンスター性よりも妹シコラックスの性欲がより顕在化していることが指摘された。「プロスペローvs. キャリバン」については、記憶から物語を、物語から「歴史」を生成するプロスペローにとって、キャリバンの記憶力の良さと雄弁さは脅威であり、記憶を回想として語りながら、彼は絶対者のフィクションを打ち破る自らの物語を提示していることが指摘された。「政治世界の位置」に関しては、モンスターの材源の観点から見ただけでも、 Pliny や Virgil などの古典的旧世界と、Mandeville などの中世旅行記文学、新世界との遭遇(“dead Indian”) などが入り混じっており、この作品の地理的設定に幅を持たせる要因となっているが、それに呼応して『テンペスト』批評も、新大陸、アイルランド、アフリカ、地中海と広範囲な地理的広がりを見せていることが指摘された。当時のイングランド人が思い描く様々な異国の情景が多層的な重なりを形成し、作品を構築していることを忘れてはならないし、イングランド本国の労働実態など、作品を取りまく歴史的・政治的・文化的文脈が与えた影響も無視できない。このような歴史主義的研究と共に、劇作術に活用される独特な詩学への理解の重要性や、詳細な言語分析に裏打ちされたジャンル研究・キャラクター批評の手法の効果も再確認されたが、さらに「記憶」論や「モンスター」論など新たな文化理解へのアプローチを取り込んだインターテキスチュアリティ研究、アフターライフ研究こそが、豊かな意味作用を特質とする『テンペスト』解釈のこれからにつながるのではなかろうか。21 世紀に於ける更なる『テンペスト』批評の展開が楽しみである。
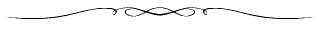
♠ PDFファイルをご覧になりたい方は、こちら へ
