日本シェイクスピア協会会報
Shakespeare News
Vol. 49 No. 2
January 2010
学 会 特 集 号
| 第48回学会を終えて | 安達 まみ |
学 会 特 集
特別講演(要旨) 「恐怖を舞台に」
青山学院大学教授 富山太佳夫
研究発表(要旨)
服飾と身体の交錯 —— Othello におけるハンカチ再考
「終わりよければすべてよし」なんて、いったい誰が言ってるんだ
『ロミオとジュリエット』における時間と作品構造
「不思議の国」のハムレット
シャイロックのナショナリズム —— 『ヴェニスの商人』試論
‘Disposed to mirth’: The Humour of Antony and Cleopatra
The Sword of Freedom and the Freedom and People’s Rights Movement
『オセロウ』受容史再考のために —— 宇田川文海『板東武者』(1892)
Birmam Wood への新たなアプローチ —— Macbeth における男性性の幻想
『スペインの悲劇』における女性表象と〈終わり〉の感覚
戦後ジャンル映画におけるシェイクスピア受容のインターテクスチュアリティ
—— 『荒野の決闘』から『悪い奴ほどよく眠る』まで
シェイクスピア時代における ‘within’の意味と用法
悪役になりたい —— サンドフォード・シバー・リチャード三世 ——
なぜイモインダは白人に変えられたのか?
オペラなのか英雄劇なのか —— ウィリアム・ダヴェナントの『ロードス島の攻囲』に見られる不確定性 ——
「バター売り女」、来る —— ベン・ジョンソン作『新聞商会』における「バター」比喩の展開
『第二の乙女の悲劇』のダブル・プロット構造の再検討
イタリアとの邂逅 —— Gascoigne's Supposes
『ハムレット』とドイツ精神 —— ゲーテからヒトラーまで ——
セミナー(要旨)
《セミナー 1 》 ロマンティック・リバイバル —— 騎士道ロマンスとエリザベス朝文学
《セミナー 2 》 NEW SYNERGIES IN CONTEMPORARY SHAKESPEARE PERFORMANCE IN BRITAIN
| 国際学会報 | 末松 美知子 |
第48回学会を終えて安達 まみ
第48回シェイクスピア学会は2009年10月3日と4日に筑波大学にて開催されました。緑豊かなつくぱの地で、自然に調和して佇む現代的な会場を拝借できましたことはまことにありがたく、国内外の各分野の先端的研究を担われる機関としてお忙しい中、開催校および共催団体として数々のご配慮をくださった大学側の皆様に心より御礼申しあげます。また、学会担当委員にご助力を惜しまれなかった大学の関係者と学生の皆様に感謝申しあげます。本年度は例年を大幅に上回る参加者を得て、すべてのプログラムが成功裡に終了いたしました。皆様の協会への多大なご関心とご協力に深謝いたします
今回の学会では、研究発表に水準の商い応募が多数あったことを反映し、研究発表会場を5室設けました。実績ある研究者から気鋭の若手まで、シェイクスピア研究の層の厚さを実感させるプログラムであり、聞き応えのある発表揃いであったというご感想を多数いただきました。どの会場でも司会の方々のご配慮もあって活発な質疑応答が行われ、発表者にも有意義な場であったと思われます。二日日の特別講演には富山太佳夫氏を講師にお迎えし、小説と芝居の関係、芝居と小説の関係という根源的な課題をめぐり刺激的なお話を伺うことができました。読み巧者の水先案内人に導かれ、広大な文学の海を彷徨う旅人となった大勢の聴衆が真剣に聞き入るようすは印象的でした。また、2室のセミナーでは、入念な意見交換を行った上で当日を迎え、白熱した議論が繰り広げられました。なお、同時開催されたワークショップでは大学院生が積極的に討議し、コメンテイターに貴重なご助言をいただいたことを付記いたします。本号の学会特集では、当学会の模様とともに、末松美知子氏による示唆的な2つの国際学レポートをとおして、海外学会の動向と国際的な場での会員のご活躍をお伝えできますことは大きな喜びです。
さて、皆様のご研究の活況とは相容れない話題になりますが、当協会の財政状況について申しあげます。ご存じのとおり、当協会の運営はすべて基本的に会費収入で賄われております。一時は900名近くに達した会員数は、近年、毎年50名程度減少しています。昨今の人文系学問の置かれた状況を考慮すればむしろゆるやかな減少であり、一方で本年も新会員の加入があるのは心強いかぎりです。それでも会費収入が減少傾向にある事実は否めず、現状のままでは、5、6年もすれば協会財政は窮地に追いこまれます。現委員会も歴代委員会同様、献身的に各事業の運営に当たり、皆様の大切な研究活動の場を提供しつづけるためにお預かりした資金を有意義に使う工夫を重ねております。同時に、A4,1・の2号化のように必ずしもご期待に添わない場合があるのは残念ですが、協会の将来のために時々の財政状況に応じた節約が必要であることをご理解いただきますよう、衷心よりお願い申しあげます。
来年度は2011年の新委員会発足に向けて、委員選挙の年に当たります。木琴には委員選挙に関する重要な文書も掲載されておりますので、会員の皆様には、ぜひお目通しくださいますようお願いいたします。
特別講演 (要旨)
恐怖を舞台に
 |
|
まず第一に、イギリス演劇史の中にゴシック演劇というジャンルは存在するのだろうか。私自身、1973年にゴシック小説をテーマとした修士論文を書いたときにはまだ数冊しか手に入らなかったゴシック小説の研究書の数が、もう何10冊を超えるようになった今でも、ゴシック演劇というタイトルを正面から打ちだした研究書はまだ眼につかない(おそらくPh.D論文のレベルではあるにしても)。ゴシック小説の総花的な解説(いわゆるコンパニオン)や事典の類にもかろうじて登場したり、しなかったりという程度である —— ゴシック演劇というジャンルは。
そのことを承知の上で、シェイクスピア学会の特別講演のテーマとし て、私はこのゴシック演劇を取りあげることにした。英文学の研究をし ている以上、この程度のへそ曲がりは当然許されるはずであるし、まし てや日本シェイクスピア協会に秋葉原からつくばエクスプレスで出か けるとなれば、この程度の判断のブレが生じることには何の不思議もな いであろう。最初に使おうと思ったのは、例のオックスフォードのワー ルド・クラシックスに収録されているFive Romantic Plays, 1768-1821 ( 2000) であった。ここにはHorace Walpole, The Mysterious Mother (1768)が含まれているので、そこから話を始めて、同書のJoanna Baillie, De Monfort (1800)に話を進めよう。当時はシェイクスピアと比較されることさえあったこのスコットランド出身の女性作家の戯曲の話をし、彼女 の周辺にあった驚くべき知的サークルの話をしよう、そこには当時の演 劇界絡みのネタもあれこれあるのだから・・・・・というような計画を立てていた。
勿論これだけでは手軽すぎて、話をする側の私にとってもつまらない から、Joanna Baillie, Six Gothic Dramas (2007)も用意した。ともかく会 場では、おそらく参加者の誰ひとりとして読んでいないはずのこの作家 の作品について得々として語り、そして締め括りに大きな紙袋の中から 赤い装幀の3巻本を取りだす。数年前、神田の古本屋で3冊計900円で 手に入れたものである。表紙にはなんとWestminster Public Librariesと刻 印され、タイトル・ページの右下にはWithdrawn from St. Marylebone Public Librariesという判が押してある。そのタイトルはJoanna Baillie, Dramas, 3 vols. (London: Longman, Rees, Orme. Brown, Green, & Longman, 1836)。本そのものは別として、こんな奇妙なおまけつきの本はそれ こそ世界にこれだけということになるだろう。これを壇上でみせびらか して・・・・・というような計画であったのだが、計画がともかくまとまると、気が変わってしまった。
私の本職はイギリス小説の研究である。だとすれば、イギリス演劇史 のあまり研究が進んでいない分野に介入してあれこれ言うよりも、むし ろ演劇と小説の交差について話をする方が役に立つのではないだろう か。アフラ・ベーンの小説『オルノーコ』(1678年)がトマス・サザー ンによって同題で劇化(1695年)された例はあるものの――1992年に山 梨英和短期大学で第31回シェイクスピア学会が開催されたとき、セミナ ー2「The Tempest と新大陸――テキストとコンテキスト」で私もこの二 つの比較を試みたことがある――演劇と小説の関係が本格化するのは1 8世紀の半ば以降のことではないかと思われる。フィールディングやゴ ールドスミスのように双方のジャンルですぐれた作品を残した作家は この時期の人々であるし、ゴシック小説を旗上げしたことになっている ウォルポールもまたこの時代の書簡マニアである。勿論この二つのジャ ンルで同時に第一級の作家となるのは至難の業であったかもしれない が、両者の関係が基本のところで変化し始めたように感じられるのは、 この時代のことである。ゴシック小説、ゴシック演劇の出現がそれとほ ぼ重なる時期の現象であるというのは、単なる偶然だろうか。
ホラス・ウォルポールの『オトラントの城』(1764年)やブラム・ス トーカーの『ドラキュラ』(1897年)と比較してみるとよく分かること であるが――本当は、比較しなくてもすぐに分かることであるが――デ ィケンズの『大いなる遺産』(1860−61年)はゴシック小説の、それを 構成する不可欠の要素の、パロディとしての性格をもっている。『クリ スマス・キャロル』(1843年)の頭のところでもハムレットの父親をロ ンドンの某墓地にひっぱりだしてみせる小説家としては、別段驚くほど のことはないとも言えるだろうが。ともかくその冒頭を読み返してみる ならば、
私の父の家の名前がピリップで、私自身の名前がフィリップだった ものだから、幼ないときには両方の名前をはっきりと長く発音しても ピップにしかならなかった。それで、自分のことをピップと言い、ピ ップと呼ばれるようになってしまった。
父の家の名前がピリップだと言うのは、父の墓石と姉の――鍛冶屋 と一緒になったジョー・ガージャリー夫人――のせいである。私は父 の顔も母の顔も覚えていないので・・・・・
戯曲と違って、小説では、その書き出しを読むだけで傑作か否かがほぼ 推定できるというのが私の考え方であるが、この作品の場合にもそれが あてはまる。第1段落は間違いなく『ロビンソン・クルーソー』の書き 出しのパロディであるし、まず家系、家名を明らかにするというのは18 世紀以来の英国小説の定石であった。ただそのために持ち出されるのが 墓碑銘というのは実にあざやかな妙案というしかなく、唯一の血縁者と して残っている姉の嫁ぎ先から下層の労働者階級であることも示唆さ れている――しかも、孤児である。これだけの情報をわずか数行のうち に書き込める作家はざらにいるものではない。典型的なゴシック小説で は、物語の展開にあわせて、この〈孤児〉が実は立派な〈家系の血〉を 継承していることが判明し、城や領地などの〈財産/遺産を継承〉するこ とになる。物語の展開を支えるのは、そのような正統の継承に対する妨 害と略奪であり、それを引き起こす犯罪であり、その隠蔽と暴露にから む犯罪である。〈家系の血〉の継承を混乱させ、妨害するひとつの手段 として〈近親相姦〉を思いつくのは造作もないことであろう。
ディケンズはおそらくそうしたことを承知の上で、ヴィクトリア時代 の読者の、そして現代のわれわれの予測を適当にくすぐりながら、裏切 ってみせる。彼がそのためにとったのは、ピップ少年とどのような血縁 関係があるのか不明のミス・ハーヴィシャムを登場させるという手法で あった。彼女は挙式の寸前に相手に逃げられ、以来、変色したドレスに 身を包んだまま屋敷の外にはいっさい出ないという、それこそ妖怪的な 存在であるが、少年はその相手をすることをしいられるのである。
大きな木の梁に目を向けると・・・・・そこに、首から吊されたひとの姿が 見えた。黄ばんだ白いドレスに身を包んで、靴は片方だけ。・・・・・その 姿を見てふるえあがった私は、一瞬前にはそこにその姿はなかったは ずなので、よけいにふるえあがった私は、まずそれから逃げ、次には それに向かって走ってしまった。しかもそこにその姿がないことに気 がついたときには、私の恐怖は頂点に達した。
以前、湿地にある古い教会のひとつに連れて行かれて、教会の床下の 地下室から掘り出された、ボロボロの立派なドレス姿の白骨を見せら れたことがある。昔フェアで見た蝋人形も、白骨も、黒い眼を動かし て私を睨んだように思えた。叫び声をあげたくなるくらいであった。
私など前者の一節を読むたびにヴァージニア・ウルフの『オーランドー 』の冒頭を想起してしまうし、後者を読むと、ドラキュラ城の地下室で 棺の中に眠るドラキュラ伯爵を思い出してしまう。いずれにしてもディ ケンズがこの小説の中でゴシック小説的な想像力を思うがままに駆使 している(そして、そこから超出してみせる)ことは疑うべくもないよ うに思われる。
そのような小説の中に〈演劇〉が内在しているのだ、最も基本的なか たちで。
お婆さんの視線をさけるようにして、その前に立った私は、まわり のものを見て、お婆さんの時計が9時の20分前で止まっていること、部 屋の時計も9時の20分前で止まっていることに気がついた。
「私をよく見なさい」と、ミス・ハーヴィシャム。「あんたが生ま れたときからずっと太陽をおがんだことのないお婆ちゃんでもこわく ないわね?」
そのときは、残念ながら、「ハイ」という返事を含む途方もない嘘 をつくことを、私はためらわなかった。
「ここに何があるか、分かる?」お婆さんはそう言って、体の左側 に両手を重ねた。
「ハイ、分かります」
「何に手を触れている?」
「心にです」
「壊れた、ね!」
止まったままの時計の時刻の確認を別にすれば、完璧に舞台の上で演ず ることのできる場面と言っていいだろう。これは小説というジャンルの 成立期とされる18世紀には殆ど見かけることのないスタイルである。小 説の中の会話体の部分が演劇からの転用であることはまず間違いない のだが、その定着、というか、見事な使いこなしが達成されるまでには 長い時間を要したということである。勿論これについては、決してディ ケンズが最初のひとりということではない。ジェイン・オースティンの 『プライドと偏見』(1813年)の冒頭のベネット夫妻のやりとりは演劇 的な会話のやりとりが小説の中でほぼ完璧に実現した稀有の例ではあ るが、そのオースティンにしても、それ以外の場所ではそれがうまく達 成できているとは言いかねるのである。そのことは自由間接話法の使い こなし方の問題として、すでに研究されている。
もっとも会話的なやりとりの採用が小説の演劇化に必ずつながるか と言えば、そうは言いきれないだろう。夏目漱石の『草枕』(1906年) から引き出せる次のような例などをその論拠にすることもできると思 われる。
「旦那さんは」
「居ります。旦那さんの娘さんで御座んす」
「あの若い人がかい」
「へえ」
「御客はいるかい」
「居りません」
「わたし一人かい」
「へえ」
逆の方向から問題を立てるとどうなるだろうか。18世紀までは無理だ としても、19世紀以降、イギリスの演劇が小説的な手法を、成功したか 否かは別にして、作品の中に活用しようとしたことがあったのだろうか 。長編を小説の基本の形式としたヴィクトリア時代のことを考えれば、 これは意味のない問題設定と見えるかもしれないが、戯曲の側からの小 説へのにじり寄りを示唆する痕跡もなくはないのだ。そのひとつが評判 になった小説の戯曲化という流れであって、例えば『ジェイン・エア』 には6本の戯曲版があるし、世紀末のドゥ・モーリアの『トリルビー』 (1894年)にいたっては小説家本人の手で戯曲化されているのだ。その 意味では、民衆文化の形と質の変容にともなって、両者がともに享受さ れる時代に突入していったのだと了解すべきなのかもしれないし、考え てみれば、チャールズ・ラムの『シェイクスピア物語集』(1808年)も 演劇と小説の交差の流れのどこかに位置していたと言えるのかもしれ ない。
もうひとつの痕跡は、19世紀を通じて眼につくト書きの量の肥大化で ある。その背景には、戯曲もただ劇場で楽しむだけのものではなくなり 、家庭内で読まれるテクストに変貌していき、一般の読者の情景的な想 像力を助けるための手段としてそれが増加していったとも考えられる のだ。極端な一例を挙げるとするならば、ジョゼフ・コンラッドが自作 の小説『密偵』(1907年)を戯曲化したものの一節はどうだろうか。
ヴァーロック〔振り向いて〕俺が!・・・・・俺がだと!・・・・・
この悲劇的な作品を読みながら私はついつい苦笑してしまうことになるのだが、おそらくそれほど厳しい批判を浴びせられることはないだろう。
小説というジャンルがその形式、手法などの面においてほぼ完成した と考えられる19世紀においてすら、演劇と小説の相互浸透関係がこのよ うなものであったとするならば、18世紀の後半におけるゴシック小説と いうサブ・ジャンルとゴシック演劇の関係を論ずるというのは強引な力 業とならざるを得ないだろう。しかし、そうした状況下では、逆に、テ ーマや主題の共有化が起こり、あとあとまで継続するそれをテクストに 強く刻印してしまうことがあるのも歴史的な事実である。端的に言えば 、18世紀のイギリスのゴシック文学の場合にもそれが起きたというのが 私の考えである――ホラス・ウォルポールというひとりの作家の小説『 オトラントの城』(1764年)と戯曲『謎の母』の間で。
私はゴシック文学の特徴をいわゆる恐怖の演出やエドマンド・バーク 的な崇高性の描出に求めるつもりはない(実のところ、アン・ラドクリ フの『ユドルフォの謎』(1794年)という長編小説を読んで、その殆ど の部分を忘却するほどの弱い記憶力をもつ者でないかぎりは、この作品 における崇高性など論じ得ないはずである)。問題は、さまざまなかた ちの恐怖なるものを生み出すテクスト内のメカニズムと人間関係にこ そあると言っていいだろう。
『オトラントの城』他の典型的なゴシック小説を貫いているのは、社 会問題や個人の人間的な成長に固着する関心ではない。最も執拗なかた ちでそこにあるのは〈継承(inheritance)〉のテーマである。城、屋敷、土 地、財産の継承であり、家名や地位の継承である。それが何者かによっ て不当に奪われ、本来の正統的な継承者がそこから追放され――しばし ば〈孤児〉として〈放浪〉し――やがて本来のしかるべき位置に復帰す る。これは19世紀的なビルドゥングス・ロマンとは両立しがたい構造で あって、努力による個人の成長と達成を目標とするジャンルとは本来な じまないものであるはずなのだ。ゴシック小説における諸々の犯罪と恐 怖は、そのような〈奪取〉、〈孤児〉、〈放浪〉、〈復権〉などのモチ ーフをつないで展開するテクストの中に埋め込まれたある種の効果、結 果なのであって、それをこのジャンルの示差的な特徴とみなすのはあま りにも単純な考え方と言うしかない。しいて言えば、そのような単純な 反応を引き出すこと自体がこのジャンルの浅薄さを保証する示差特徴であるとは言えるかもしれないが。
しかし、18世紀から19世紀にかけての社会経済の変動の中で、城や地 位や家名の継承が安定した不動の魅力を維持できるはずはない。それと 併行し、それにとってかわるだけの魅力をもっていたのが〈血の継承〉 というかたちの継承問題である。つまり、結婚問題である。ゴシック文 学がそれを犯罪とつなぐために近親相姦の問題を持ちだしてくるのは 簡単に予測のつくことではあるし、げんにウォルポールが『謎の母』で やってみせたのはその乱用であった。夫の伯爵の死を目前にして、伯爵 夫人が息子と関係をもち、それによってできた娘とその息子が結婚に突 き進むという設定を振り回してみせたのだから。
19世紀のイギリスのゴシック小説はこの〈血の継承〉というテーマに 徹底してこだわり続けることになる。継承されるべき血統の中に他の人 種の血が介入してきたらどうなるか(『嵐ケ丘』)、狂気の血が混入し てきたらどうなるか(『ジェイン・エア』)、通常の人間とは違う、異 常な血が混入してきたらどうなるか(『フランケンシュタイン』、『ド ラキュラ』)。いや、コンラッドの『密偵』にしてもこの問題にこだわ っていたはずである――その意味では、お化け小説、ゴシック小説とは さまざまな差別的な偏見が展示される場ともなりうるのである。

第48回 シ ェ イ ク ス ピ ア 学 会 報 告
2009年10月3日(土)・4日(日)
会 場: 筑波大学
研究発表(要旨)
第1室
司会 奈良女子大学准教授 西出 良郎
服飾と身体の交錯—— Othello におけるハンカチ再考八鳥 吉明
初期近代英国においてダイナミックな変貌を遂げていった服飾と身体に纏わる言説と表象を踏まえ、本発表ではOthello の読解を通して服飾と身体の問題を考察した。Othello ではハンカチが悲劇の重要な要素を構成しているが、服飾論ならびに身体論の視座から見ると、この劇ではハンカチを身体、特に女性身体との関係性において提示し、問題化する視点が顕著であり、それが悲劇の展開と密接に関連している。
初期近代、ハンカチは清潔さと身体に関する新たな概念形成を促し、女性の身体は「囲われた庭」と「漏れやすい器」という、相反する表象によって両義的に意義付けがなされた。妻の不貞という去勢不安に捉えられたOthelloにとって、ハンカチはグロテスクな女性身体を隠蔽すると同時に可視化するテクストであり、ハンカチを失ったDesdemonaの身体は「漏れやすい器」と見なされ、Desdemonaは娼婦化されてしまう。
またハンカチは目や鼻、耳、唇といった身体部位と連想的に結び付けられていく。その際、ハンカチは多くの性的観念・イメージが圧縮・置換された表象となり、それを通してDesdemonaの女性身体は性的欲望の身体として規定される。“the Rainbow Portrait”と呼ばれるエリザベス一世の肖像画のマントに描かれた目、耳、唇は、エリザベスの王権を神秘化し、強化する寓意として機能するが、そこに描かれると同時に抑圧され、不可視なものとされる女性身体のグロテスク性がDesdemonaに投影されているとも解釈できる。
しかし、ハンカチはDesdemonaが主体性を構築する物質的基盤ともなる。またEmiliaは女性の身体や欲望と服飾とを安易に接合することを拒否する。その結果、服飾と身体は家父長制の中でまさにその服飾と身体を核にして構築される女性性の言説と表象に断層線を入れる契機ともなり得る。Othelloはそうした可能性や契機も胚胎しているのである。
「終わりよければすべてよし」なんて、いったい誰が言ってるんだ高田 茂樹
本発表は、『終わりよければすべてよし』を、シェイクスピアが自分の従来の作劇法や自己成型の仕方を疑問に付して再検討するために書いた実験的な作品と捉えようとする試みである。
作品の主要な登場人物たちは、バートラムに対する自身の一方的な思いに沿ってことを遂げようとするヘレナや、むやみに彼女に肩入れするバートラムの母親、ヘレナに対する個人的な恩義からバートラムに彼女との結婚を強要する国王、そして、自分に押しつけられる成長の物語に(積極的な意図を持ってというよりも、むしろただ未熟なゆえに)うまく嵌ろうとしないバートラムなど、それぞれ言動が奇妙にちぐはぐで、全体として後味の悪い芝居にしてしまっている。
彼らの語る言葉も、その内面を適切に表現しているというよりは、むしろ、多くが借り物の言葉、世間一般の決まり文句で構成されているように聞こえる。そしてまた、この芝居の中の重要な出来事の多くも、シェイクスピアのそれまでの芝居のシーンから借用してきた二番煎じのように感じられる。しかも、そういう借り物の言葉や二番煎じの場面は、それぞれうまくかみ合って、統一された全体像を提示することはなく、むしろ、それぞれの要素のそぐわなさや時代遅れぶりを際だたせ、その破綻ぶりを強調するアサンブラージュのような様相を呈するのである。
この時期、シェイクスピアは、他人の縁談を仲介しており、その際の事情が作品の執筆に影響したと考えられているが、さらに、20年余り前のシェイクスピア自身の結婚の経緯も、創作に影を落としていると考えられる。二つの結婚のあいだの類似性とそれぞれにおいて自身が果たした役割の違いについての思いが、シェイクスピアに、自分が多くの芝居の中で描いてきて、またその創作を通して自身に課してもきた自己成型のあり方に疑問を抱かせて、そのことが彼にこのアサンブラージュのような作品の創作に向かわせる一つの動機になったと考えられる。
司会 元青山学院大学教授 青山 誠子
『ロミオとジュリエット』における時間と作品構造由井 哲哉
『ロミオとジュリエット』では、9ヶ月に及ぶブルックの物語が5日間に圧縮された上、プロローグで早々に悲劇的結末が観客に知らされるなど、シェイクスピアの意図的な時間加工の工夫が随所に見られる。本発表では、キャピレットが娘とパリス伯爵との婚礼の日取りを決める3幕4場の重要性を検討しながら、結末の時間を規定してからそこに至るプロセスに光を当てようとするシェイクスピアの意図を探った。
3幕4場は、5日間に圧縮されたこの物語の中で、初めて曜日が示される重要な場だが、それによって冒頭からこの中盤の場に至るまでたった1日しか経過していないことも明らかにされる。芝居を観ている観客は意識しないものの、実はこの1日の中に、主人公二人の出会い、バルコニー・シーン、結婚式、マーキューシオとティボルトの死、ロミオの追放など、芝居の重要な事件のほとんどが凝縮されているのである。
一方、一気に悲劇へと突き進むはずの後半部にはむしろ3〜4日という時間の幅が割り当てられている。ジュリエットはこのとき父親が決めた婚礼の木曜日を空白の一日とするために神父の眠り薬を利用するわけだが、ジュリエットと神父と観客の三者にしか共有されていないこの情報が他の人物に行き渡らずにロミオだけに行き渡るかどうかが終盤の見所の一つとなってくる。そしてこの木曜日を境に、ロミオの時間がジュリエットの時間に追い着こうとするプロセスが始まり、物語は初めて登場人物も観客も情報を共有することのない未知の領域に入り、これが終盤の圧倒的な加速感を生み出していくことになる。
マーキューシオとティボルトの死が芝居の大きな転換となることは確かだが、真の意味での芝居の転換点は短い3幕4場にあり、そこで決められる木曜日の扱いこそがこの悲劇の重要な仕掛けの一部となっている。シェイクスピアは、悪人を一人も登場させず、ただ時間と情報の落差だけでこの物語を崇高な悲劇に仕立てあげたが、そこには入念に計算された彼なりの時間加工の意識が隠されているのである。
「不思議の国」のハムレット中野 春夫
『ハムレット』の劇世界にはユートピア物語やファンタジーと類似するフィクションならではの特殊な設定が施されているように思われる。法律、慣習、文化等について観客(読者)が自明とするものとは異なる制度をもつ異世界にシェイクスピア時代の社会常識をもつ登場人物が生活したならば、その登場人物はどんなトラブルに直面し、人間関係の上でどのような重荷と困難を背負わされることになるのだろうか?
シェイクスピア時代のイングランド社会においては婚姻障害事由(impediments)が教会法だけでなく、議会制定法(25 Hen.VIII. c.22, 32 Hen.VIII. c.3)でも明文化されており、義理の姉と弟は禁じられた関係をひそかに結ぶことは可能でも、婚姻関係を公に認められることはあり得なかった(宗教改革前の教皇による特免というウルトラCの法的手続きが非合法になっていた)。明々白々に議会制定法上の「婚姻禁止親等(Levitical Degrees)」に該当する義理の姉と弟が有効な婚姻関係を結べるという、シェイクスピア時代の観客にとってありえないことがすでに起きているのが『ハムレット』の劇世界である。
今日の視点から「『ハムレット』はどういうお芝居か?」という問いを立てると説明は困難になるが、「社会制度の設定からみると、『ハムレット』はどういうお芝居だったか?」という限定的な問いであればかなり明確な答えを出しうる。『ハムレット』の劇世界とは王位(不動産)相続、婚姻契約(spousal)、婚姻関係(matrimony)など根幹的な社会関係のルールにかんして、観客が同時代の現実世界ではありえない仮想世界を想像することから始まったお芝居である。
本発表はこの仮想世界の制度的設定を材源との関連から説明したうえで、さらに異世界への主人公の紛れ込みというファンタジーさながらの摩訶不思議な設定を指摘してみた。
第2室
司会 東京経済大学教授 本橋 哲也
シャイロックのナショナリズム―『ヴェニスの商人』試論
田中 一隆
本発表では、シャイロックのキリスト教徒に対する態度を「ナショナリズム」(nationalism)という概念を使って考察した。今日の「ナショナリズム」の概念は、「国家」(state)という概念と深く結びついている。しかし、シェイクスピアの時代は、「国家」と結びついた近代的な意味における「ネイション」(nation)―いわゆる「国民国家」(nation-state)の概念―が生まれる前、あるいは誕生にいたる過渡期であったので、近代的な意味での「ナショナリズム」が『ヴェニスの商人』にそのままあてはまるわけではない。しかし、シャイロックの台詞に見られる"nation"という言葉は、それが他の作品で使われた時とは異なる、あるはっきりとした態度、価値観を示唆していること、シャイロックのナショナリズムは、近代的な国民国家の概念を前提としない、きわめて原初的な態度、価値観であることを主張した。
シャイロックの"nation"は、出生の共通性によって結びつけられた人々の集団という語源的な意味に強く色づけされている。シャイロックは自らの属するユダヤ民族を"nation"という言葉で呼ぶことによって、ユダヤ民族の起源の意識に訴える。シャイロックが新約聖書に間接的に言及するのは、古代ローマに支配されたユダヤ民族の苦難の歴史に言及し、自らの生業としてのusuryを正当化しようとするためである。usuryがユダヤ民族の始祖ヤコブの「繁栄」("thrift")と結びつくのも、このような起源の意識の産物である。一方キリスト教的価値においては、出生や起源の同一性といったエスニックな要素は否定される。シャイロックの娘ジェシカは、バラバスの「子孫」("stock")へ嫁がせたかったという父親の願いにも拘わらずキリスト教徒と駆け落ちし、シャイロックの財産はヴェニスという「国家」("state")の財産(estate)となる。ユダヤを支配する古代ローマに反逆しようとする挑戦的な身振りで始まったシャイロックのキリスト教徒に対する復讐は、結局、擬人化された「収税官」("publican")としてのヴェニス国家に財産を奪われるのみならず、キリスト教徒に改宗させられて幕を閉じる。この作品は、nationとstateという、ヨーロッパの歴史の中でやがて大きな意味を持つようになる概念を孕みながらも、この二つの概念が「国民国家」(nation-state)という形で共存してゆくその契機をまったく提示していないように思われる。
‘Disposed to mirth’: The Humour of Antony and CleopatraDavid Taylor
This session considered the numerous comic elements of Antony and Cleopatra as central to the play’s status as a ‘problem tragedy’, and raised the following issues. Commentators have not missed the strong tension between tragic action – the failure to avert personal disaster by obeying public or political strictures – and the omnipresence of comic statement passing through characters with, for Shakespeare, an unusual fluidity, which is paralleled in the peculiar formlessness of the play itself. It is not just Antony who, according to Cleopatra, is ‘disposed to mirth’, but any number of the characters - from Cleopatra to Octavius - who are to be witnessed engaging in comic, humorous or ironic repartee to convey the seriousness of human predicament. This central paradox is not unique to this particular tragedy (Shakespeare’s gallows humour is a familiar feature of both his tragedies and comedies), but the comic effects of the play’s celebrated and lesser-known passages received more detailed attention on this occasion.
To what extent does the humour in Antony and Cleopatra add to the established critical debate that Shake- speare is straining the limits of tragic form and demanding an unusual degree of judgment from audiences in his mature artistry? Antony and Cleopatra’s composition follows King Lear and Macbeth in a sequence generally regarded as Shakespeare at the height of his powers for creating tragic drama, and the modern critical tradition (chiefly Honigmann (1976), Jones (1977), Bevington (1990)) was reviewed for two major strands: being firstly, the standard recognition of both Shakespeare’s soaring lyrical rhetoric as appropriate to its subject matter of all consuming love, obliv- iousness in risk, extreme sacrifice, loss and idealistic gain, but secondly, the exploration of the play’s formal complexities, as in Bayley (1981), who argues that tragic fate is reconceived in Antony and Cleopatra, where it ‘has something almost good-natured about it, relaxed and familiar’. This critical area was extended in the paper’s conclusion, which argued that Shakespeare, in the wake of major achievements in tragedy, is experimenting intriguingly with comic effects, and that Antony and Cleopatra’s depiction of tragic indiscretion is inseparable from eccentricities of tone.
Questions for the speaker included debate of Diana Preston’s Cleopatra and Antony: Power, Love and Politics in the Ancient World (2009), considering in particular the clear thematic differences which divide Rome and Egypt in Shakespeare’s artistry, but which, according to Preston, have less basis in ancient history.
司会 元杏林大学教授 川地 美子
The Sword of Freedom and the Freedom and People's Rights Movement
Robert Tierney
In my paper, I examined Tsubouchi Shōyō’s first translation of Shakespeare's Julius Caesar. When he started to work on this work in 1882, Tsubouchi was a student at Tokyo Imperial University majoring in political science and he completed it shortly after graduating from the university in 1884. The play has the kabuki-like title: Shiizaru kidan: Jiyū no tachi nagori no kireaji (The Strange Tale of Caesar: the Sword of Freedom and the Echo of its Sharp Blade). In 1913, when Tsubouchi translated Julius Caesar a second time, he disavowed this early work and pointed out its shortcomings: “Shiizaru kidan was my first translation of a play by Shakespeare, but I translated it while I was still a student at Tokyo University. The style of this translation is not as I wished, there are many mistranslations and it has no relation to the present translation.” Following his lead, scholars have tended to dismiss “The Sword of Freedom” as a preparatory step to his mature translations of Shakespeare.
In my analysis, I argued that this translation represents a high point in his early career but that it also points toward a turning point in his views on literature. Tsubouchi inserted the language of Meiji political thought and the rhetoric of the Freedom and People’s Rights movement directly into his translation. Following the form of a jōruri play, he also added a narrator to the play and had the narrator offer critical commentary on the significance of the play as a whole, drawing out didactic lessons for the spectator. By examining the different comments that the narrator makes about the meaning of the play, I showed that Tsubouchi experienced a change of heart toward the Freedom and People’s Rights as he was translating the play. In addition to studying Tsubouchi’s involvement with politics, I also examined the place of this work within his overall translations of Shakespeare and its significance as an early case of the reception of Shakespeare in Japan.
『オセロウ』受容史再考のために —— 宇田川文海『阪東武者』(1892)近藤 弘幸
明治期の日本における『オセロウ』受容史は、川上音二郎による翻案上演から、坪内逍遥による翻訳上演へという流れで語られる事が多いが、それに先立つ新聞連載翻案小説という「前史」が存在する。とりわけ、1892年9月19日から10月19日まで31回にわたって「大阪毎日新聞」に連載された宇田川文海の『阪東武者』は、全くと言っていいほど知られていない。本研究発表の目的は、この忘れられた翻案小説を演劇改良運動という当時の文脈の中に位置づけることである。『オセロウ』を日本化しようとしていた文海は、春画における悪相の伝統に倣い、その主人公の「黒さ」を「醜さ」と置き換え、さらに「醜さ」を補強するものとして、三世河竹新七の『籠釣瓶花街酔醒』(1888)から、先行する翻案小説『痘痕伝七郎』を経由して、「あばた面」という要素を付け加えて、『阪東武者』を執筆した。こうした「日本化」のプロセスを経たため、『阪東武者』は、『オセロウ』という作品が持っていた人種の政治学を、ことごとく喪失してしまったのである。
しかしながら、ここで想起すべきは、明治日本におけるヨーロッパ演劇受容が、演劇改良運動という、日本演劇=旧劇の西洋化=近代化を目指す運動の一翼を担っていたという事実である。『オセロウ』を「日本化」するための受け皿の一つが『籠釣瓶花街酔醒』であったということは、逆の見方をするならば、『籠釣瓶花街酔醒』という旧劇を『オセロウ』という西洋戯曲の力を借りて近代化した「改良狂言」が『阪東武者』であったと考えることもできる。そしてこうした考え方に立った時、この作品は、坪内逍遥や、演劇改良運動のイデオローグ外山正一を含む、当時の知識人層が、江戸時代的・旧劇的「色」の世界に取って代わるものとして称揚した、近代的・新劇的「恋愛」イデオロギーというプログラムをインストールするという、性の政治学に深くかかわるものであったことが明らかになるのである。
第3室
司会 同志社大学教授 勝山 貴之
Birnam Wood への新たなアプローチ —— Macbeth における男性性の幻想
塚田 雄一
本発表では、Macbethで下される「帝王切開で生まれたマクダフ」と「移動するバーナムの森」をめぐる二つの預言に焦点を当て、特に自然による祝祭的な秩序の回復を示唆するものとして主に読解されてきた後者の預言に対し、新たな解釈を呈示した。
預言読解の手掛かりとして、男性性の表象から女性性の痕跡を消し去り、完全な男性性の演出を志向する、ルネッサンス期の「男性性の幻想」(“female-free fantasy”と呼ぶ)に着目した。たとえば、前者の預言に登場する帝王切開は、当時、既に死んだ母胎から胎児を救い出す男の医者による男性的な手術として知られ、帝王切開によって生まれた男児は、その命を男の手によって「創り出される」ことにより、無傷の男性性を保持すると認識されていた。
マクベスの支配するScotlandが、その体内で人々の息絶えていく「死んだ母親」に喩えられていることに注意したい。後者の預言に登場するバーナムの森は、「病んだ国家の医者」と呼ばれるマルコムと男の兵士たちの手によって、その「死んだ母親」から「引き抜かれる/切り離される」(“unfix”)。母なる大地からその根を切り離されるバーナムの森は、人為的に母胎から切り離される赤ん坊の姿を彷彿させる。荒れ果てた大地からバーナムの木々を引き抜くマルコムの行為は、死んだ母胎としてのScotlandから国民を切り離し、新しい国家を創り出すという意味で、いわば朽ちた女性性から男の手によって生命を創出する帝王切開に擬えることができる。また、ここにおいて、マルコムにはElizabeth Iの母胎からEngland=Scotland同君連合という新しい国家を創出したJames Iの姿が重ね合わせられており、二つの預言が一体となって演出する“female-free fantasy”はJames Iの男性的な君主としての幻想と響き合っていたと論じることができる。
『スペインの悲劇』における女性表象と〈終わり〉の感覚岩田 美喜
『スペインの悲劇』における「復讐」という主題はこれまで、ヒエロニモーを中心に論じられてきた。だが、アンドレアからホレイショーへと対象を変えてゆく「復讐」の両方に関わっているのは、ヒエロニモーではなくベル=インペリアである。作品が進行するにつれ、アンドレアからホレイショー、ホレイショー からヒエロニモーの手へと渡っていく彼女のハンカチが示唆するように、ベル=インペリアは二つの復讐の物語をつなぐ媒介的存在だ。だが、それゆえにこそ、作品における彼女のポジションは常に曖昧でもある。「二人目の恋人は私の復讐を進めてくれる人になるのよ」(1.4.66)という台詞は、それをよく表しているといえよう。また、「支配の美」を意味する名を持ちながら、兄の策略のために抑圧・監禁されるという点にも、彼女の存在の両義性、中間性が見て取れる。
『スペインの悲劇』において媒介的な役割を果たす女性は、ベル=インペリアだけではない。アンドレアの語りに登場する女神プロサーパインもまた、アンドレアの死後の運命を決める裁決権をプルートーより委譲され、さらにその実行権を復讐神へと委譲する、媒介的存在である。実際に舞台には登場しないものの、彼女の存在が、この戯曲の枠となる物語を作っていることは重要だ。『スペインの悲劇』より遡るはずのアンドレアの物語とホレイショーの物語とをつなぐベル=インペリア同様、この作品では、女性が作中の時間の二重性と結びついて表象されているのである。
こうした時間の二重性は、復讐神による最終行、「ここでは死が彼らの苦しみを終わらせたが/この私があそこで終わりなき悲劇を開始するのだ」(4.5.47-48)においては、観客の〈終わり〉の感覚を揺るがすものになっている。『スペインの悲劇』の特徴のひとつは、結末感の解体と女性表象が結びついている点だといえるのではないだろうか。
司会 京都教育大学教授 太田 耕人
戦後ジャンル映画におけるシェイクスピア受容のインターテクスチュアリティ
—— 『荒野の決闘』から『悪い奴ほどよく眠る』まで
大島 久雄
大戦後1950年代は、Kiss Me Kate (1953)、Joe Macbeth (1955)、Forbidden Planet (1956)、『蜘蛛巣城』(1957)が登場し、ジャンル映画におけるシェイクスピア受容が活性化する。しかし戦後ハリウッドにおいてシェイクスピア利用にまず注目したのは、アメリカの国民的娯楽ジャンル映画、西部劇・ギャング映画である。本論は、特に受容の地域性・時代性に注目しながら、戦後ジャンル映画におけるシェイクスピア受容のインターテクスチュアリティを探った。西部開拓史とモニュメント・バレーというアメリカ独自の時代性・地域性を活かした西部劇古典映画、John Ford監督 My Darling Clementine (邦題『荒野の決闘』, 1946)では、Hamlet 等のシェイクスピア作品言及が、人物描写や、フロンティア対文明等の主題展開に重要な役割を果たしている。Philip Yordan (Joe Macbeth脚本も担当) によるKing Lear 翻案ギャング映画 House of Strangers (『他人の家』, 1949) は、リメイクされて西部劇 Broken Lance (『折れた槍』, 1952)、さらには舞台をサーカスに置き換え The Big Show (1961)となり、これはシェイクスピア異種映画ジャンル・リサイクルの典型事例である。悲劇的ミザンセンヌ、宿命の女、フラッシュバックなど、40年代ギャング映画に端を発するフィルム・ノワール的映画構成によりシェイクスピア翻案が行われている。Delmer Daves監督によるOthello翻案Jubal (『去り行く男』, 1956)は、西部劇として初めて性を取り上げ、シェイクスピア的人間描写と雄大な西部自然風景を融合させた意欲作であるが、勧善懲悪の傾向が強い西部劇のジャンル的特徴に従い登場人物に関しては分散的翻案がなされている。各邦題が示すようにこれらの映画は日本でも同時期に上映されていた。このようなジャンル映画の背後に隠れたシェイクスピア受容動向の派生作品として黒澤明監督『悪い奴ほどよく眠る』(1960)を分析したが、ノワール的映画構成の中でHamlet的要素を活かし、戦後日本の時代性・地域性にこだわった映画造りには、黒澤が深く敬愛していたFordの遺伝子が確実に受け継がれている。
シェイクスピア時代における ‘within’ の意味と用法
市川 真理子
シェイクスピア劇をはじめとするイギリス近代初期劇のテクストにおいて ‘within’ は最も基本的な演劇用語のひとつである。数年にわたり、このト書きの意味と用法に関する研究を行ってきた。その報告として、主に次の5点について、それぞれ例を挙げて説明した。
- ‘Within’(「楽屋内部で」)というト書きは、きわめて漠然としたものであるが、実際に ‘within’ として頻繁に使われる場所は数箇所に限られていた。すなわち、舞台のドア (stage doors) とその中間にあるカーテンで被われた中央開口部の背後である。
- したがって、ドアないしはカーテンが開いていれば、‘within’ とされる人物の姿は、舞台上の人物や観客から見える可能性がある。
- 俳優がドアから姿を見せる行為が、‘enter’ というト書きで指示されていることもあれば、‘within’ とされていることもある。当時の劇作家や俳優の意識において、「舞台上」‘onstage’ と「舞台裏」‘offstage’ との境界線は非常に曖昧だった。
- また、‘within’ が楽屋の上階ないしは舞台の上方のバルコニーに言及している例が少なからず存在する。つまり、時として、‘within’ は ‘above’ と同じ意味で使われた。
- 極めて稀ながら、‘within’ が ‘to direct a speech towards within’ の意味で使われているのではないかと思われる例がある。それらがフレッチャーの作品に集中しているのは興味深いことである。
第4室
司会 愛知教育大学教授 南 隆太
悪役になりたい —— サンドフォード・シバー・リチャード三世 ——
小西 章典
本発表では、〈悪役の系譜〉という観点からColley CibberのRichard III (1699)を読解した。とりわけ、Richard III役を演じるにあたりCibberがその演技を継承しようとした悪役俳優Samuel Sandfordの〈曲がった背骨〉に注目した。まず、悪役SandfordというステレオタイプがCibberの視界に浮上してきた背景について実証的に調査し、1690年代に上演(再演)されたJohn Drydenの芝居が、その大きな要因のひとつになっている可能性を指摘した。さらに、Cibberの演じる悪役Richard IIIがSandfordの〈曲がった背骨〉をどのようなかたちで占有しているか、Richard III というテクストをシアトリカルなレベルから見ることで考察した。具体的には、この芝居のなかに存在する2つの〈ディスカヴァリー・シーン〉をとりあげ、これらの場面がRichard IIIの〈曲がった背骨〉に焦点をあてる方法について、ShakespeareのRichard III にも目配りしながらあきらかにした。これらの〈ディスカヴァリー・シーン〉には、悪役俳優Cibberの〈曲がった背骨〉に視線がそそがれるように観客の経験を統制しようとするシアトリカルな意図がうかがわれるのであり、その意味で、Richard III とは、Shakespeareの翻案という装いを備えつつも、実質的には悪役俳優になりたかったCibber自身が案出した芝居にほかならない、と結論づけた。
なぜイモインダは白人に変えられたのか?
福士 航
1695年11月にトマス・サザンの翻案劇『オルノーコ』が初演されたとき、アフラ・ベインのオリジナル散文作品にある決定的な改変が加えられた。アフリカ人ヒロインのイモインダが、白人に変更されたことである。なぜこの改変がなされたのかについては、女優が黒塗りでは舞台に立てなかったという慣習上の理由や、肌の白さと女性の美徳とを関連づける美学的言説の存在を理由とするなど、盛んに議論されてきた。本発表では、サザンの『オルノーコ』における上演面での諸要素を考慮し、受容論的な立場から、劇場の内部にこそイモインダ白人化の理由があったことを論じた。
具体的には、チャールズ・ギルドンの『ベタトン伝』を手がかりに、王政復古劇場においては、感情を可視化させることが俳優の演技に要求されたことを確認し、さらに『オルノーコ』がいかに感情の可視化を狙った劇であるかを、主にオルノーコとイモインダの死別の最終場から確認した。感情を可視化するのは、観客の中にも同情などの感情を喚起させ、それを発散させるためであり、『オルノーコ』を見る観客は、特に女性を中心にして、オルノーコとイモインダの死別に感情移入し〈感動〉して涙を流していたことを、幾つかの資料から確認した。観客を満足させることを劇作家および劇団は考慮せざるを得なかった状況において、劇場全体で〈感動〉を共有することがこの芝居の上演戦略だったと考えられる。観客の興味を引きつけ、興行的な成功を収めるために〈感動〉の共有が求められた劇場という共同体の中では、黒人同士の悲恋が感情移入の対象として必要とされることはなく、劇場に関係する全ての人間が黒人のヒロインを望まなかったためにイモインダは白人に変えられたのである。換言すれば、劇場内部にこそ、黒人を他者化するような植民地主義的イデオロギー生成の契機は含まれていたとも言えよう。
オペラなのか英雄劇なのか
—— ウィリアム・ダヴェナントの
『ロードス島の攻囲』に見られる不確定性 ——
末廣 幹
近年、17世紀内乱期の演劇文化の再評価が進むようになり、その結果、護国卿政府時代に上演されたとされるサー・ウィリアム・ダヴェナントのオペラ『ロードス島の攻囲』二部作がふたたび注目されるようになっている。たとえば、Susan WisemanやMatthew Birchwoodの論考の方法論には共通した陥穽が見られる。それは、もっぱらトルコ人の表象に焦点を当てることで、このテクストの構造的な特徴、すなわちプロットやナラティヴの特異性をじゅうぶんに分析していないことである。その結果、このテクストのジャンルの不確定性が等閑視されている。本発表では、このテクストのプロットやナラティヴの特異性に注目することを通じて、『ロードス島の攻囲』の演劇史的位置づけの修正を試みた。
とくに『ロードス島の攻囲』「第1部」の「第1四折版」のテクストを詳細に検討してみると、劇作家John Drydenが『ロードス島の攻囲』に対して行った批判のうち、少なくともプロットが不完全であるという点だけは妥当であることがわかる。エンディングは、問題の解決を曖昧にしたまま、すべてを先送りにしており、完全に尻切れトンボだからである。実際に、中心人物のAlphonsoは、悲劇的な死を遂げることもなく、喜劇的もしくは悲喜劇的にIantheと和解することもないからである。本作は王政復古期の英雄劇の先駆的作品と位置づけられているが、中心人物の設定は、その後の英雄劇とは決定的に異なるのである。最後に、本作において繰り返し脅威として言及される“jealousy”とは、17世紀における“zeal”や“enthusiasm”、つまりピューリタンらに見られる「宗教的・政治的熱情」を表す記号であったという問題提起を行った。
第5室
司会 岩手大学教授 境野 直樹
「バター売り女」、来る
—— ベン・ジョンソン作『新聞商会』における「バター」比喩の展開
瀧澤 英子
本発表では、The Staple of News (1626年初演)における“butter”比喩の再検討として、第一幕四場に登場する“Butterwoman”(「バター売り女」、以下、“BW”)を取りあげた。新規開店の準備で慌しい商会に見知らぬ女性が現れNewsを要求する。店員は即座に“BW”と察し、入荷まで待つよう言いわたす。従来の各版は“To scold like butterwives”(Tilley B781)を引き、この人物を呼び売りの声から連想されたであろう冗舌の典型像と読むか、もしくは新聞出版業者Nathaniel Butter氏の姓名のもじりとする見解に終始している。しかし、当時、“BW”がいかなる人物像を想起させる生業であったかを考察した上で、商会店員とのやりとりや欄外のト書きを読み直していくと、この名もない女性に著しく活動的な性格が与えられていることがわかる。
Shakespeare作品で言及される“BW”像(AWW IV.i.42-43; AYLI III.ii.86-87)を巡りこれまでに重ねられた解釈を見直すTaylorの報告に加えて、行商人ゆえの寄る辺ない立場を指摘する同時代文献(Harrison 250, Brinklow 19-20)をふまえ、本論では、変質しやすい生鮮食品を売りさばく“BW”みずからが、可変性を帯びると分析した。
butterを売る女性が、隣で片面刷りのバラッドを売る男の歌声に惑わされる光景を描くEarleの記述が示すように(81)、売買のやり取りが活発に行なわれる商業空間は、“BW”に売り手から買い手への転身を促す。新聞商会を訪れる“BW”もbutterの売り手を示す名で呼ばれながら、Newsの買い手として出現する。さらに“BW”はNewsを「土曜に教区牧師のところへ持ち帰る」(11-12)と予告しており、やがて地元へ戻り仕入れた話題をほかへ受け渡すことで、Newsの供給者へと変わる意思を示す。彼女の買ったNewsは、翌日の説教でさらに広く伝播されていくことが予想できるのだが、“BW”はその席に参列し、自身の提供したNewsを牧師の口から聞くことで、ふたたび買い手の立場へと転回するのである。
このように、“BW”が情報を媒介しながら動態を発揮する動態を見届けた。そしてJonsonが、同時代の言説をにぎわせた“butter”比喩を借りつつ、情報の流通過程とその只中で往来する人物を効果的に活写する表象へと発展させた独自性を明らかにした。
REFERENCES
Brinklow, Henry. The Compleynt of Roderick Mors. 1545. Ed. J. Meadows Cowper. EETS 22. 1874. NY: Kraus Reprint, 1973.
Earle, John. Micro-cosmographie. 1628. Ed. Edward Arber. Westminster: Constable, 1904.
Harrison, William. The Description of England. 1587. NY: Dover Publications, 1994.
Herford, C. H. and Percy Simpson and Evelyn Simpson, eds. Ben Jonson. vol.x. Oxford: Clarendon Press, 1925.
Taylor, Gary. “Touchstone’s Butterwomen.” RES 32 (1981):187-93.
『第二の乙女の悲劇』のダブル・プロット構造の再検討
小林 潤司
ミドルトンの『第二の乙女の悲劇』(別名『淑女の悲劇』)には、主筋と脇筋の両方で、プロットの節目ごとに現れる印象的な修辞がある。「鍵と錠」のメタファーである。鍵と錠は閉鎖された空間に何かを密閉(監禁、隠蔽)するための道具であると同時に、閉鎖された空間を外部に開き、そこに密閉されたものを解放(暴露)するための道具でもあるという二面性を持っており、劇の筋立てを考えると、<秘密とその暴露>、<肉体の桎梏からの魂の解放としての死>を表わす隠喩として、「鍵と錠」が繰り返し現れることには一定の必然性がある。また一方で、この悲劇の筋立ては、「監禁/隠蔽」にしても「解放/暴露」にしても、それが当初の思惑通り運ばずに想定外の結果を招くという失策の連続から成り立っていると言っても過言ではない。
「鍵と錠」のメタファーは、この悲劇のなかで、ただせりふのレトリックとして頻繁に用いられているというだけではない。プロットの展開とともに、「ことばの彩」を超えて、生きた劇的モチーフとして機能しはじめる。すなわち、ドラマのアクションがはらむ「隠蔽/監禁」と「暴露/解放」をめぐるパラドックスに観客の注意を引きつけ、物語世界を理解するひとつの視点を提供するのである。「鍵と錠」という共通の修辞を手がかりにして読み直すことで、ふたつのプロットが、これまで解釈者たちが着目してきたのとは別のレベルで、一定の計算に基づいて、統合が目指されている可能性に気づくことができる。それは、劇世界のなかで何が起こっているかではなくて、劇世界で起こることをどのような態度で見るかというレベルにおいての統合である。要約して言えば、アクションの悲劇性をパラドックスとアイロニーによって解体する志向が、この作品を貫く原理として働いているということである。
司会 東京都立大学名誉教授 上野 美子
イタリアとの邂逅 —— Gascoigne’s Supposes
冨田 爽子
イタリアの文化がエリザベス朝演劇に与えた影響を目に見える形で具体的に示すのは極めて難しいが、一つの切り口として英国の出版活動に注目する。イタリア関係の書籍は突然大量に出版されるようになるが、戯曲本の翻訳は極めて少ない。その中にあってGeorge Gascoigne が Ludovico Ariosto の I suppositi を翻訳したことは、英国喜劇の確立にとって幸運であった。Gascoigne の英国人としての感性は、後にエリザベス朝演劇の核心となる特質へと成長する原作の本質―variety と vitality と verisimilitude―に反応した。Ariosto は古典の遺産を尊重しつつ、新しい独自の喜劇を創作する。即ち日常語であるイタリア語の散文を用い、場面を近過去の自国に設定し、遠近法の背景幕を用いて、リアルに描き、時代を映し出した。
Gascoigne は原作の散文と韻文の両方を入手した上で、散文を選んだ。喜劇には現実的なスタイルが似合うと直感的に感じ取っていたからに違いない。散文喜劇が全盛となるのは20年近く先で、この時期に喜劇のスタイルを確立しようとした功績は画期的である。またGascoigne は ‘supposes’ という言葉の奥にある概念が演劇で果たす大きな可能性に気づき、原作にある言葉の遊びを更に拡大した。後にShakespeare はこの演劇的可能性を活用し、The Taming of the Shrew を書くことになる。
更にGascoigneは第2版で舞台を ‘as it were in Ferrara.’ と修正し、Ferraraの世界をアウトサイダーとして体験していることに注意を喚起する。JonsonのThe Alchemist での ‘Our scene is London’ を先取りしている感を与える。パイオニアのみならず、真のdramatistとしてGascoigneは高く評価されるべきである。
『ハムレット』とドイツ精神 —— ゲーテからヒトラーまで ——
山田 由美子
本発表の目的は、ゲーテに発するドイツの『ハムレット』ブームを通して、ロマン主義からナチズムに至るドイツ精神の変容を再考することにある。従来、ドイツにおけるシェイクスピア作品の受容は、恣意的なドイツ化による極端なものとみなされてきたが、20世紀終盤以降の研究の進展により、シェイクスピアがむしろドイツ的精神を内包していたことが解明されつつある。
今回は、トーマス・マンがドイツ精神をナチズムへと変容させた主要人物として挙げている4人の文化人――ゲーテ、ショーペンハウアー、ワーグナー、ニーチェ――に着目し、最初に各人の『ハムレット』解釈がどのように影響を及ぼし合ったのかを概観した。ゲーテ文学における独自の『ハムレット』解釈はショーペンハウアーの悲観論哲学の形成を促進し、哲学者ショーペンハウアーはワーグナー音楽によって崇拝の対象となり、音楽家ワーグナーはニーチェによって神格化され、ワーグナーから離反したニーチェは自らを神話化し、ワーグナーと共にナチズムの伝播のために濫用される。次に、ナチズムを形成する「人種神話説」・「帝国の理念」と4人のルター主義との親和性を考察しながら、『ハムレット』とルター主義に関する近年の研究成果を網羅し、作品の随所にルターの伝記や教条が反映されていることを確認した上で、『ハムレット』自体のドイツ性が、ドイツ的な『ハムレット』の受容を誘発した可能性が強いと結論づけた。
今後の課題としては、シェイクスピアが『ハムレット』にルター主義を反映させた動機や原因、『ソネット』その他の作品におけるルター主義との比較検討、シェイクスピア自身の宗教的信条との関係などの解明などが挙げられるが、ドイツ精神の形成とナチズムへの変容に対する『ハムレット』の影響力だけは、厳然たる歴史的事実として残っている。
セミ ナ ー (要旨)
《セミナー 1 》 ロマンティック・リバイバル —— 騎士道ロマンスとエリザベス朝文学
 |
|
エリザベス朝における騎士道ロマンスの流行は、時代錯誤の中世趣味 でもなければ、宮廷主導による絶対王政のプロパガンダでもない。むし ろ、近年大きな批評的関心を集めているのは、中世より伝承された騎士 道文学が、宗教改革と人文主義の高まりという逆風をくぐり抜け、文学 的・社会的に大きく拡散していく傾向である。文学史には残っていない 大衆娯楽作品(その中には、散逸のため物理的にも存在していない作品 が多い)に着目すると、エリザベス朝末期は、ヨーロッパでも類を見な い騎士道ロマンスの特需景気を迎えていたことがわかる。とりわけ、印 刷出版と商業劇場という二つの新興メディアの恩恵に浴した16世紀後 半のロンドンで、新しい形態の騎士道ロマンスを創作し、それを受容す る民衆文化の土壌が豊かに広がっていたことは注目に値する。この分野 は、史料の少なさというハンディの影響もあり、未だ研究の立ち遅れが 目立ち、特に大衆劇場における騎士道ロマンス劇ブームの実態はほとん ど解明されていない。本セミナーは、急速に肥大するロンドンの都市文 化を視野に収めつつ、16世紀後半から17世紀初頭にかけて隆盛を極めた大衆騎士道文学の文化的意義を検証することを目的とした。
セミナーの冒頭部で司会者が近年の研究動向を概観した後、各セミナ ー・メンバーによる報告が行われた。まず井出氏が、1570年代から1590 年代を中心に、なぜ騎士道ロマンス的な英雄がロンドンの大衆劇場でこ れほど人気を博したのかという問題について、劇場文化、及び政治的背 景の両面から考察した。井出氏が特に注目したのは、レスター伯やフィ リップ・シドニーなどプロテスタント武闘派貴族が積極的に活用した騎 士道文化的な自己成型が民衆レベルにまで深く浸透していたという現 象である。騎士道精神は、行き場のない渇望感を鬱積させる若年層に対 して国家主義的な集団意識の形成を促し、個々の市民をカトリック勢力 に立ち向かう「神の騎士」として祭り上げる文化装置として機能する。 「アーサー王の騎士たち」と呼ばれた弓術協会や、シドニーの葬列につ き従う武装市民は、1580年代以降、騎士道文学という特権階級の文化的 資本をロンドン市民が積極的に領有していく過程を示す好例と言える。 「スキタイ人の羊飼い」という特異な出自を持つ主人公の英雄的行為を 描いたChristopher MarloweのTamburlaine the Great は、こうした市民層 の価値観を巧みに掬い取ったものであり、その階級横断的なロマンス世 界は1590年代以降一挙に顕在化することになる市民型騎士道ロマンス の先駆けである。
騎士道ロマンスという既存の文学様式が解体され、劇場で新たな価値 観を付与されて再生産される様子は、続く前原氏の発表によっても論じ られる。前原氏は、テクストが現存する3つの騎士道ロマンス劇、Tom a Lincoln、The Seven Champions of Christendom、Guy of Warwick を取 り上げ、原作である散文物語を芝居に書き換える際に挿入された道化の 役割に焦点を当て、その演劇的趣向が従来の騎士道ロマンスにいかなる 改変をもたらしているかを分析した。前原氏によると、食欲や性欲など 身体的欲望への言及に満ちた道化の言説は、騎士のカリカチュアとして 機能し、宗教的大義名分を掲げる騎士道的英雄行為を即座に異化する効 果を発揮する。こうした諷刺は、食糧品の物価上昇や、肉食をめぐる政 府当局による法令にも向けられており、当時の市民生活と密接に連動し ていたことを窺わせる。異教徒討伐というロマンス的主題が、海外貿易 と植民地事業を牽引した商人階級のプロテスタント的商業資本主義を 反映するように、騎士道ロマンス劇は、願望充足というロマンス特有の メカニズムを通して、市民社会の飽くなき欲望を照射しているのである。
しかしながら、井出氏や前原氏が一方で指摘したように、騎士道文化 は不満や欲望を社会的・生産的なエネルギーへと変換したわけではなく 、むしろそれを野放図に無軌道化させる危険性を孕んでいた。森井氏は 、市民の騎士道ロマンス趣味を揶揄した作品として知られるFrancis Bea umontのThe Knight of the Burning Pestle を取り上げ、そのパロディ性を 劇の枠構造という観点から分析した。徒弟Rafeを中心に進行するロマン スは、あくまでも市民夫妻の脅迫めいた要求に沿う形で挿入された劇中 劇として機能しており、騎士道ロマンスの虚構性を自意識的に前景化す る。と同時に、荒唐無稽なロマンスの筋書きを要求することで劇の進行 を阻害する市民夫妻は、大衆劇場を席巻した市民層のロマンス趣味が劇 団側にとっては脅威となっていた可能性をも示唆している。市民のロマ ンス的幻想を具現するRafeは、最終的には排除されねばならない異分子 として、喜劇的大団円の中で唯一人「死」を迎えるのである。
高次文化と低次文化の接点としての騎士道文化は、司会者による発表 の問題提起となっている。1590年代における騎士道ロマンスの出版事情 が顕著に示す貴族的エリート主義と大衆性の二極化傾向は、もとより騎 士道ロマンスというジャンルそのものに内在する特質と言えるが、それ は同時に宮廷と市民社会が物理的・精神的に緊密な形で共存していたロ ンドン特有の都市文化の在り様を示唆している。ロンドンの街路を練り 歩いた「アーサー王の騎士たち」やThomas Deloneyの散文物語に登場す る市民騎士団は、騎士道文化が体現する貴族的な美意識やエートスへの 回帰を示す一方、市民としての歴史的出自や既得権を新たに誇示すると いう二つの方向性を示している。騎士道精神は、貴族と市民が共有する 文化コードとして機能するものの、こうした祝祭的連帯感はあくまでも 出版物を介して構築される「想像の共同体」の産物でしかない。Delone yが英雄化する現実主義的・経済主義的な市民像は、騎士道文学が標榜 する汎ヨーロッパ主義的ミリタリズムを真っ向から否定するアンチテ ーゼとして捉えることができる。
騎士道文学の衰退をもたらしたのは、宗教改革でもなければ人文主義 でもなく、他ならぬ民衆への社会的拡散であったとする定説がある。騎 士道文学が王侯貴族や知識層から市民を主体とする民衆にいわば「下賜 」された時、ロマンスの空洞化が始まったとする見方である。このよう な進化論的な文学史観に立てば、エリザベス朝の大衆文化における騎士 道ロマンスは、中世以降ゆっくりと瓦解してきた騎士道文学の残滓とも 言うべき姿を晒していることになる。しかし、メンバーによる発表、メンバー相互やフロアとの活発な意見交換を通して明らかになったのは、 大衆騎士道文学の創造性と多様性である。その背景には、台頭した市民 層が自らの共同体の理念や秩序を構築する際に共通の歴史観や集団的 記憶の形成を必要とした様子が窺える。ただし、民衆が騎士道文化に投 影する理念もまた決して一枚岩的なものではない。英雄の出現を待ち望 む期待感、暴力的・反社会的エネルギー、祝祭的なユーフォリア、土俗 的で野卑な大衆性―宮廷を発信源とする人文主義的な騎士道文化が周 到に抹殺したロマンス主義は、劇場や出版市場で再生産されながら、多 極化の傾向を辿ることとなる。ロマンスの大衆化は現代文化の様々な分 野に見られる現象であるが、その黎明を近代初期に見出すとすれば、エ リザベス朝の大衆騎士道ロマンスはロマンスの死ではなく、むしろ復活 への道標と言えるのではないだろうか。
《セミナー 2 》 NEW SYNERGIES IN CONTEMPORARY SHAKESPEARE PERFORMANCE IN BRITAIN
 |
|
The basic purpose of this seminar was to explore the connections bet ween academic Shakespeare studies and Shakespeare performance, or more generally between ‘page and stage’, in the context of Shakespeare production in contemporary Britain. The topic was open to a range of approaches, not the least of which must be the relationship between text and performance in a decentred, multicultural society such as contemporary Britain, and the consequent decline in ‘received’ notions of Shakespeare performance. This decline has become especially apparent over the last twelve years of ‘New Labour’ government, as a dated, organic view of Shakespeare has come undone, the Royal Shakespeare Company has come to focus on the individual theatrical event rather than the preservation of specific traditions, and new institutions such as Shakespeare’s Globe (1997) and the British Shakespeare Association (2002) have emerged not, as it were, to assert the hegemony of British Shakespeare but to keep Shakespeare’s plays alive in a society that must seem quite remote from the Elizabethan age. In other words, academics and performers, whether directly or indirectly, may collaborate to redefine the relationship between the present and the language and socio-historical environment of Shakespeare’s plays, avoiding on the one hand nostalgia for the past and, on the other, an obsession with contemporary relevance.
One example that I mentioned in my introduction to the seminar was that of Michael Gambon’s performance as Falstaff in the production of King Henry IV Part I, at the National Theatre in 2005. Coming shortly after the July 7th bombings in central London and with the heightened racial sensitivity, Gambon released a welcome draft of Bakhtinian energy into the auditorium; I, for one, will never forget his first appearance, when he urinated at some length into a stage bush before consuming a Full English Breakfast. Productions such as these represent a welcome break from the politicized environment of the 1980s when one leading Conservative politician declared that ‘Shakespeare was a Tory, without any doubt’, while some on the left assumed that Shakespeare could only be of any use if he could be co-opted into the class war. The last two decade s have seen the emergence of aggressive marketing practices, a greater recognition of theatre by government, and no doubt some of the faults of profligacy and spin associated with the current age; Gambon’s performance suggested that it was enough for Falstaff just to be Falstaff. Rather than attempting to define the impossible, that is to say either ‘British Shakespeare’ or the current age, this seminar sought to offer a range of examples of how Shakespeare performance in contemporary Britain had come alive to the five participants (in order of speaking below).
- What is ‘the marketplace of now’? Shakespearean drama and cultural production in contemporary BritainJames Tink (Associate Professor, Tokyo Women’s Christian University)
My paper considers contemporary British Shakespeare in performance with reference to cultural production, especially in regard to the idea of the role of modern drama (and the institution of the public theatre) in Britain. It outlined some accounts of British Shakespeare as part of an overall movement in the dramatic arts that has been labelled ‘left -culturalism’. Turning to the period since 1997, it then considered in what ways the cultural production of drama has changed during this time and looked at arguments about the contemporary relevance of Shakespeare made by the director Dominic Dromgoole and critic Benedict Nightingale. The second part of the paper considered the topic of globalization and localization as particularly important concerns for Shakespearean performance and criticism in recent years. The paper focused on one particular production: The Winter’s Tale, directed by Nicholas Hytner for the National Theatre, London in 2001. This is seen to be a representative example of how Shakespeare performance in this decade has explored ideas of locality and British identity, especially in its presentation of Bohemia and the portrayal of Autolycus by the actor Phil Daniels.
- Tomorrow’s audience: Shakespeare on stage and in the classroomDaniel Gallimore (Associate Professor, Japan Women’s University)
My paper discussed the teaching of Shakespeare in British schools, drawing partly on my own experience from the 1990s. It is only over the last sixty years that English has superseded Latin as the core subject of the humanities; a central concern of the new discipline, therefore, has been that Shakespeare’s plays should not be taught as ‘a dead language’ but as a vibrant linguistic, cultural and historical resource. Teachers are understandably apprehensive of the perceived difficulty of Shakespeare’slanguage, although there has been no shortage of creative advice from in dividuals such as the late Rex Gibson and the education departments of the major theatre companies. Teachers may also appeal to the system its elf, since in 1989, the teaching of a Shakespeare play (typically, A Mid summer Night’s Dream, Julius Caesar, or Romeo and Juliet) became compulsory at Key Stage 3 (ages 11 to 14), with a national test at the end of it. In other words, Britain’s ‘national poet’ has at last become a universal part of the British education system; this, more than anything else, will determine the extent to which Shakespeare remains a part of British culture in the foreseeable future. The compulsory test, however, was recently dropped due to the difficulty of designing questions appropriate to all academic levels, although Shakespeare remains an essential feature of GCSE English, which is taken by the majority of 16 year olds. The difficulty of testing Shakespeare may reflect a still unresolved pedagogic difference between a critical, textual approach that favours academically brighter pupils and an experiential, actorly approach that seeks to make the characters and themes of the plays relevant to pupils’ immediate concerns. Academics have a considerable role to play in this debate, for example due to their influence on new schools editions and development of critical approaches, while theatrical institutions such as the Royal Shakespeare Company and Shakespeare’s Globe have well-established education programmes and offer substantial discounts on tickets for school parties. As part of my talk, I showed a clip from a video produced by Globe Education, which demonstrated the theatre’s educational activities at three levels: with local primary school children, with students from an American university, and with a group of mentally handicapped adults.
- Original pronunciation performances at Shakespeare’s GlobeTomonari Kuwayama (Lecturer, Kobe University)
My paper examined the productions of Romeo and Juliet and Troilus and Cressida, performed in the original pronunciation (OP) reconstructed by the linguist David Crystal at Shakespeare’s Globe in 2004 and 20 05 respectively. According to Crystal’s book Pronouncing Shakespeare and the ‘Show Reports’ kept at the theatre’s archives, these performances were received favourably by the audiences, but British society on the whole did not show much interest in them. In fact, there were only a few reviews in the press, and not a single Shakespearean play has been performed in OP since Troilus at the Globe or elsewhere. There could be various reasons for this disregard for OP performances, one of which may be related to the ‘expected’ sound of Shakespeare established through the history of British education and culture. Moreover, the choice of Troilus, with its complicated speeches and general lack of rhyme, might not have created a strong enough case for the further use of OP. I also suggested some potential merits of OP in Shakespearean performances: as most of modern diphthongs were pronounced as long vowels in OP, it can, for instance, give the Queen Mab speech onomatopoetic effects that represent the swift movement of her carriage, and enhance the declamatory feature of Juliet’s speech in the balcony scene.
- ‘Black Kings’ – colour-blind casting in contemporary British productions
of Shakespeare’s history playsYumi Sato (Associate Professor, Fuji Tokoha University)
In this paper, I tried to consider what kind of interaction there was between practitioners and academics in terms of colour-blind casting. In exploring the theme, I picked up two examples of colour-blind casting, in which black actors played the historical kings, and which therefore might reveal the difficulty of this type of casting. One production, of the Henry VI trilogy, performed for the Royal Shakespeare Company in the year 2000, drew attention partly, but unmistakably, because the protagonist was played by a black actor. In another production, of Henry V, staged at the National Theatre in 2003, the fact that the king was black was deemed to be of less significance. One point I realized in my research was that colour-blind casting, in fact, was ‘colour-conscious’, made only after the directors had taken into consideration the social context of the plays. In both cases, the casting was a challenge to the stereotype that kings in history plays should be acted by whites. Another point was that academics have become increasingly interested in this type of casting in recent years, and it is expected they will continue to explore this issue in the future. Their efforts will surely help audiences in general to understand better the challenges of casting.
- Reading through programmesKyoko Matsuyama (Lecturer, Komazawa Women’s University)
Nowadays, when one purchases a programme for a Shakespeare production, it almost always includes articles written by professional Shakespeare scholars. The inclusion of such articles reveals much about the current relationship between performers and academic research. It seems that the two sides are inseparable in the sense that one cannot exist without the other in the context of Shakespeare performance. The two sides cooperate to suggest the timelessness and the universality of the drama, and to clarify their intentions the inclusion of academic articles in programmes is surely essential. With scholars providing the necessary explanation of or introduction to different styles of performances, audiences also may be encouraged to carry on seeing Shakespeare in the theatre, especially if such articles refer to the current society and problems with which audiences are familiar.
第49回 シ ェ イ ク ス ピ ア 学 会
2010年10月16日(土)・17日(日)
福岡女学院大学(福岡市)にて開催予定
国際学会レポート(London / Seoul)末松 美知子
- The Fourth British Shakespeare Association Conference
- The International Shakespeare Conference at Seoul 2009: Shakespeare in Asia
世界の西と東からシェイクスピア研究の現状を概観する機会に恵まれた。2009 年9 月と10 月に開催された The Fourth British Shakespeare Associa- tion Conference (King’s College London) と The International Shake- speare Conference at Seoul 2009: Shakespeare in Asia (Sookmyung Women’s University / 淑明女子大 学)について報告する。
The Fourth British Shakespeare Association Conference
2002 年より隔年で開催され今回で4 回目を迎えたBritish Shakespeare Association Conference (以下BSA)が、9 月11 日〜13 日の3 日間ロンドン大学キン グス・カレッジとロンドン・グローブ座の共催で開催された。創設当時BSA は、研 究者、演劇人、教員、コミュニティグループ、一般のシェイクスピア愛好家など幅 広い分野の人々が集う境界横断的組織をめざしていたが、今大会では演劇人の報告 や教室でのアクティビティを体験するワークショップを減らすなど、アカデミック 重視の方向へいくらか舵を切った印象を受けた。
およそ30 カ国から延べ400 人が参加した今大会の統一テーマは、Local/Global Shakespeares である。主催者の一人Sonia Massai によれば、early modern texts の諸問題を包括するにふさわしい今日的枠組みとしてこのテーマが頭に浮かんだと のことだ。おそらくは、‘Shakespeare’s World/World Shakespeares’という統一テ ーマを掲げて開催された第8 回国際シェイクスピア学会(2006 年、Brisbane)で の成果に、シェイクスピア「本拠地」として返答を試みようとしたのではないだろ うか。
学会プログラムの巻頭言では本大会の議論の焦点として次の2 点が言及されている:
- グローバリゼーションとマルチカルチュラリズムが現在のシェイクスピア研 究、教育、上演の手法にいかに影響しているか。
- local、national、global というコンテクストがシェイクスピアが活動した 当時から現在まで作品の劇的想像力、上演、受容にどのような影響を与えてきたか。
欧米の参加者やトピックが大勢を占める中、アジアからも日本人11 名を含む十数 名が参加し、学会の「グローバル化」に貢献した。
3 日間のプログラムは、plenary(全体講演)が12、各部屋に分かれてのパネル・ セッションとワークショップがあわせて39、台湾からの招待公演『ヴェニスの商人』 (Taiwan Bang Zi Company)と、盛りだくさんであった。本稿ではplenary セッシ ョンを中心に報告する。
大会テーマと正面から向き合っていたplenary は、Sonia Massai、Ann Thompson、 Rustom Bharucha による3 講演である。特に、インターカルチュラルな上演の可 能性を極めて積極的に肯定したMassai の初日の講演は今大会の基調を提示したと 言って良いだろう。Massai によれば、インターカルチュラルな上演は作品とのダイ ナミックな批評的対話を可能にし、新たな‘common ground’を提供する。この ‘common ground’とは、劇場空間で俳優と観客の行動・思考様式が衝突しテクスト に対する未知の反応がうまれる「場」を指す。インターカルチュラルな上演は異なる文化の観客間で反応が全く異なるなど、そのモデルの確立が難しい。Massai は上 演例により‘common ground’の成立過程を具体的に説明し、差異よりも共通の ‘ethos’を手がかりとすることで新たな上演研究の方向性を示唆しようとした。
Ann Thompson は‘Hamlet: The Universal Mirror?’で自身が編集したアーデン版 『ハムレット』第三版の編集方針とからめながら、劇『ハムレット』をlocal/global な現象として論じた。local な一作家による『ハムレット』は当時の劇場論争への言 及などあきらかにlocal な一面を持ち合わせる一方、材源を広くヨーロッパに求めた その精神はlocal な枠組みをはるかに超えている。何より年間400 を超える『ハム レット』に関する研究成果が世界中で出版される現状こそ、『ハムレット』がglobal なシェイクスピア研究の「場」として成立していることを示しており、これを充分意 識して編集したのがアーデン版『ハムレット』であると締めくくった。
Rustom Bharucha の‘Memory and Misunderstanding: Learning through Intercultural Stories around Shakespeare’と題されたplenary では、インターカル チュラルなシェイクスピア上演をめぐる彼の思索の旅にいざなわれた感がある。基 本的には、このplenary もシェイクスピア上演を欧米のテクスト中心主義や一つの 言語や文化に縛られた解釈から解放すべきだという従来のBharucha の持論に沿っ たものだ。集合的な過去の記憶によって理解されるテクストは同時に上演の場で生 まれる「即興」により生命力を得る。上演とはこのようなエネルギーの流れが劇場空 間に「浸透」(‘osmosis’)する過程でもある。神聖化されたテクスト解釈によって「無 菌化」(‘sanitize’)されたシェイクスピアの再生は、未知の知的コンテクストにおい てその意味を探り「アニマリティ」(‘animality’)を回復することで可能となる。言い 換えれば、シェイクスピアは文化の境界を越える触媒として機能するのだ。 Bharucha 自身このペーパーに明確な結論は無いと断っていたが、ともすると議論 の整合性が優先されるペーパーが多い中で、Bharucha のスケールの大きい自由な 発想は知的刺激に満ちていた。
大会テーマに疑問を投げかけたのはMichael Dobson である。そもそも過去の歴 史が、本来シェイクスピアがlocal でありながらglobal な存在であったことを示し ており、あらためて議論する必要があるのとかとDobson は問う。世界各地を遍歴 するシェイクスピア劇団の歴史は、古くは17 世紀からヴィクトリア朝のBritish Empire Shakespeare Society、20 世紀のBritish Council 後援の旅公演と、現在ま で連綿と続いている。繰り返される世界ツアーにより、英国の劇団による上演が世 界各地の上演と影響し合った結果、今我々がロンドンで見ている上演とて‘foreign’ と呼べるのだとDobson は皮肉に結んだ。
大会テーマに全く言及しないplenary も複数あった。例えばStanley Wells や Andrew Gurr は、国際的に意議のある研究成果を発表することでlocal/global Shakespeares という大会テーマに応えてみせた。Wells がPaul Edmondson と共 同で既存のソネット研究を覆す「劇的」議論を展開したplenary を紹介しよう。「劇 的」であったのは、発表の形式と内容の双方である。二人の掛合いで説明を行ない、 引用をせりふさながらに分担して読むなど、文字通り「劇的」なプレゼンテーション で聴衆を大いに楽しませてくれた上、その内容も極めて「劇的」な指摘に満ちていた。 ソネットの並べられた順序に意味を見出しシェイクスピアの自伝的要素を読み込む従来の解釈に異議を唱え、the dark lady やthe youth などの人物設定自体にも疑問 を投げかける大胆な指摘の背後には、手あかのついた読みからソネットを断固解放 するという明確な意図が見えた。
演劇人のplenary としては、東京芸術劇場での7 月公演『夏の夜の夢』/『ヴェニ スの商人』の記憶も新しい、男性俳優劇団Propeller の演出家Edward Hall が、男 性俳優による上演の様々な利点やシェイクスピアを「メタファー」として上演する 劇団の基本方針を披露した。
ロンドン・グローブ座からは、芸術監督Dominic Dromgoole と教育部門責任者 Patrick Spottiswoode がインタビューに応じ、劇場のglobal な取り組みを紹介した。 グローブ座は、ウェスト・エンドのような商業劇場でもなくロイヤル・シェイクス ピア・カンパニーのように巨大な補助金を受けてもいないユニークな劇場であるが、 その成功の原因は単純に観客中心の上演に徹して来たことであるという。海外での ツアー成功や観客の二割を外国人が占めるというglobal な状況もこの方針に従った 結果にすぎないとのこと。2012 年のオリンピック開催時期には、世界からの招待公 演も含めてシェイクスピア全作品を一ヶ月で上演するフェスティバルを計画中だそ うである。今後もその活動に大いに期待したい。
以上のplenary に加えて、前述の通りセミナー、2〜3 人で行うパネル・セッショ ン、ワークショップが多数開催され活発な議論が展開された。大会テーマを反映し てlocal/global な視点からシェイクスピアを読み直すセミナーが大勢を占め、英国、 ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アラブのシェイクスピア、インターカルチュラル なシェイクスピアまで、幅広くバランスを心がける配慮が見えた。local/global なト ピック以外では、シェイクスピアと映画、テレビ、教育、デジタル化などが議論の 対象となっていたが、取りたてて目新しいテーマは見当たらなかった。
日本からは、冨田爽子がセミナー‘Shakespeare’s Europe: Early Modern Contexts’ に、浜名恵美、エグリントンみかがセミナー‘Asian Shakespeares in Europe’ に、南隆太がセミナー‘Localizing Shakespeare in Asia’に参加した。また大矢玲子 は、パネル・セッション‘Intercultural Shakespeare & the Modern’でオーガナイザ ーを務めた。
次回第5 回大会は、‘Shakespeare: Sources and Adaptation’というテーマで、2011 年9 月ケンブリッジ大学において開催予定である。
The International Shakespeare Conference at Seoul 2009: Shakespeare in Asia
(Sookmyung Women’s University / 淑明女子大学)
300 人を超える会員を擁する韓国シェイクスピア協会は、3〜4 年に一度国際学会 を開催している。その4 回目となった今大会がソウルのSookmyung Women’s University で10 月23〜24 日に開催され、二日間で延べ150 人が出席した。アジ アの6 カ国(日本、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール)から招かれた 13 人のゲスト発表者を含めて15 本の発表が行われた。
大会は「アジアにおけるシェイクスピア上演」、「アジアにおけるシェイクスピア 教育」、「その他のトピック」の三部で構成されていたが、その区分はあまり厳密ではない印象を受けた。
第一部の6 本の発表のうちアジア各国の上演を論じる発表は4 本で、そのうち2 本は中国人大学生によるシェイクスピア上演フェスティバルに関する発表であった。 日本から参加した小林かおり・末松美知子はウェブ・アーカイブA-I-S-A (Asian Intercultural Shakespeare Archive) 構築の現状と研究における今後の可能性を 共同で報告した。
第二部の4 本の発表のうち、自国のシェイクスピア教育の現状について論じたの は中国のLuo Yimin とシンガポールのGenice Ngg である。敷居の高い異国の文学 であることに加え、最近の若者の文学離れが一層シェイクスピア教育を困難にして いるという指摘に、参加者の誰しもがうなずいた。マレーシアのC S Lim は‘Why Shakespeare in Asia?’というペーパーで、ヨーロッパという概念に対抗できるよう なアジアの概念を我々自身が生み出さなければならないと説いた。また、南隆太は、 ‘Re-defining the “Foreign” of “Foreign Shakespeares” in Asia’で、シェイクスピ アが‘foreign’で歌舞伎が‘familiar’であるといった単純な発想を批判し、‘foreign’と ‘familiar’の概念が複雑にからみあう‘intracultural’な日本のシェイクスピア上演の 様相を分析した。
第三部の5本の発表の中では、日本のアニメを例にシェイクスピアの世界的権威 に疑問を呈する‘improper Shakespeares’の意義を論じた吉原ゆかりの‘ “Improper” Shakespeares in Japan’ 、中国でシェイクスピア全作品の翻訳を成し遂げた梁実秋 を紹介し、その翻訳の特色を分析したYan Xiaojiang の‘On Liang Shiqiu’s Translation of The Complete Works of Shakespeare’が印象に残った。
いずれのセッションにおいてもディスカッションの時間が充分に取られ、事前に 入念な準備をして臨んだ討論者(韓国シェイクスピア協会員)やフロアーからのコ メントと質問で議論は充実したものとなった。
初日のレセプション後に英語で上演された『オセロ』も嬉しい驚きであった。作 品の後半のみとはいえ、2時間弱に及ぶ公演を上演したKorea Shakespeare’s Kids という劇団の俳優は、全て韓国シェイクスピア協会所属の大学教員だったのである。 1983 年より協会の中心事業の一つシェイクスピア・フェスティバルで原語による学 生向け公演を続けて来たとのこと。上演を教育の一環として生かそうとする強い意 欲を感じた。
当然のことながら、シェイクスピア研究に従事する研究者達の視線の先には西洋 がある。今回の韓国での学会においても、アジアの研究者達がいかに多くの欧米の 先行研究や研究手法を共有し、かつそれに依存しているかを再確認した。しかし、 西洋と東洋のbinary により規定されないアジアの概念やアジア独自のシェイクス ピア研究手法模索のためのネットワーキングの必要性を参加者全員で確認できたこ とは、今回の収穫である。そして、韓国シェイクスピア協会はそのネットワークの hub として名乗りを上げようとしているという印象を持った。
第4回シェイクスピア・ワークショップ

第4回シェイクスピア・ワークショップは第48回シェイクスピア学会 と同会場の筑波大学で開催され、下記の通り大学院生5名による活発な議論が交わされました。
日時:10月4日(日)13時−16時
場所:筑波大学3A 202室
メンバー(五十音順):
- 大木絢深 (聖心女子大学大学院博士後期課程)
パリスの目は何色か?
—— シェイクスピアの日本語翻訳における色とその表象について —— - 小泉勇人 (早稲田大学大学院博士前期課程)(司会)
『尺には尺を』における、娼館取り壊しのサブ・プロットが果た す機能
—— 梅毒が蔓延する世界とそうではない世界を作り出す境界 線 —— - 杉浦美咲 (学習院大学大学院博士前期課程)
テクストはどのようにパフォーマンスされるのか?
—— 『十二夜』の異性装と恋愛に関する一考察 —— - 鈴木このみ (学習院大学大学院博士前期課程)
わからない『ハムレット』 - 山田美幸 (北海道大学大学院博士後期課程)
Indian Othello像
—— 複合された「区別」を生みだすインド ——
コメンテイター(五十音順):
廣田篤彦(京都大学准教授)
前沢浩子(獨協大学准教授)
第5回シェイクスピア・ワークショップは、
2010年10月17日(日)
福岡女学院大学(福岡市)にて開催予定
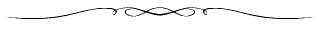
♠ PDFファイルをご覧になりたい方は、こちら へ
