���{�V�F�C�N�X�s�A������
Shakespeare News
Vol. 48 No. 2
December 2008
�w �� �� �W ��
�w �� �� �W
���ʍu���i�v�|�j
�ԍ⌛�Y�@�V�F�C�N�X�s�A�^�ِl�����̍Ղ�
�������\�i�v�|�j
Sauny the Scot (1667)�ɂ݂�V���Ȋ쌀���ɂ���
�X�e�B�[�����Y�ƃ}���[�� —— 18���I�V�F�C�N�X�s�A�S�W�ɂ����钍�߁A��ǁA�����āu�F��v
18���I�̔Ŗ{�ƃt�H���I�{�ւ̏�������
Thomas Nashe, The Unfortunate Traveller ���Łi1594�j�̈���Əo��
�w�G�h���[�h�O���x�ɂ����������ʂƗ��j�L�q
Peele's David and Bethsabe —— 1590�N��̐��������߂�����
���l�T���X�����ɂ����鉉�Z�ƌ�����
�������R���[�̈��� —— Hamlet �ɂ����鋶�C�̊K�w���ƎЉ�s��
�n�b�s�[�G���h��Tom Thumb —— Eliza Haywood�� The Opera of Operas �ɂ����錋����
Edward I —— ����������ꂽ���܃��I�m�[���̋؏���
���蕨�ƌ��Â��Ǝ� —— �w�A���g�j�[�ƃN���I�p�g���x�ɂ����鑡�^�̖��
�n�̉ʂĂ���̗��K�҂Ɓw���F�j�X�̏��l�x
Manga �ƃV�F�C�N�X�s�A���o��Ƃ�
�gA voucher stronger than ever law could make�h —— �w�V���x�����x�ɂ����鏑�L��p�ƃ��f�B�A�E���e���V�[
�ߑ㏉���C�M���X���s�L�ɂ����� cabinet of curiosities �I���_
���݂Ɩ@���ƁA�����ă}���N�X
�Z�~�i�[�i�v�|�j
���ʍu�� �i�v�|�j
�V�F�C�N�X�s�A�^�ِl�����̍Ղ�
 |
|
�u�ِl�v�Ƃ��u���E�v�Ƃ��u�����v�Ƃ������e�[�}�����܃V�F�C�N�X�s�A�����Ńu�[���Ȃ��Ă���̂ł��Ђƌ����A���O�ɂ�������炸�u�������������Ă��܂����B���X���[�E�t�B�[�h���[�́w�V�F�C�N�X�s�A�ɂ�����ِl�x��ㆂ��Ă݂�䩑R�����B����͂��܂����悤�̂Ȃ����E���Ɗo������߂��B���w���̎��ɓǂ��Ƃ̂���w���F�j�X�̏��l�x�ɖ{�̈����O�Y��ł�����x�ǂݒ����A�����̐��̗��ꂩ�牽�������邩�A�����ɓq���Ă݂����Ǝv�����B��̂��Ƃ����b������B���炩���߂��f�肷�邪�A��s�����̗ނɂ͂��������ڂ�ʂ��Ă��Ȃ��B�l�����ꂩ�炨�b�����邱�Ƃ́A�����炭���łɒN�������������Ƃ�������Ȃ����A����͎d���̂Ȃ����Ƃƒ��߂Ęb��i�߂�B
�w���F�j�X�̏��l�x�`���ɓo�ꂷ�鏤�l�A���g�j�I�̗J�T�A���̌����͉����낤���B�D�̐ςׂ݉̂��Ƃł����ς��ł��Ȃ��炵���B�ނ́u���Ԃ��C�ɂ�������v�Ƃ�������B����́A���ƁE���Ղɕt���܂Ƃ��A�C�f���e�B�e�B�̕s���ƊW���邩������Ȃ��B�����Ƃ����ߓn���ɂ����鏤�l�̃A�C�f���e�B�e�B�̊����̃h���}�Ƃ��āA���̍�i��ǂݒ�����̂ł͂Ȃ����B�Q�I���N�E�W�������ɂ��A�ǂ�ȕ����ł��t�����Ɉِl�͏��l�Ƃ��Ďp�������B���Q�҃I�C�f�B�v�X�ِ͈l�Ƃ��Ă̏��l�̐_�b�I�`�ۉ��ł���Ƃ����B�Ñ�M���V�A�ŏ��l�́A�߁E�ŁE�a�C�E�q�ꂻ�̂��̂ł���A���Ȃ��Ƃ������������^�t�@�[���疳���ł͂��肦�Ȃ��d���������B���l�͓y�n�̎҂ł����Ă��ِl�̂悤�ɏ��������B���l�̌n�̈قȂ鋤���̂��q���A�g�p���l�̗������������l�ɖ|�A���p�I�s�ׁE�B���p�Ƃ��ė�����y�ݏo���B�}���N�X�̌����悤�ɁA���i�����͋����̂��s�����҂Əo��ڐG����Ƃ���Ŏn�܂�B������z�����X�͏��l���u��������ҁv�ƌĂB���̂悤�ȏ��l�Ƃ������̂��A�w���F�j�X�̏��l�x�ł̓Z�b�N�X�⌋���Ɠ�d�ʂ��ɂ���Ă���悤���B���ɓq����j�������������Ė��m�Ȃ�����̏�ւƒ���B���Ƃ̋N�����C���s�ׂƂ���w�҂�����B�܂��u���ٌ��Ձv�Ƃ����āA�قȂ鋤���̂̐l���m���������܂܌��t�����킳���ɕ�������������Ղ̑��݂��m���Ă��邪�A�ٕ������������q��Ƃ̐ڐG�������Ƃ������Ƃ�����ɂ������̂�������Ȃ��B�e���j�G�X�́w�Q�}�C���V���t�g�ƃQ�[���V���t�g�x�̒��ŁA�u��Z�I�ȓy�������ɂƂ��ď��ƂƂ́A���̂Ȃ��A�����₷�����ۂ��v�ƌ����Ă���B���l�͗��Q�҂ł���A�������킵���댯�ȑ��݂ł������B
�A���g�j�I�̓V���C���b�N�ɑ��āA�Ȃ�����قǍ��ʈӎ����ނ��o���ɂ���̂��낤���H�ނِ͈l�Ƃ��Ă̎��Ȃ̕s����Ȃ�������B�����邽�߂ɁA������l�ِ̈l�V���C���b�N�ِ̈l�����ނ��o���ɁA���������悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B�A���g�j�I�ƃV���C���b�N�ɂ́A���ꂼ��قȂ闈����w�������ِl�Ƃ��Ă̋L�����e�𗎂Ƃ��Ă���悤���B�O�҂̓L���X�g���k�̖f�Տ��l�Ƃ��āA�Ñネ�[�}�l�̌ւ�ƃ������������Đ�����B�������Ղ�V���N���[�h�̌��ՂŔ���ȕy���W�ς��Ă���A���݂̑���͂��Ȃ��B��҂͍����݂��Ń��_�����k�B�����Ƃ����ߓn���ɂ͂��܂���������F�߂��Ă��Ȃ��ߑ�I��������g�ɑтт��C�z������B�w���F�j�X�̏��l�x�͒����̌��Փs�s��ɁA�Ñ�I�������Ƃ��ꂩ�猻��Ă���ߑ�I�������E���E�ςƂ��A�Փ˂̃h���}�������Ă���悤���B
| �A���g�j�I | �c���O�̋���͗r���l�A���R�Ɏq���Y�ނƂł����������̂��B |
| �V���C���b�N | �����A�ǂ��ł����B������ɂ���A��������A���h�Ɏq���͎Y�݂܂���ȁA��O�ǂ��̂Ƃ���ł́B�i������j |
| ������ �r�͂������Ď��R�Ɏq���Y�ނ킯�ł͂Ȃ��B�ƒ{�Ƃ��Đl�Ԃ�������������A����ΘB���p�̂悤�ɐl�דI�ɉ��ς����A���̌��ʂƂ��ėr�͎q���Y�ށB |
�����݂��͌�̋��Z���{��`�̏����`�ԂƓǂ߂邪�A���܂��q�ꂽ�s�ׂƂ��Ċ������ꂽ�B�A���g�j�I�͖@���x�I�ɂ͍����݂���F�߂Ă��A�������Ƃ��Ă͋����Ȃ��B�@��x�̌��Ԃɐ��N���ĂƂ肠�������@�I�ł����Ă��A�ǂ����ɔ��Љ������Ă���B���������@�ƃ������̌��ԂɁA�ٔ��ł̓|�[�V���̂������k�ق����낤���ĉ�����������������B�����ł́A���_���l�V���C���b�N�͈ٖM�l�ł���A���F�j�X�s���̊O���ɒu���ꂽ�l�ł���Ƃ������Ƃ��ނ��o���ɂ����B�V���C���b�N�̓L���X�g���I���E�E���F�j�X�̎s���Љ�ɑ��ĈٖM�l�̍��ɂƂǂߒu����Ȃ�����A���@�̈ӎu��\������B�ނ̓��_���̖��ɑ��鍷�ʂɍR���A���F�j�X�̖@���x�ɑ������킢�݁A���ǂ͔j���B
�}���N�X�́w���{��`�I���Y�ɐ�s���鏔�`�ԁx�ɁA�u�����Љ�̃��_���l�̂悤�ɌÑ㐢�E�̊Ԍ��̒��Ő������鏭���̏��Ɩ����A����Ƃ̓Ɛ�҂̏ꍇ�ɂ����A�y�͎��ȖړI�Ƃ��Č����v�Ƃ����ꕶ������B����Εy�����ȖړI�Ƃ��Đ�����ِl�Ƃ��Ē����Љ�̃��_���l������߂��Ă���Ƃ������Ƃ��B�A���t���b�h�E�V���b�c�͌��ۊw�I�Љ�w�̗��ꂩ��A�u�ِl�Ƃ͗��j�������Ȃ��l�Ԃł���v�ƌ�����B���_���l�͓y�n�ɍ��t�������j�������Ȃ��l�Ԃł��邪�̂ɁA�����炭�����Љ�̉��[������ߑ�̉��l�������\�����Ă����̂�������Ȃ��B
���{�̎���Ɉ�������ƁA�w��ًL�x�Ɏ��@��m�������Z�Ƃ��c�ގp���L����Ă���B�Ԗ�P�F�ɂ��A�u�������v�Ƃ������̂�S�ۂɂ��̂₨�������ꂢ�ȁu�����̍��v�Ƃ��Ă�����^�p���A�����̕n�����l�X���~�ς���d�|���ɂ����Ƃ����B�₪�Ă���͕y�����ȖړI�Ƃ��ēW�J���n�߂�B�܂������̊G�ł́A�����݂��͕K���얞���������̎p�ŕ`���ꂽ�B�m���������������̖����������B�����ɂ́A���q�ɓZ����q���_���̌��Ђ̂��Ƃŏ��������h�ߑ��u�����݂����炵���B���m�ł͂����炭�A�v���e�X�^���e�B�Y���̖u���ɂ���Ă͂��߂ď��ƁE���Z�ƂɓZ����q�ꂪ��菜���ꂽ�B�����E�y�̒Nj����ΕׂƂ����V���ȃ������ɂ���čm�肳��A�����Ď��{��`���{�i�I�ɓ��������B���{�ł͕����I���������A���m�ł̓v���e�X�^���e�B�Y�����A���ꂼ�ꂱ�̖��ɉe�𗎂Ƃ��B
�w���F�j�X�̏��l�x�́A�����Ƃ����ߓn�̋G�߂ɐ��N�����A���Ƃ⍂���݂����߂���A�����ꂽ�������̏�i���f���Ă���̂ł͂Ȃ����A����ȋC������B�ȏ�u�ِl�_�v�Ƃ����������珤�l�E�����݂��߂Ă݂��B
���Ă�����̂��b�Ƃ��āA�ŋ߂����Ƃ��C�ɂȂ��Ă���e�[�}�u�H�ׂ�^�����^�E���v���߂���֎~�E�^�u�[�����グ�����B�̘b�Ɉٗލ���杂Ƃ����̂�����B�Ⴆ�u�^�̉��l�v�����A�����ł͐H�Ɛ��Ƃ̊Ԃɋ����ے��I���т���������B�����Ė�������̂�H�ׂ�Ƃ������Ƃ́A��������̂��E���Ƃ������Ƃł�����B�w���F�j�X�̏��l�x�ɂ��A���́u�H�ׂ�^�����^�E���v���߂���֎~�E�֊�������߂��炳��A���ꂪ�����̉B�g�I�������Ȃ��Ă���Ɠǂ߂�̂ł͂Ȃ����Ƃ����\��������B�����ɂ̓��^�t�@�[�Ƃ��Ă̓������J��Ԃ��o�Ă���B�܂����̂Ƃ��Ă̒��b���������Ȃ�̉ӏ��Ŏp��������B����͂��Ă݂����Ǝv���̂����A�����܂ł͂܂��͂��Ȃ��̂ŁA���̎�O������̘b���������������Ă����������Ǝv���B
�u�l�Ԃ̓��P�|���h�v�Ƃ����\�����C�ɂȂ��āA���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă݂��B
�H������̎w�W�Ƃ��Đl�Ԃ⓮���ނ��Ă݂�Ɖ��������Ă��邩�B�E�����߂ɎE���s�ׁA����͐l�Ԃɂ��Ă͖@���x�I�֎~�̑ΏۂƂȂ�B�����ɂ��Ă͐����т̂��߂ɎE���Ƃ������Ƃ�����B�H�ׂȂ��ꍇ�͂���������B�V�тƂ��Ă̎�́A�P�ɎE�����߂ɎE���Ƃ������ƂŔ���邱�Ƃ������B�H�ׂ邽�߂ɎE���s�ׁA����͐l�Ԃł���J�j�o���Y���ɂȂ�B�����ɂ��Ă͂ǂ����B�ƒ{�͐H�ׂ邪�A�y�b�g�͐H�ׂȂ��B�������ߐ��̂��̗ނ̖{�ɂ́u�L�̓��͂��������v�Əo�Ă��邵�A���̓��������̊Ԃ܂ŐH�ׂ��Ă����B�܂��^�u�[�̑Ώۂł��邪�̂ɐH�ׂȂ�����������B���̂����肩��Ȃɂ��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�����o����B
�u�����v�Ƃ����e�[�}�ɂ��Č����A���̎ŋ��ł͕����̋ߐe�����I�~�]�A������^�u�[�Ƃ��ĕ`���Ă���B�u�킵�̖��́A�킵�̌������v�Ƃ����V���C���b�N���A���̃W�F�V�J�͋��₷��B�����e���|�[�V���ɉۂ������I�т̎����ɂ��A�ߐe�����I�^�u�[�ɂ��}���̂悶�ꂪ��������B���邩��������邩�A�j�����͋��ɂ̑I���𔗂��A���m�Ȃ鐢�E�ւ̒������������B
�u�E���v�Ƃ����e�[�}���߂����āA��d�ɂ��B������Ă��邯��ǂ��A�u���P�|���h�v�ɂ͐l���H�̏L�����t���܂Ƃ��A����ȋC������B�u���̔������̂̓��A��������P�|���h�A���̂́A�����Ȃ镔������Ȃ�Ɓc�B�v�u�l�Ԃ̓��A�P�|���h����������āA�r�̓��A���̓��A�R�r�̓��قǂ̒l�ł����Ȃ��Ⴀ�A���ɂ�������B�v�l�Ԃ̓����e�[�u���̏�ɐ����A���e�̂悤�ɉ�X�̔]�����悬��B�����B�E�X�g���[�X�͋����a�ɂ��ĐG�ꂽ�G�b�Z�C�ŁA�u�����̓���H�炤���H�ƃJ�j�o���Y�����v�������ʐe�����W�������Ă���Ƃ������Ƃ��A�����a���̒��ŘI�o�����v�ƌ����Ă���B���H�Ɛl���H�́A��X�����ʎv���Ă���قǒf�₵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B�l�Ԃ̓��ł��u����ނ�a���炢�ɂ͂Ȃ�B���̑����ɂ͂Ȃ炸�Ƃ��v�ƃV���C���b�N�͌����B�܂��u���_���l�ɂ́A�ڂ��Ȃ��̂��B�c�肪�Ȃ��̂��B�݂������A�̑����t�����Ȃ��Ƃ����̂��v�Ƃ����悤�ɐg�̂��E�v�f�ɕ������Č����邱�ƁA����͓����̓X���ɕ��ԉƒ{�̓��̕������̂�A�z������B
�ٔ��̒��Ń|�[�V���́A�u����ɂ������āA�������L���X�g���k�̌�����H����Ƃ������Ƃ��́v�y�n�����Y�����ׂĖv������ƍ�����B�k�قȂ���ƂĂ��C�ɂȂ�䎌���B����������Ƃ����ɂ��}�����ꂽ�J�j�o���Y���̉e�������Ă���̂ł͂Ȃ����B
�l�Ԃ̐g�̂̏ے��I�ȉƒ{�������̌��t�ɂ���ĉʂ�����Ă���B�ƒ{��H���ɂ��邽�߂ɁA�q�{���́u�����v����сu�j�{�^�j�E�v�̋Z�p��p����B�����́A����ے肵���B��l�Ԃ̃R���g���[�����ɒu�����ƁB�܂��j�{�^�j�E�̋Z�p�ɂ́A�u�������v�̋Z�p���K���܂܂��B�����Ȃ�����̓��͐H���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾�B�������m���E���i�����A����ɂ͉H������B�u���Ɠ��̕����v�̔w�i�ɂ͂���Ȃ��Ƃ��B����Ă���̂�������Ȃ��B�u���P�|���h�v�͉��i�̐ݒ��\�z�����邪�A���i���ݒ肳���Ό������l���������ă}�[�P�b�g�̈�p���߂邱�ƂɂȂ�B�E�l���J�j�o���Y�����B���Ȃ܂܂Ɏ����ꂽ�V���C���b�N�̗v����ے肷��_���Ƃ��āA�|�[�V���͐g�̂����Ɠ��ɕ������邱�Ƃ��v�������B���{�ł͂��āA�H�ׂ铮���̓����u�V�V�v�ƌĂB�C�m�V�V�A�^�k�V�V�A�N�}�V�V�A�J���V�V�A�A�I�V�V�i���J���V�J�j�c�A�H�ׂ���P���m�̓��̓V�V�ł���B�|�[�V�������Ɠ��̕������咣����Ƃ����A���̓��m�Ɍ��͍��ɂȂ���A����_�������o����Ă���̂�������Ȃ��B�����̕s�\���������āA�g�̂����m������H������邱�Ƃ�j�~����Ƃ����_�����Ă��B
�����ŋC�ɂȂ�̂͋]���Ƃ��ẴL���X�g�̐g�́B�p���ƕ������A���Ȃ킿���ƌ��̃V���{���Y�����B����͐_�̐g�̂����H���邱�ƁA����Ӗ��ł͂����ɂ���߂�ꂽ�J�j�o���Y�����e�𗎂Ƃ��Ă���̂�������Ȃ��B�L���X�g���k�̐M�����̂��X�V���Ă������߂̋V��Ƃ��čs���Ă���A���Ɠ��ɐg�̂����Č�����p���ƕ������̃V���{���Y���A�����ւ������Ɉڍs���Ă����悤�ȁA����Ȃ���ǂ����܂�ł���B
���̂悤�ȃJ�j�o���Y���̕��i�͈�u�����I�o���A�����ɔے肳��Ĉӎ��̐[�݂ɒ��߂���B�u���P�|���h�v�Ƃ������t�ŁA���ꂪ�J��Ԃ����������B�@��x�ł͎E�l���ق����Ƃ͂ł��Ă��A�l���H���ق����Ƃ��ł��Ȃ��̂�������Ȃ��B�l����H�ׂĂ͂����Ȃ��Ƃ����@���́A���ꎩ�̂���������A�@���Ƃ��Ď�����邱�Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�u�H�ׂ�^�����^�E���v���߂����āA�O�̋֎~�E�^�u�[���A�����Ă����N�Ƃ���Ƃ������Ƃ��A���̍�i�̒��ɂ͌J��Ԃ��o�ꂷ��B����������������J�ɓǂ݉����ƂȂɂ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����邪�A�܂�����͑N���ɂ͌����Ă��Ȃ��B
�l���v�����ł��܂��b���������Ƃ́A�V�F�C�N�X�s�A�����̒��ł��łɘ_�����Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂł͂Ȃ����Ǝv�����A����w���F�j�X�̏��l�x�Ƃ�����i�Ɍ����������Ă݂āA�l���g�͖ʔ��������B�̘b�̈ٗލ���杂Ƃ��������̂Əd�ˍ��킹�ɂ����肵�Ȃ���A�Ȃɂ��������Ă������ȗ\�������͂���B�l�ɂƂ��āw�ِl�_�x�͖{���ɎႢ���̎d�������A�ŋ߂ɂȂ��āA���k�Ƃ����t�B�[���h�������蔲���Ă��炽�߂Ĉِl�_�̂��̏ꏊ�ɉ�A���悤�Ƃ��Ă���A����Ȋ��G�������Ă���B
�i�v�ӁF�����O�Y�j
��47�� �V �F �C �N �X �s �A �w �� �� ��
2008�N10��11���i�y�j�E12���i���j
�� ��F ��茧����w�i���L�����p�X�j
�������\�i�v�|�j
��P��
�i�� �w�K�@��w�����@���� �t�v
Sauny the Scot (1667)�ɂ݂�V���Ȋ쌀���ɂ�����a ���s
Sauny the Scot (1667)�́A Taming of the Shrew �̉���Ƃ��Ēm���鉤�����Ê��̊쌀�ł���B���̌��ł́A�薼�̖����������o�D�������John Lacy�̊쌀�I���Z�Ɍ�������悤�A�]��Sauny�̖��ǂ����傫�����āA�V���ȁu���Ⴖ��n���́v�����o���Ă���B�����ASauny ��John Tatham�ȗ��̃X�R�b�g�����h�l�^��ɂ��錀�̌n���ɘA�Ȃ�L�����N�^�[�ł���A�X�R�b�g�����h�ꕗ���a�肪���ۂɂ̓C���O�����h�k���n���h���J�X�^�[�̕����Ō���邱�ƂŁA�u�p���v���肩�u�C���O�����h���v���̕s��������\���B�䂦�ɁA�{��i�̊쌀���͕��G�Ȃ��̂ł���B
Sauny the Scot �Ƃ́A���������ɊO���l��������������e�N�X�g�ł���A��Ƃ���Margaret��Sauny�ɂ���Ĕ�������s���̐����A17���I���t�̃C���O�����h��
Sauny the Scot �ɂ͑��̌���i�ւ̌��y���������A��i���ŗB��u�C���h�v�ւ̌��y���Ȃ����ӏ��i5.1.161-62�j�́A�ȉ��̃C���^�[�e�N�X�`���A���e�B�������炵���\��������B�����AJohn Dryden�� The Indian Emperor (1665)�ŏ������ Nell Gwyn���A����1667�N�� Sauny the Scot �������� Margaret ���������Ƃ���A�u�C���h�v�Ƃ������t����̘A�z�ŁA���̉����I��Ԃ̓C���O�����h�����ЂƂ���тɃC���h�ɂ܂ōL���������Ƃł��낤�B�C���O�����h�l�������\����Margaret ��
�X�e�B�[�����Y�ƃ}���[��
—— 18���I�V�F�C�N�X�s�A�S�W�ɂ����钍�߁A��ǁA�����āu�F��v�ĒJ ��q
1793�N�ɑ�������łƂ��ďo�ł��ꂽSteevens�ɂ��15���W���ł̏����i�gAdvertisement�h�j�́A�ʏ�Steevens�ɂ��Malone�ւ̍U���A�܂�1790�N��Malone��10���W���łւ̎��i�ɖ��������s�s�Ȕ����Ƃ��ĉ��߂���Ă���B�Ƃ�킯Margareta De Grazia��Brian Vickers��Steevens�ᔻ�́A�u���̈�����������D���v�Ƃ��Ă�Steevens�ɔ����Ђ��߂Ă���Boswell��Malone��̎��I�Ș_�]�ɂ���č\�z���ꂽ���߂ł���A������l��Steevens�ւ̕Ό������̂܂܌p���������߂ƂȂ��Ă���B�e�N�X�g�Ҏ[�̌���̊O���ʼnQ�����Ă���Steevens�Ƃ����l�Ԍl�ɑ��邱�̂悤�ȕΌ��ɑ������邱�ƂȂ��ASteevens��Malone�̊W�Ƃ��̌���ɂ�����Ӌ`���ĉ��߂��Ă����ׂ��ł���A�Ƃ����ϓ_�̂��ƂɁA���Վ������X���ɂ�����Steevens�̕Ҏ[���@��Malone�̏W���ŁA����ɂ�19���I�ȍ~�̏W���łƂ̊ւ��ɂ��čl�@�����BSteevens�̔ł̓����́A�����������Ă�����ʓǎґw�ւ̕X���͂���A�ǎ҂ɂ�鑽�l�ȉ��߂̉\�����ӎ����A���ߕ�����啝�ɑ��₵�A���������钍�߂�����ꍇ�͂ǂ��炩�ӓI�ɑI�����邱�ƂȂ����L���A���ꂼ��̒��߂̌�ɒ��ߎ҂̖��O��t�������Ƃł���BMalone��F1�ȂnjÂ��e�N�X�g�̌��Ђ��ŗD�悵�Ă���悤�Ɍ������A���ۂɂ�1785�N�ł�Johnson-Steevens�ł̍Z�����̗p���Ă���A���̍Z�����@�͐�s�e�N�X�g�̂����Ɣ�ׂ�V�X�e�}�e�B�b�N�ɂȂ��Ă͂�����̂́A�n�C�u���b�h�Ȑ��i�������̂ƂȂ��Ă���BDe Grazia�́AJames Boswell �iBoswell Jr.�j�ɂ���ď������ꂽ1821�N�̑S�W�łɂ�1790�N��Malone�ł̍\�������f����Ă���Ǝw�E���A1790�N�ł̈�Y�ƁA���̑啝�Ɋg�傳�ꂽ1821�N�ł̈�Y�̊Ԃɑ��݂��鋤�ʐ���F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝ咣����B�������A1821�N��21���{��ڂɂ���ƁA���̔ł��\�����Ă���悤��1790�N�ł̒��߂Ƃ̗ގ��������ނ���A1793�N�ŁA�����Johnson-Steevens�� 1803�A1813 �N�̔łƂ̕��ɗގ������F�߂���̂ł���BSteevens��Malone�̊ԂɁA���Ƃ����I�l�I�ȑΗ��͂������Ƃ��Ă��A����2�l�̕Ҏ[�����S�W�͓���̏W���ŕҎ[�̃p���_�C���ɂ̂��Ƃ��ĕ҂܂ꂽ���̂ł���A�Ƃ������Ƃ�_�����B
�i�� ������w�����@���q �Y�i
18���I�̔Ŗ{�ƃt�H���I�{�ւ̏��������Z�{ �K�q
��������V�F�C�N�X�s�A�E�t�H���I�̃R�s�[�ɂ͏������݂̂�����̂����Ȃ��炸���݂���B�{���\�ł́A�{�h���[�}���ُ����̃Z�J���h�E�t�H���I�ƃt�H�[�X�E�t�H���I�̍��{�i�����ԍ�Arch.Gc.9�j�A����сA�t�H���W���[�}���ُ����̃T�[�h�E�t�H���I�i�����ԍ�s2914 Fo.3 no.20�j�̏������݂ɂ��āA�摜��p���ĕ����B���ꂼ��A�������݂Ɠ���̔Ŗ{�Ƃ̂������̖��ڂȊW�����w�E����19���I�㔼�ɔ��\���ꂽ��s�����̑��݂��Љ���̂��A�������݂̓�������̓I�ɂ݂��B
Rowe�{�Ɉˋ����鏑�����݂�����Gc.9�̏ꍇ�ł́ASig.*1 �ɏ������܂ꂽ�u�V�F�C�N�X�s�A�`�v�̗v��A���̕����̃y�[�W�ɂ݂��邻������̈��p����͂��߁A���ꉻ�������G�A���ꊄ���g�����̈ړ��A�o��l���\�̓]�L�Ȃ����͐����������ӏ��Ȃǂ��݂�Ɠ����ɁARowe�{�o�ňȑO�̃����h���ɂ�����㉉�ɂ������N���ώ@����邱�Ƃ��w�E�����BPope�{�Ɉˋ����鏑�����݂�����Fo.3 no.20�̏ꍇ�ł́APope�{�ɂ���ꏊ�̐ݒ��ތ����A�e��r���A���ꊄ��̓]�L������������ق��A�e�N�X�g�s�����ʖ`����Pope�������e��}�[�N���]�L����Ă���݂̂Ȃ炸�A�Ǝ��̊g�[���{����Ă���ARichard II�̎��̏�ʂɎ����Ă͖ڂ�������������̊G���`�����܂�Ă��邱�ƁA��������B�܂��ATheobald�{����̏��������Ȃ����荞�܂�Ă��邱�Ƃ��w�E�����B
�����ɁAHanmer�{�̋r���ƃO���b�T���[��]�ʂ���������w�����T�[�h�E�t�H���I�iMR733�j�i��44��w��Z�~�i�[�ɂĕj�̎���ɂ́A�����āA���l�̗Ⴊ�������݂��邱�Ƃ����m�ɂȂ����A�Ƃ��������ŁA���̂悤�ȏ������ݍs����W.H. Sherman�̋ߒ��ɂ�����p���p���ăt�H���I�́u�J�X�g�}�C�Y�v�Ɖ��ɖ��t�������A�Ƃ����B�iFolger�R�s�[�̒����͉Ȍ���i19520266�j�̏����������̂ł���B�j
Thomas Nashe, The Unfortunate Traveller ���Łi1594�j�̈���Əo���p �m��
�{���\�ł́A�悸Unfortunate Q2 �iThomas Scarlet������j�̕��S����Ǝ҂��A�{���Ɍ���鑹�������������� John Danter�ł��邱�Ƃ��m�F�����B���ɓ�ӏ��̈�����ŁA�i�b�V�����������{������������Ȃ���������{�������ɕ������������Ƃ������ɂ��āA���{�̋��ʒu�̓�������Scarlet��Danter�͓�x�ʉ�A2�V�[�g����T�d�Ɏ��s�����Ɛ����B�܂�Q2���������i�b�V���̗��R�Ɩ{���AScarlet��o�ŋƎ�Burby��Q2�o�łɂ܂��Ӌ`��ʂ̎���Ȃǂ𐄗ʂ��A��ƁA����ƎҁA�o�ŋƎ҂��a���o��Q2���߂���W�҂����́u�v�f�v���ЂƂЂƂ_�����B�܂�Q1��Q2�̏o�Ōo��̔�r��AScarlet��Danter����������������ΏƓI��Q2�̐A���X�^�C���Ƃ��ꂼ��̋Z�I�̍I�قȂǂ����Ă��A�����̉c�ׂ����ׂĘ��ՓI�Ɍ��n����Q2�o�łւƓ�����Burby�̏o�ŋƎ҂Ƃ��Ă̍����I���f�ɂ��Č������B
��Q��
�i�� �ޗǏ��q��w�y�����@���o �ǘY
�w�G�h���[�h�O���x�ɂ����������ʂƗ��j�L�q
�O�Y �_�j��
King Edward��Countess of Salisbury�ɉ����炵�A�ޏ��ɕs�`�����v����O���ƁA�ނ����ʌp�������咣����France�ɍs�����z�������������Ɏn�܂�S�N�푈�̌㔼�ō\������� King Edward III �́A���҂Ƃ��ċ��炳�ꐬ������e�q��`���A�̐����x�����Ă���悤�Ɏv����B�������Ȃ���A�����Ɛ푈���݂��̔�g�Ƃ��ėp����퓅��i�ɂ���āA������ʂ͐푈��ʂɉe����^���AKing Edward���]������푈�̐������������A�̐��ᔻ�̗v�f���Ɏ�������\����s�ށBCountess���^���鎍�ɂ����āA���ۂ̔��ȏ�ɔ�����������y���́A�푈�ɂ����ė��j���L�q����y���Ƃ��Ă̑����A���͎҂̐�������s��������̂Ƃ��ċ@�\����댯�����Î�������̂ƂȂ�B�ꌩ���������Ԃ����͕��s����r�������z���グ�Đ�������Ƃ���Countess �̑䎌�́A���Ƃ�����n�ɔ������W�J���鎩�R�Ƃ��Č��y�����퓬�����������菊�Ƃ���A�������푈�����o�����V������ے肷��B���ɂ���ē��̂��痣��邱�ƂŐ��ł̗E�C�������͂��̍��́A���̂ւ̎����������A���z�̋R�m�Ƃ��Ẳ��q�̋���Ȃ��댯�������ׂ肱�܂���B�c�s�ȕ��m�B���瓦���f�����O�̑䎌�́A�푈�̂��ߐ���s���Ɋׂ���England�����Î����A�퓬�ɏ�������England�̕��̖ʂ�z�N��������������B���n���ς��A���ɗ��j�I��T�����Ƃ�܂��A�����Ȃ������ɍs�����j�L�q�ɂ���āA���̌��͂��ł����͂ɐ��s�����푈���^�����A�̐�������}�����A�����������ӓI�����̕s��������\���������ʂ������̂Ƃ��đO�����̗����V�[���͋@�\����B�~�ɑł������̋��炪�������A�㔼�ł͂��̑��݂������Ă��܂������̂悤�Ɏv��������V�[���́A���͂ɑ��ď�ɕ��G�Ȏp�����Ƃ铯�����A�S�̂�ʂ��Ďx���鑕�u�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��咣�����B
Peele's David and Bethsabe —— 1590�N��̐��������߂��������� ���
George Peele��David and Bethsabe (1592-94)�́APeele�̃L�����A�̔ӔN�ɑn�삳�ꂽ�������ł���A�����w�T���G���L�x�Ɏ�ނ��Ă���_�ɓ���������B��s�������T�ς���Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�{���ɂ����ẮADavid�𒆐S�ɓW�J����鐭�����I�ȕ����ƁAAbsolon�i���ɂ��̉����̔��j�����ɕ`���o����镔����2�_�����ڂ��W�߂Ă����B�ތ��Ƃ̔�r�ΏƂ�ʂ��Ă��ڍׂɌ����Ă݂�Ȃ�APeele���Ӑ}�����쌀��̎�v�ȕύX�_�́ADavid�́ghumanization�h���ތ��ɂ�����v���O�}�e�B�b�N�Ȑ����ƂƂ��Ă̋@�\�̊��ƁA����ɔ����l�ԓI���������l���Ƃ��Ă̕ϗe�����łȂ��A��ΐ_���n�E�F�𒆐S�Ƃ�������̕���̐l�Ԓ��S�����ł���A�R�i�ߊ�Joab�̈�w�̗�O�Ȑ������ł���AAbsolon�̋@�\�g���3�_�ł��������Ƃ���������B������������ƕ��s����`�ŁAPeele�͍ތ��ł̒����ɂ킽�镨��̓W�J�����k���A�Z�����Ԍo�߂̒��Ńy���y�e�C�A���̋}�W�J�𑽗p���邱�ƂŁAAbsolon�̔g���ɕx���ꂪ��������`��David�̃v���b�g�ɔg�䂪�����A���ꂪDavid�̊���ɋN���������Ă䂭���{�����L���錀�I�\���Ƃ́A���̂悤�Ȃ��̂ƍl������̂ł���B
David and Bethsabe ���߂��鍡��̏d�v�ȓ_�́A���j�����ނ̗���̒��ŁA�{�����ǂ̂悤�Ɉʒu�t����̂��Ƃ��������j��̖��ł���B�A���O���J���E�`���[�`�̐��ɂ��A�J�g���b�N�I�������q�̈Ӗ��킳�ꂽ���j���̗}�����i�s�������A14���I�̌㔼�ȗ�200�N�ɂ킽���đ������Ă������j���ɂ܂��L�����A�C���O�����h�l�̃����^���e�B�ɐ[���Z�����Ă����B���̗��҂̂��߂������̒��ŁA�E�ƌ���ƂƂ��āA���j���ɑ��閯�O�̍������w���֔z������Ɠ����ɁA��w�ːl�Ƃ��Ă̌ÓT�I�f�{�ɗ��ł����ꂽ�ތ��̐l�ԉ����s�����ƂŁA�����炭Peele�́A�{����a���������̂ł���A���̌��̉����j�I�ʒu�����A���̂悤�ȂƂ���ɂ���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�i�� ������w�����@���� �a�b
���l�T���X�����ɂ����鉉�Z�ƌ�����
���� ����
���l�T���X�̎���A�����̓~���[�V�X�̊ϓ_����]������邱�Ƃ����������B���̍ہA�����͌����̉e�ł���A����̓I�ȋ��\�ł���Ƃ������ƁA�܂��A�����͌����𐳊m�ɉf���o�����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ύw�E����Ă���B�������A�����͕����Ŗ��҂ɂ���ĉ�������Ƃ����_�ɂ����Ă͎��̐��������̂ł���B����ɁA1600�N�O��̃C�M���X�����E�ł͌����ɂ�葦�������Z�����������悤�ɂȂ��Ă���B�����̉������߂��鑊�����鑤�ʂ��A�����̃C�M���X�ɂ����镑��\�ۂ�����t������Ƃ݂Ȃ��A�{���\�ł́AThe Spanish Tragedy (ST)�AA Midsummer Night�fs Dream (MND)�A�����Ė���Richard Burbage�ɂ��čl�@�����BST�̍Ō�̌������ɂ����āA����̊ϋq��Hieronimo�̑䎌�ɏ]���Č������\�Ƃ��Ċς����ŁAHoratio�̎��̂̌��i�ɂ���Ĉ����t�����Ă����B�ϋq�̈ӎ��ɂ����āA�����̎��̂͌����Љ�ɂ�������J���Y�̌��i�Əd�ˍ��킳���̂ł���A�����ł͖��҂̐g�̂̎��̐����ϋq��engagement�ݏo���Ă������ƂɂȂ�B�܂��AMND��Bottom�͌����ɑ��������Z�ւ̈ӗ~�������邪�A���ۂ̔ނ̉��Z�͑�U���Ȃ��̂ł���A�ނ�̌��͗\�z�Ƃ͗�����detachment�̌��ʂ������ϋq�ɂ����炷���ƂɂȂ�B�������A����ł́ABottom�Ƃ����f�l�o�D�����R�ɁABottom���̂܂܂炵��������{����b����̖��҂̋Z�ʂ������ɂ͓ǂݎ���̂ł���A���̉��Z�͂ɂ����Bottom�Ƃ����o��l����illusion�͐�������̂ł���B�Ō�ɁA Burbage�̎���o�ł��ꂽelegy�ł́A�ނ̉��Z�̔��^�����^����Ă���A�܂��A����̋��\���ƌ��������߂��鍬��������e�̏�����������B�����̋��\���������Ȃ�������������\�z���悤�Ƃ��鎎�݂������̕���\�ۂ̓����Ȃ̂ł���A�ϋq�ɂ�茻������^���镑������o���Ă�����ŁA���҂̐g�̂Ɖ��Z���d�v�ɂȂ��Ă����ƍl������B
�������R���[�̈��� —— Hamlet �ɂ����鋶�C�̊K�w���ƎЉ�s��
���� �_�j
Shakespeare�̎���ɂ����鐸�_�Ɛg�̂̃��J�j�Y���́A�����̉�X���z�肷����̂Ƃ͑傫���قȂ�A�Ƃ�킯���_�̕a�Ɋւ��ẮA�K���m�X��w�ȗ��̎l�̉t���_�Ɋ�Â����̉t�̃A���o�����X�ɂ���Đ�������̂ł��邩�A���邢�͈����ɂ���Ēm�o�𑀍삳��Ă����ԂƂ��Đ������ꂽ�B�������AClaudius��Hamlet�̋��C�͂��āA�u�����Ă��邱�Ƃ͂������������������Ă͂��邪�A���C�imadness�j�Ȃǂł͂Ȃ��B�S�ɂ킾���܂肪�����ă������R���[�����������Ă����ƒg�߂Ă���B�iIII.i.165-7�j�v�ƌ����悤�ɁA�������R���[���K���������C�ł������킯�ł͂Ȃ��B������̕����̑̉t���_���ɂ��ƁA�l�̉t�̈�Ƃ��Ă̍��_�`�inatural melancholy�j���D���ƂȂ�����Ԃ̂ق��ɁA�̉t���_�ɂ���Ă͐����̂��Ȃ��A�D���iadust�j�Ƃ������ۂɂ���Đ������������R���[�iunnatural melancholy�j�Ȃ���̂��z�肳��Ă����̂ł���B����������AShakespeare�̎���ɂ́A���͂��b����Ƃ������K���m�X��w�ł͑Ή��ł��Ȃ����C�Ƃ������̂����݉����Ă����̂��B���̂悤�ȋ��C�̑��w���́AHamlet �̌����E�ł́A���C��������Hamlet�ƌ����ɍ�������Ophelia�ɂ���Ĕ@���ɕ`���������Ă���Ƃ����邾�낤�B
�Љ�j�����ɂ��A���������̐��_�a���҂��������ŁA�̉t���_����肾���A�Ƃ�킯�m���K���̐l�X�̊Ԃŗ��s�����X�m�b�u�Ƃ��Ẵ������R���[�����݂��Ă������Ƃ��킩��BOphelia����������͕̂�����Ȃ����_�����ł���A�L���X�g���k�Ƃ��Ă̖��������ۂ���邻�̂��킭���̋����́A�����̂���̒Ǖ��Ƃ���������̑傫�ȎЉ�s����`���o�����AHamlet��������̂̓t�B�N�V�����Ƃ��Ắu���C�v�Ȃ̂�������Ȃ��BShakespeare�́A1590�N��ɂ������A�̊쌀�ɂ����Ċm�����ꂽ�X�e���I�^�C�v�Ƃ��Ẵ������R���[���͂��߂Ĕߌ��̕���ɂ̂����B�����Ă����ɂ͑̉t���_��̃������R���[����͑傫����E�����A�Љ�s���Ƃ��Ă̐��_�a�A�^�̋��C�����`�����Ă���B
��R��
�i�� �Ջ���w�y�����@�O�� �_�q
�n�b�s�[�G���h�� Tom Thumb —— Eliza Haywood��
The Opera of Operas �ɂ����錋����
���� �؎q
Eliza Haywood �ic.1693-1756�j ��The Opera of Operas; or Tom Thumb the Great (1733)�́AHenry Fielding�� Tom Thumb (1730)��Fielding���g������������ The Tragedy of Tragedies (1731)�̉���ł���BFielding�̌��삩��Haywood�̉���ւ̎�v�ȉ��ϓ_�Ƃ��ẮA33�Ȃ̉̂��lj�����o���b�h�E�I�y�������ꂽ���Ƃ��͂��߁A�n�b�s�[�G���h�̌������lj����ꂽ���Ƃ�A�����o��l���̈������g�傳��Ă��邱�Ƃ���������B�����̉��ϓ_�̂����A�{���\�ł̓n�b�s�[�G���h�̌����̒lj��Ɏ�Ƃ��Ē��ڂ��A���̌��̌����Ɋ_�Ԍ����錋���ρA�Ђ��Ă͓����̎Љ�̌����ςɂ��čl�@�����B�������߂���`�ʂɊւ��āA���̌��ł����Ƃ������ȓ_�́A��v�����o��l���������閧�����⊭�ʂ��l���͂��Ă����s���Ȃ����Ƃł���BFielding�ɂ�錴��ł͔ޏ������͖���Ŏh�E����邪�AHaywood�ɂ�����ł́A���̃q���C���������Ԃ点��v���b�g�ƂȂ��Ă���BHaywood�ɂ�����ɂ�����u�����Ԃ�v�̃v���b�g�́A�閧�����⊭�ʂ��߂���1730�N��̐��_�̓������@�m���A�ޏ��������Љ�ʔO����E���Ȃ������_�Ɋϋq�̏̎^���ނ��邽�߂ł͂Ȃ����B�Ȃ����������l�@�̉ߒ��ŁAHaywood�̉���̈ꃖ���O�ɏ������ꂽLewis Theobald�� The Fatal Secret (1733)�ɂ����錋�����߂���v���b�g�Ƃ̔�r�����݂��B����Theobald�̍�i�́A1614�N�ɏ������ꂽJohn Webster�� The Duchessof Malfi �̉���ł���BTheobald�ɂ�����ł̃q���C���̍s���́A����ł̌��ݕv�l�̂悤�ɁA�������x���߂���Љ�K�͂ɐ^�������璧�킷��̂ł͂Ȃ��A�ŏI�I�ɂ͎Љ�K�͂ɉ����悤�ɕ\�ۂ���Ă���B�����[���̂́ATheobald�ɂ�����ɂ����Ă��AHaywood�̌��Ɠ��l�ɁA�q���C�����u��Ղ̂悤�ɐ����Ԃ�v�_�ł���B1730�N��O���ɂ����āA�����Ԃ�Ƃ����u��Ձv�̃v���b�g�́A�����̎��Ȏ咣���Љ�ʔO�����E���Ȃ��悤�ɕ\�ۂ��悤�Ƃ��鉉���I�퓅��i�̂ЂƂł������̂ł͂Ȃ����B
Edward I —— ����������ꂽ���܃��I�m�[���̋؏����O�� ���q
George Peele��Edward I �ɂ�����c���Ńv���C�h�̍������I�m�[�����܂̃G�s�\�[�h�́A�j���ɔ�������肩�A�E�F�C���Y�����̖{�Ƃ̊֘A���ɖR�������Ƃ���A���炩�̗��R�ʼn��M���ꂽ���̂ƍl�����Ă����B�Ƃ�킯�A�A���}�_�C���̔��X�y�C�������A�X�y�C���o�g�̉��܂�c�Ȃ����ƌ��Ȃ���]�Ƃ������B�Ƃ��낪�A���܂̋؏����͓�����̃o���b�h�ł��ڍׂɉ̂��Ă���A�����ɂ͕K���������X�y�C�������ǂݎ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�o���b�h�́A�X�y�C�����܂́u�v���C�h�v�������ȊO�����̈ߕ�����p�i�ɚg���A�C���O�����h���ґ�ȑ嗤�����ɓł���Ȃ��悤�x������B����A���ɂ����Ă��A���܂̃v���C�h�́A�C���O�����h�Y�̗r�тւ̎̕��ƁA�O�����̍����ȕz�n�̕Ώd��ʂ��ĕ�������ɂ����B���Ȃ킿�A���I�m�|�����܂̋؏����ɂ́A16���I���̍��ۖf�Փs�s�����h���̐�����慎h����v�f���܂܂�Ă����ƍl������B
�܂��A���I�m�[�����܂̋؏����ɂ́A���̏]���ȍȃO���Z���_�̃p���f�B���Ӑ}����v�f���U������B�O���Z���_���A���̏����G���U�x�X��A�z�����郁�^�t�@�[�ł����������Ƃ܂���ƁA���܂̋؏����́A�{���ɂ����ĐV���ȈӖ���ттĂ���B���Ȃ킿�A���܂̓G�h���[�h�Q�����E�F�C���Y�ŏo�Y���A�u�E�F�C���Y���܂�̃E�F�C���Y���v���a�����邱�Ƃɂ���ė����̓������������邪�A�����ɂ�David Powel��The Historie of Cambria �P����j���̏����ւ����F�߂��A�����{���Ɠ��l�ɁA�G���U�x�X�������u���e���̉��ʌp���҂Ƃ��Đ�����������̂ł��邱�Ƃ��M����B���M���ꂽ�ƌ��Ȃ���郌�I�m�[�����܂̋؏����́A�ꌩ��O�I�Ȋϋq�����Ƀo���b�h�̃e�[�}��ڂ��������̂悤�Ɍ����āA���̂Ƃ���͒��q�̂Ȃ������ӔN�̎���ɗl�X�Ȋ܂݂����������ւ̏��������ł������ƍl������̂ł���B
�i�� ����w�����@���� ����
���蕨�ƌ��Â��Ǝ� —— �w�A���g�j�[�ƃN���I�p�g���x�ɂ����鑡�^�̖���k�� �ш�
Antony and Cleopatra �ɂ����āA�o��l���͕p�ɂɂ��̂�����A��������肷��B�������Ȃ���Marcel Mauss��Lewis Hyde�AGeorges Bataille�AJacques Derrida�Ȃǂɂ�鑡�^�_�����̑��l�Ȑ��ʂ�Shakespeare�����ɂ������Ύ�������Ă���ɂ�������炸�AAntony and Cleopatra �ɂ����鑡�^�̈Ӗ������ɒ��ڂ������͂͂܂����Ȃ��B�{���\�ɂ����ẮA�����������^�_�ɂ������v�Ȑ�s�������Q�Ƃ��A Antony and Cleopatra �ɂ����đ��^���W�F���_�[����A�@���A���Ȃǂ̍�i�̍������Ȃ����Ƃ����ɖ��ڂɗ��ݍ����Ă��邩���l�@�����B
Antony and Cleopatra �ɂ����āA�A���g�j�[�͋C�O�̗ǂ��Ƃ��������ߑト�[���b�p�ɂ����čł��̎^���ꂽ�����̈���ӂ�ɂ��Ȃ����l���Ƃ��ĕ`����Ă���B����ŃA���g�j�[�͏����ߑ���L�̑��^�ɂ����鎩�����̖��ɂ��Y�܂���Ă���B�A���g�j�[�͌ݏV�W�̒��ő��蕨�̎�Ƃ��Ăւ炤���Ƃ����ۂ��邪�A���������ւ荂�����^�̐��s�҂����Ƃ���p���䂦�ɔނ̑��^�͂����Εs�����ɏI���A�ŏI�I�ɂ̓A���g�j�[�̑��^�ɂ�����I�������[�}�ƃG�W�v�g�Ƃ̊Ԃ̐푈�Ƃ����d��Ȍ��ʂ������B
����ŃN���I�p�g���͑��^�ɂ����Ă��T�d�ł��邪�A����͑��^�ɂ����鎩�������N���I�p�g���̏����Ƃ��Ă̌��͂��ے����Ă��邱�ƂɋN�����Ă���B�N���I�p�g���͐����̏�ő��^�����p���邱�ƂŃG�W�v�g����낤�Ƃ��邪�A���ǃG�W�v�g�͔s�k���A�N���I�p�g���͎���������邽�߂Ɏ���I�ԁB�N���I�p�g���̎��E�̏�ʂɂ����Ă͑��^���L���X�g���ȑO�̌Ñ�̐_�X�ɑ���M�ƌ��т����Ă���A���̎��͌Ñ㐢�E�̏I�����ے�������قȗ��j����тт��o�����Ƃ��ĕ`���o����Ă���ƌ�����B
�n�̉ʂĂ���̗��K�҂Ɓw���F�j�X�̏��l�x
���R �M�V
�]����The Merchant of Venice �_�ł́A�n���C�f�Փs�sVenice�̍��ې����d������Ă����B������16���I�㔼�A�A�t���J�嗤���I��C���h�q�H��V�嗤�����ԑ吼�m�q�H�̔����ɂ��A�f�Ւn�}�͑傫�������������悤�Ƃ��Ă����BAntonio�̏��D���K���f�Ս`�́A�n���C���z���āABarbary�AMexico�Athe Indies�ւƍL�����Ă���A�V���Ȗf�Սq�H���m������悤�Ƃ��Ă������Ƃ��M����B�ނ���Shakespeare����i�̒��ɕ`���o���Ă���̂́A�Ȃ�������n�߂Ă���Venice�̌����ł͂Ȃ��A���E�f�Ղւ̔e����������England�̖�S�̓��e�ł��������Ƃ����������B
���������������̓��ɂ��鑼���ւ̗~�]�́A���̂܂ܑ��҂ɂ�鎩���ւ̗~�]��U���댯�������͂�ށB�n�̉ʂĂ���̗��K�҂ɂ��Portia�ւ̋����́A�܂���England�l���g�̃A�C�f���e�B�e�B�̊�@���ɕ`���o�����̂ł���AMorocco��Spain����̋����҂́A�吼�m�q�H�Ƃ����V���ȍ��ۖf�Ղւ̔����J����England�l���猩���A�����̕����ɑ��鑼�҂̋��Ђ�\���Ă���B�Ȃ��ł�Morocco�͕����I�ɉ������ꂽ�C�X�������Ƃł���ɂ�������炸�A�����̕��G�ȍ��ۏ�ɂ����ẮA��Spain�헪�̈�Ƃ��āA�d�v�ȓ��E�ƌ���������Ȃ����ł������B���������̂Ȃ��AEngland�l������̂����Ɉً��k�ɑ���A�Ë��Ɣ����A�M���Ɖ��^�A�����ėF�D�ƌy�̂Ƃ������������镡�G�Ȋ��������Ă������Ƃ͗e�Ղɐ����ł���̂ł���B
��i����́A���O���Ƃ̐V���ȊW�n�o�̂Ȃ��ŁA�l��A�@���A���ɑ���s���ɗh�ꓮ��England�̍����I�A�C�f���e�B�e�B�̖͍��̗l�q���M����B�吼�m�f�Ղ��������悤�Ƃ��鎞���ɂ����āAEngland�l�͎���̐V���Ȗ��������A���Ȑ��^���ʂ������Ƃ����߂��Ă����̂ł���B���̌����́A��������England�l�̓��I�����ɂЂƂ܂����g����^����`�Ŏ������邪�A�����ɁA�������England�l�̐S�ە��i��I�m�ɉf���o���A���Ȃ�s����P��o���đO�i�����铭�������Ă���B
��S��
�i�� ���S�����q��w�����@�r�� ����
Manga �ƃV�F�C�N�X�s�A���o��Ƃ�
�g�� �䂩��
2007�N�A�C�M���X�̏o�Ŏ�SelfMadeHero�Ђ���AManga Shakespeare �V���[�Y�̊��s���n�܂����B���{�ɋN�������}���K�ɗR������manga�Ƃ����\���}�̂�p���āA�C�M���X�ɍݏZ����A�[�e�B�X�g���A�C�M���X�̏o�ŎЂ���A�V�F�C�N�X�s�A�̖|�č�i���o�ł���Ƃ������Ԃ́A���������Ȃɂ������Ă���̂��낤���B�����A��ˎ����́w�o���p�C���x�i1966�j���V�F�C�N�X�s�A�́w���`���[�h�O���x�Ɓw�}�N�x�X�x�̖|�Ăł���Ƃ�����ɂ݂�悤�ɁA���{�ɂ̓}���K�ɂ��V�F�C�N�X�s�A�|�āE�p���f�B���������݂���B����㉉�ɂ��Ă����A���̂����Ђł̂艉�o�i���c���V�����j�́w���^���E�}�N�x�X�x�i2006�j��w�O�̐X�ɐ��ދS�x�i2007�j�́A�V�F�C�N�X�s�A�|�Ăł���Ɠ����ɁA�����Ƀ}���K�I�ȃe�C�X�g������߂Ă���A��҂ɂ͑O�q�̎�ˁw�o���p�C���x�ɗR������Ǝv����ӏ��������B�A�j���[�V�����ł́A�ߖ������V�s�s�ɕ�����ڂ��ւ��A�W�����G�b�g���v�����͂̔��������m�ɕϐg���������{�̃A�j���[�V��������`�[��GONZO�ɂ��w���~�IX�W�����G�b�g�x�i2007�j���A���{�����O�Řb����ĂB����ɂ́A��p�⒆���ŏo�ł��ꂽmanga�ŃV�F�C�N�X�s�A�����݂��A�����̈ꕔ�́A�؍��ŏo�ł��ꂽmanga�ł̒�����ւ̖|��ł���B���������ł���͂��̃V�F�C�N�X�s�A�ƁA�ዉ�����Ƃ���� manga�i�I�Ȃ��́j�Ƃ����f�B�A�E�~�b�N�X���A���E�K�͂̎s��ɗ��ʂ��Ă���Ƃ������̎��Ԃ́A�O���[�o�����ƃ��[�J�������A��������̏����ɂ��āA�������̂��Ƃ���肩���Ă���B�u�܂œǔj�@���A���v�i���{�A2008�j���A�i���Љ��n���w�̊g��ȂǁA������{��������a����F�Z�����f��������ł���Ƃ�����ȂǂɌ�����Ƃ���A����I�S�ɑΉ�����悤�Ɂu�V�F�C�N�X�s�A��n���I�ɉ���v�����ƕ]���ł����i�����Ȃ��Ȃ��B�o���Ƃ��O���[�o������������ȕ������{�ł���manga�ƃV�F�C�N�X�s�A�̊W�́A���ꂩ��ɒ��ڂ������B
�gA voucher stronger than ever law could make�h
—— �w�V���x�����x�ɂ����鏑�L��p�ƃ��f�B�A�E���e���V�[
�{�� �N��
Cymbeline �ł́A���L�̗͊w�Ƃ��ꂪ�\�ۂ���o�����⎖�ۂ��A�l�Ԃ̐g�̂Ƃ�����ވߑ��Ƃ̋��Ԃł��߂������B���҂̐g�̏�ŋL���̉��ߓ������s�Ȃ��A�n�쓖�����N�o�D�������Ă��������̋��E�N�ƓI�ȓ��̏�ŁA���̏�̏��L��p�̓lj�\�͂��K����W�F���_�[�ɂ���č��ى������B
Iachimo�ɂ���Ď�������A���̕M�ŏ����Ƃ߂�ꂽImogen�̓��̂��o�ϓI�@�I�p��ɂ����������A�ޏ��̏����I�g�̂͒j���I���L���͍�p�ɏ]�����闇�g�ɊҌ�����邪�A�ނ̏��L�s�ׂ͐g�̂��\�S�ɕ\���ł��Ȃ��Ƃ����\�ەs�\���ɂ�������B��������Iachimo�̏��q��lj�����\�́A���Ȃ킿���f�B�A�E���e���V�[�Ɋւ��₢����������Ă����B
�����������L��p�ƃ��f�B�A�E���e���V�[�Ƃ̍R�����t�s������̂��AImogen�ɂ��ϑ��ł���BImogen�ɂƂ��āA�������ʓI�ȏ��L��p�ɂ��L���A���̖\�͂ɑR����j���������A���U���̂��̂̉����I����ł��邪�䂦�ɁA���f�B�A�Ƃ��Ă̐g�̂̍\���ϊv�������炷�B�����Ă��������g�̓I�ϗe�����L��p�ւƖ|��̂��AImogen���E�����ƋU��̕�Posthumus�ɓ`���邽�߂ɕԑ������Pisanio�̎莆�Ȃ̂��BPisanio�͏��g�Ƃ����]���I�ȗ���䂦�ɗD�G�ȃ��f�B�A�lj�\�͂���i�Ƃ��A�K�����x�ɂ��\���I���ى��䂦�Ɂu�莆�v�̏��L��p�����V���ȊW���̎������J�����Ƃ��ł���B
�Ō��Guiderius��Cymbeline�̎��̑��q�ł��邱�Ƃ�������u�؋��v�ƂȂ�̂́A�ނ́u����Ƃ̃z�N���Ƃ����^�g�̐��v�ł���BImogen�́u�s��v�̏؋��Ƃ��ꂽ�u�����Ƃ̃z�N���v���u���_�v����u�^�g�̘I�v�Ƃ��������̏ے��ւƂӂ����ѓ]�L�����Ɠ����ɁA�ƕ������x���������钷�j�̌����������B�؋��Ƃ��Ă̒����ے��Ƃ��Ă̕W�L�ɜ��ӓI�ɕϊ�����邱�Ƃɂ���āA�e�q�A�Z���A�v�w�A�F�l�A��]�Ƃ����W�F���_�[�I�����K�w���������ׂĂ̓o��l�����ۂ��A�ِ�����`�Ɖƕ������x���猩����I�Șa���������炳���̂ł���B
�i�� �����w���_�����@�O�u ����
�ߑ㏉���C�M���X���s�L�ɂ����� cabinet of curiosities �I���_
���� �O�a�q
17���I���߂ɃC�M���X�l���s�҂ɂ�菑���ꂽ�嗤���s�L�́A�ٍ��̊X��`�����A���s�҂��̌��A���������Ƃ��镨����o�����Ƃ��̒n�Ɋւ���n������j�Ƃ�������ʓI�ȏ������X�Ɨ��ċL�q���Ă���B���̂悤�ȎG���ȋL�q�́A�ꌩ�����������ɓǎ҂ɏ���^���Ă���Ƒ������邪�A�{���\�́A������ɗ��s����cabinet of curiosities�Ƃ����R���N�V�����`�Ԃɂ����鎋�_���炱�������L�q��ϋɓI�ȋ�ԕ`�ʂ̎�@�Ƃ��đ����Ȃ����B��̓I�ɂ́AThomas Coryat�� Crudities (1611)�AFynes Moryson�� Itinerary (1617)�AWilliam Lithgow�� The Totall Discourse (1632)�̎O�̗��s�L�͂���Bcabinet of curiosities�́A�ߑ㏉���A���[���b�p�y�уC�M���X�Ő��������ꂽ�ł���A���̓����́A�l�H���Ǝ��R���̗������܂ޕ��L������̒��i�̕���ł���B�L���r�l�b�g���ɖ��W���ĕ��ׂ�ꂽ�l�X�Ȏ�ނ̃A�C�e���̏W�����Acabinet of curiosities�Ƃ�����̋��ق̋�Ԃ����グ�Ă���B�܂��A������C�M���X�ł́Acabinet�̌���^�C�g���ɔz���āA�L���r�l�b�g���̃A�C�e���̂悤�ɗl�X�ȕ�����T�O�ɂ��Ă̋L�q�ŏ����ߐs�����Acabinet of curiosities�ɂ������ԍ\�z�̎�@�����^�t�@�[�Ƃ��Ďg�p���鏑���������o�ł��ꂽ�B������̗��s�L�ɂ�����ٍ��̒n�̕`���������̂悤��cabinet of curiosities�Ɍ����鎋�_������߂���ƁA�G���ȋL�q�̈��́A�ٍ��̊X�𗷍s�L���ōČ�����A�C�e���̂悤�ɓ����A�s�����ȋL�q�̕���A�W���ɂ��A�S�̂Ƃ��Ĉ�̊X�̋�Ԃ�`���o�����Ƃɐ������Ă���Ɠǂݒ������Ƃ��o����B
���݂Ɩ@���ƁA�����ă}���N�X
���c ���j
�O���[�������b�W����� A Looking Glass for London and England (1588)�́A�������q�̔_����Ƃ��ĕs���ɒD���Ƃ鈫煂ȋ��݂�`���Ă���B�i�ׂɂȂ�Δ����ƕٌ�m�Ƀ��C���������čٔ��ɂ͏��B���̃v���b�g��17���I�̎ʎ��I�Ȍo�ϔƍߌ��̒�^�ɂȂ�A���Ƀ~�h���g�����ł���Ԃ��g���Ă���B���̂���A Trick to Catch the Old One�i1605�j�����삵���}�b�V���W���[��A New Way to Pay Old Debts�i1625�j�̎�l��Sir Giles Overreach�́A�ٌ�m�Ɣ������ق��Ĉ��������肩�����m�M�ƓI�Ȉ������Z�Ǝ҂ł���A���̏������Z���{�Ƃ̗��j�I�ʒu�Â������Ƃ����̂����AMichael Neill�́w���Y�}�錾�x�����p���Ĕނ��u�u���W���A�W�[�v�̐��I���݂ƌ��Ȃ��Ă���B(Putting History to the Question, 2000)
�������̋��݂��u�u���W���A�W�[�v�ł��蓾�Ȃ����́w���Y�}�錾�x�ɂ����G���Q���X���g�̒��ɂ���Ė��炩�ł���B�܂��A���̎ŋ��̐����N�i1625�j�Ɓw���Y�}�錾�x�i1848�j �̊Ԃ̓�S�N���鎞�ԓI�u������l����AOverreach ���u���W���A�W�[�́u���ҁv�Ƃ��鎖���������̌��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����ɔ��}���N�X�j�ς̗��j��(Peter Laslett, The World We Have Lost, 1983)����̑������ƒf���āANeill���g���w���Y�}�錾�x�̈��p������́A�d�v�ȕ��������f�폜����Ă���BNeill�����z�Ƃ�����K�ł͂Ȃ��b�I�T�[���B�X�ɂ���Đl�ԊW���������Ă�������ɂ��A���ۂɂ͕x�T�ȉƕ����ɂ��u�@���̌��e�ɕ����B���ꂽ�v��悪���݂��Ă���A�u���W���A�W�[�͂��̍����u���R����A�p�m�炸�́A���ڂȘI���ȍ��ɂ����������v�ɂ����Ȃ��Ƃ��镔�����Ӑ}�I�ɖ�������Ă���̂́A���j�������p�̃��[���������A�w��I�ɂ͋�����Ȃ��s�ׂł���B
�p�Ă̌����҂̃}���N�X��`���������͊T���Đł���A�V���j��`�E�V�}���N�X��`�̗���ɂ��_���ɂ͗��j�̌����������Ӑ}�I�Ȍ�ǂ������̂ŁA�ނ�̈��Ղȗ��j�������߂ɘf�킳��Ȃ��悤�ɂ���K�v������ƍl����B
�Z�~ �i �[ �i�v�|�j
�s�Z�~�i�[ 1 �t �G���U�x�X������̕��w�Ɛ������y
 |
|
�{�Z�~�i�[�ł́A�G���U�x�X������̕��w��i�\����Mary Stuart�̏��Y�Ȍ�̎��Ɖ����\�Ɠ�����̐������y�Ƃ̊ւ��ɂ��āA�c�_���W�J���ꂽ�B����ꂽ�e�[�}�͑���ɂ킽�邪�A�����Ė{�Z�~�i�[�̃L�[���[�h��������Ƃ���A(A) �����I�A���S���[�i�e�����o�[�ɋ��ʁj�A(B) Essex���i���c���A�g���A�y��A�{���A�����j�A(C) Elizabeth�\�ہi���c���A�c��A�����j�A(E) Mary Stuart�@�i���c���A�c��A�{���A�����j�A(D) Protestantism �i���c���A�{���j�A(E) Republicanism �i�g���A�����j�A(E) James VI�Ɖ��ʌp�����i�y��A�{���j�A�Ƃ��������ڂ��������邩�Ǝv���B���\��A�G���U�x�X������ɂ����錟�{�̖��A Lyly�̍�i�ɂ�����Elizabeth�ᔻ�̉\���ARepublicanism�̒�`�i�t���A�[����̎���j�A�����I�A���S���[�Ƒ�O�����AChettle��Essex�Ƃ̊W�Ȃǂɂ��ē��c���ꂽ�B���ɁA�u��O�����ɂ����āA�����I�A���S���[�́A�ϋq�ɂǂ̒��x�������ꂽ�̂��v�Ƃ����₢�́A����̉ۑ�ƂȂ����B����ꂽ���Ԃ̒��ŁA���푽�l�ȃe�[�}�����������߁A�ЂƂЂƂ̖��ɂ��Ė������ɏI������ʂ����������A�G���U�x�X������̕s���肩�_�C�i�~�b�N�ɗh�ꓮ�������Ƃ��ꂼ��̍�i�̍���ɉ������͂����ڂɘA������l�q���A�_�Ԍ��邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�e�����o�[�̔��\�̗v�|�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(1) ���c�� �uSpenser��Essex�FThe Faerie Queene V, VI �𒆐S�Ɂv
Leicester��Sidney�Ȃ��セ�̌�p�҂Ɩڂ��ꂽEssex�́A�����ł̌p���I������v�ƊO���ł̐ϋɓI�Ȕ��J�g���b�N��������߂�v���e�X�^���g���������߂��Ă����B
The Faerie Queene �܊� �i1596�j ��Mercilla�̋{��̃G�s�\�[�h��Bourbon�̋~���́A���j�I�ɂ̓��A���[�̏��Y�A��n�����ւ�Leicester�̔h���AIreland�ւ�Grey�̔h���AEssex��Henry IV�x����\�����̂Ƃ����B���ߐ[���Ə^���ꂽ�����̋{�a�Œ��ɐ��B�t���ɂ��ꂽ���l�̎p�́A�o�ł̌��{�Ə�����\�����̂Ǝ���B�����������`�̎��ɕ\���ɂ��������ւ̕s���͋��ӂƂ����`�ŕ\����A�����Elizabeth�̐������͏o�ł���Ȃ�����The Mutabilitie Cantos�ɂȂ���B
����̓G�Ǝ�����ԂƂ������B�̕ς��s�������v���̒��ŁASpenser�̓v���e�X�^���e�B�Y�����̂���i���������BDavid Norbrook�́A�܊��S�̂��v���e�X�^���g�I���E�ς�\���AEssex�Ƃ��̃T�[�N���ւ̌ە����Ǝw�E���Ă���BCollin Burrow�̎w�E�̂悤�ɁASpenser�̗��j�I���ӂ͔ނ̐��E��ς���悤�ɈӐ}����Ă��āA�ނ�1570�N��㔼����80�N�㏉�߂̐ϋɓI�ȃv���e�X�^���e�B�Y���̉���ւ̔M�����D��������1590�N��ɏ������̂ł͂Ȃ����낤���B
(2) �c�� �uEndimion �Ɍ�����Elizabeth �\�ہv
John Lyly��Endimion (1588) ���A���S���[�ł���ACynthia�͌��̏��_�Ƃ���Elizabeth�̕\�ۂł��邱�Ƃ͖����ł���BEndimion�����ɍ���A���@�Ŗ��炳���؏�������́AAlciati�̃G���u�����ʂ�A�g���Ⴂ�̗����|�߃v���g�j�b�N�Ȉ�����������BEumenides����̐������G�s�\�[�h�́A�F��̗D�ʐ������łȂ��ACynthia�̈ڂ�C �iinconstant�j �ւٌ̕�Ƃ��āA�����������錎�͏�Ɋۂ����Ƃ���ASemper Eadem�����b�g�[�Ƃ���Elizabeth��i�삵���BCynthia�̗��GTellus��Mary Stuart�ƌ���ꍇ�AEndimion��Leicester���Ƃ���A�閧�����������̂�Elizabeth�ւ̋���������B�����߂Ƃ������ڂ������ALyly�̃p�g����������Oxford�����Ƃ���A�J�g���b�N�M���̂ĂĂ������ɏ]���Ƃ�����������i����藧�Ăƍl������B�N�w��Gyptes�̌�����ALyly��Elizabeth�Ɏd�������ӎu��`���Ȃ���AEndimion�̖��ł͍��ʂ̎҂����X�̎҂ɖ���_���錾�����J��Ԃ��A���̏��ł�Endimion�̌��g���䂪�g��栂���BLyly�͖����Ȑ����I�X�^���X�͔������A�����̉��߂��\�ɂ���悤�Ȑl���������o�����B
(3) �g�� �u�G���U�x�X������ɂ����鋤�a��`�v�z �\ Julius Caesar�v
�{���\�ł́AShakespeare��Julius Caesar (1599) �ɂ����āA���a�����[�}�̏I�����E��`�������ƂƁA�G���U�x�X������ɍs��ꂽ���a��`�C�f�I���M�[�ɑ��鐭�{�̒e���Ƃ̘A�ւ��w�E���A��i����Shakespeare�̃G���U�x�X�������ɑ��靈�����Î�����Ă��邱�Ƃ��w�E�����B����Shakespeare�Ɠ�����̋��a��`�C�f�I���M�[����������Ƃ�����������A����ɖ\�N�E�Q�ȂNj��a��`�C�f�I���M�[����������悤�ȏ����������ɂ���ȂǁAJulius Caesar �����M�E�㉉���ꂽ1599�N���́A���{�̎���肪���i�����ꂽ�����������B���̐������E�́AJulius Caesar �ŕ`�ʂ���鐢�E�Ɠ������A���a��`�C�f�I���M�[�ɑ��Ĕ����z�I�ȏ�Ԃɂ������ƌ�����B���̗ގ����́AShakespeare�����̎����ɌÑネ�[�}��ɂ���Julius Caesar �����M�����Ӑ}���𖾂���q���g���������Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
(4) �y�� �uRichard II �ɋ����ߖ����ւ̌x���v
Shakespeare���ARichard II (1595)�Ƃ�����ނ��A���ɉ���ވʂ�����Ƃ�����_�ɂ̂ݒ��ڂ��W�܂��ނ����グ���̂́A�������ւ̔����S��������J��ߖ����ւ̌x���S����ł͂Ȃ��������Ǝv���鑤�ʂ�����B��p�Җ��ɗh���England�ɉ����āASpain��Infanta�𐄂���h��James VI��]�ވ�h�̂��ꂼ�ꂪ�s�����Η����ւ̔�排����ɖڂ�ʂ��ƁA���O���V���ɑ��������̂͊��҂ł͂Ȃ��s���ł������ƍl������B�ނ�́AEngland���䂪�����舕�����\�N�a���̉\����A������R��ׂ��葱����Elizabeth�̌�p�҂ƂȂ��Ă��A�������p�������咣�������邱�ƂŁA�����ɍ�����������\����ے�o�����ɂ����ł��낤�BRichard II �ō��グ����A�j���������i�i�̏オ�����\�NRichard���ƁA�����œ|����������Ȍ�p�҂ɂ͂Ȃ�Ȃ�Bolingbroke�������ʌp���������鑈���́A�m�肵�Ȃ����������̎p�ɋ����A�p����̍������Ă���A�G���U�x�X������̕����̒��ł����傫�ȏՌ���^������̂ł͂Ȃ������낤���B
(5) �{�� �uHenry Chettle��Protestaitism �\ The Downfall and Death of Robert, Earl of Huntington, Sir Thomas Wyatt ���߂����āv
Henry Chettle�́AAnthony Munday�Ƃ̋���The Death of Robert, Earl of Huntington (1598)�AThomas Dekker���Ƃ̋���Sir Thomas Wyatt (1602)�Ȃǂ̍�i�ŁA���J�\���b�N�E���X�e���A�[�g�Ƃ����ԓx���Î����Ă��邪�A�Z�~�i�[�ł͏�L��i�ɂ�����Chettle�̂������������E�@���I������_�����BThe Death �́AThe Downfall �̑��҂ŁA���̓��i�̓��r���t�b�h���Ƃ݂Ȃ���Ă��邪�AThe Death �́A���X��Robert�iRobin�j�̎���`���A�\�NJohn��Matilda�iMarian�j�ւ̗~�]�𒆐S�I�v���b�g�Ƃ��邱�Ƃ���A�W���������̌n���ƌ����悤�B����i�́A�J�\���b�N�̐��E�҂̕��s��ʂ��A�J�\���b�N��ᔻ���Ă���悤�Ɏv����B�Ƃ�킯The Death ��John�����E�҂����AMatilda�悤�Ƃ��鉺��́AJohn�ƃJ�\���b�N���k�Ƃ̖��ڂȊW�������Ƌ��ɁA���ɂ�鐭���Ə@���̎x�z���������Ƃ���A�����C���O�����h����p�Ҍ���ʂł�����James�ɏd�˂���ƍl������BSir Thomas Wyatt �ł́A�v���e�X�^���g�̌R�l��Mary Tudor��Philip of Spain�Ƃ̌����ɔ�����Wyatt���AMary�ɑ��������N�������A���s�����Y�����B�����Ύw�E����Ă����悤��Wyatt��Essex���Əd�˂���ł��낤���A�����ł͂���ɁA�ꐧ�I�Ŗ����߂ŃX�y�C���ƌ��т��J�\���b�N�̌N��Mary�̕`�ʂɁA������p�Ҍ���James�ɑ���뜜���Î�����Ă���ƍl������B
(6) ���� �uDavid and Bethsabe �l �\ Peele��Essex�v
George Peele, David and Bethsabe (1593-4����)�́ADavid=Elizabeth���Î������Ȃ���AWeak Queen�Ƃ��Ă�Elizabeth�ɑ���ᔻ�����Ă���BDavid�̕\�ۂɉ����ᔻ�����̂��邱�̎�@�́A�������{�ɕs��������M���������A�����"discontent"��\������ۂɗp�����퓅��i�ł������BDavid and Bethsabe �̎��M���A���炭Peele�́uEssex�ɂ��Elizabeth�iWeak Queen�j �ᔻ�v�Ƃ��������𑊓��ӎ����Ă����Ɛ��肳���B����̔��\�ł́APeele��Essex��personal connection���l�@���Ȃ���A���̍�i�ɂ�����Elizabeth�ᔻ�Ƃ����e�[�}���A����Essex circle�̊Ԃŗ��z���Ă���Neostoicism�Ƃ̊֘A����l�@�����B
�i���ӁF���� �B�Y�j
�s�Z�~�i�[ 2 �t �V�F�C�N�X�s�A�㉉�E�㉉�����̍�
 |
|
�V�F�C�N�X�s�A�㉉�E�㉉�����̍�
�V�F�C�N�X�s�A�����㉉���ꂽ���̂Ƃ��Č�������悤�ɂȂ��Ă��łɔ����I���o�Ƃ��Ƃ��Ă���B�����̏㉉�����͌��]��ʐ^�Ȃǂ̌�����ʂ��ĉߋ��̏㉉���L�^�Ƃ��Ďc�����Ƃɂ������B�������Ȃ���A�ŋ߂ł́A�L�^�Ƃ��Ă̏㉉�����͎p�������A�|�X�g�E�R���j�A���Y�����_�A�O���[�o�����_�A�p�t�H�[�}���X���_�Ȃǂ����p�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
�܂��A�p���̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�������[�J���ȏ㉉�ɏœ_�����Ă��Ă���̂��ŋ߂̓����ł���B�p�����l�V�F�C�N�X�s�A��u�{��v�p���̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�������Ђ���̂��悤�Ƃ��铮���������ɂȂ�A��p�ꌗ�ɂ�����V�F�C�N�X�s�A�㉉�ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B�������A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉����邳���ɁA�p�Č��̏㉉�����̃p���_�C�������̂܂܉��p���Ă��悢�̂��낤���B���������l����ׂ����͑��X����B
�{�Z�~�i�[�ł͍����O�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�̌��݂̏��m�F���������ŁA�㉉�����̃p���_�C���̍��A����̕����������ɂ߂Ă������݂Ƃ��Ċ�悵�����̂ł���B���ʁA���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����V���ȃp���_�C����T��D�@�ƂȂ����B
�{�Z�~�i�[�ł́A�ȉ��̎O�_�ɗ��ӂ��āA�Z�~�i�[�O�̏����A����ѓ����̔��\���s�����B���ɁA�V�F�C�N�X�s�A�㉉�������ЂƂ̊w��̌n�Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃɏd�_��u�����B���̂��߂ɁA�p�Č��̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����̗��j�A�p�t�H�[�}���X�E�X�^�f�B�[�Y�̓����A�����O�̏㉉�j�ȂǁA�e�����o�[�����S���ă}�b�s���O���s�����B�����̃p���_�C����㉉�j�̊m�F�͔O����ɍs��������ł���B�����āA�㉉�����A�㉉�j�S�̗̂���������o�[�S�����c�����������ŁA�e�X�̔��\�ɗՂB�����̃p���_�C����㉉�j���m�F�����Ƃ́A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�̌�����͍���������ƂȂ����悤�Ɏv���B���ɁA�㉉�Ɋւ���]���̔��\�͌ʂ̏㉉���Љ��P�[�X�E�X�^�f�B�[�ɂȂ�X�����������A����̃Z�~�i�[�̔��\�ł͌X�̏㉉�����炩�̃R���e�N�X�g�Ɗ֘A�����čl�@���邱�Ƃɏd�_��u�����B�����āA��O�ɁA�����̃p���_�C���A�������́A�V���ȃp���_�C�������p����ꍇ�A��̓I�ȏ㉉�������Č�����Ꭶ���邱�Ƃ����݂�����ł���B
�É��͓��{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�̈ꎖ��Ƃ��āA吐�K�Y�̏����o�ƂȂ�̕���l���̖|�Č��wNINAGAWA�\���x�i2005�A2007�N�����j�ɂ��āA����w�\���x�Ƃ̎�v�ȑ���_�܂��Ȃ���A����Ɖ��o�̎��Ԃ��������B�̕���̕���A�ߑ��≉�Z�A�����ȂǓ`���I�ȗl������荞�݁A���̗l�������ꂽ����ɒʒႷ�鎋�o�I�������ł��o��吐쉉�o�́A����ɐ�����j�ՓI�쌀��������荞��ŁA�V�@����ł��o�����������|�ĉ̕���Ƃ��ĕ]�������B
�����́A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�j�̃R���e�N�X�g�ɂ����Čʂ̏㉉���c�_���鎎�݂Ƃ��āA�̕���wNINAGAWA�\���x�ɂ��āA�㉉�j�Ƃ����c���ƃC���^�[�J���`�������e�B�Ƃ��������̑o���̊ϓ_����l�@�����B��̓I�ɂ́A�`���|�\�́u�l���v����{�I���o�v�f����i�֑g�ݍ��ގ�@����吐��i���O�^�C�v�ɕ����A���ꂼ��̃X�^�C���̈Ⴂ�Ǝ�@�̕ω��𑣂����v���͂��A�wNINAGAWA�\���x�Ɏ���吐�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�j���������B
�����́A�wNINAGAWA�\���x�̊ϋq���A�㉉�̂ǂ̗v�f���D�܂������̂Ɖ��߂��������l�@�����B���̉ߒ��ɂ͊ϋq�_�������ۂ̖�肪�������B�ߔN�C���^�[�l�b�g��ňӌ������\�����ʊϋq���������Ă��邪�A���̈ӌ��͎��ؐ��Ȍ��ɂǂ̒��x�L�����Ƃ����_�ł���B������l�����������ł��A���Ƃ��ʊϋq�̈ӌ��S�̂���A���̖|�Č��ɑ���ϋq�̎������f����B����́A����͏㉉�̈�v�f�ɉ߂����A���̏㉉���̕����i�Ƃ��Đ����������ǂ������ϋq�ɂƂ��čł��d�v�ł������Ƃ������Ƃł���B
��{�́A�j���̐������������u�ِ��z���̐g�́v�̏㉉�ɂ����������A���{�ɂ����鏗���z���̗Ⴉ��_�����B�̕���Łw�\���x�ł́A�ِ����̔��i�P�^���q�ۂ��j���̐g�̂��Ɍ�����Ƃ����̕���ɂ����ł��Ȃ���@��p���邪�A���ҋe�V���̐g�̂���������邠�܂�A���̐g�̂��k������Ă���B�����ۂ��A������吐�K�Y���o�́u�I�[�����[���v�V���[�Y�ł́A�Ⴂ�j�D���������Ɩ��҂̐g�̂̓�w���Ɍ����āA�W�F���_�[�E�A�C�f���e�B�e�B�̂��߂Ȃ����͓I�Ȑg�̂��\�z���Ă���B
�K�����A�́A���{�̖|��̖�����肠�����B����20�N�̊ԂɁA�����a�q�Ȃǂ̖|��҂ɂ���āA�����قǑ����̐V�����V�F�C�N�X�s�A�|���\����Ă���B���{�ɂ�����V�F�C�N�X�s�A�Ƃ����c�_�ɂ����ẮA�㉉�Ɋւ��錤�����|��_�����d�������悤�ɂȂ��Ă͂��邪�A�V��A�Ƃ��ɕ�������̖�̕��͂̏d�v�����K�����A�͎咣�����B
�G�O�����g���́A�p�t�H�[�}���X�E�X�^�f�B�[�Y�iPS�j�̔��W�o�߂��}�b�s���O���A�O���[�o�����^���[�J���������V�F�C�N�X�s�A��i�̏㉉���A���܂��ɉ��Ē��S�A���������PS�̃p���_�C����p���ēǂ݉����ۂ̖��_�܂����B���̂����ŋ{�������o�w�N�E�i�E�J�Ŗ����\�ȃI�Z���[�x�ƃC�E�����e�N���o�w�����\�I�Z���[�x���ɁA�C���^�[�J���`�������Y�����_������ꂪ���ȃj���Η�����j���A�V�F�C�N�X�s�A�㉉��PS���抪���p���_�C���𐼂̎��_����^�ւƋO���C�����邱�Ƃ����݂��B
���т́A�p�Č��̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����̃p���_�C���܂��������ŁA���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����p���_�C���̖͍������݂��B�I�c�F�G���o�w�~����x���ɂƂ�A�C���^�[�J���`�������e�B�̎��_�A W.B. Worthen������h���}�e�B�b�N�E�p�t�H�[�}�e�B���B�e�B�̎��_����㉉�͂����B�܂��A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����ہA�㉉�ƎЉ�I�E�����I�R���e�N�X�g�Ƃ̑������l�@����K�v�������邱�Ƃ��w�E�����B
�X�̔��\�ɑ����f�B�X�J�b�V�����ł́A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����̐V���ȃp���_�C���̉\���ɂ��ē��_�����B�����̐��m�̗��_����{�̏㉉�ɓ��Ă͂߂�ȊO�ɁA���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�������@�͂��肦��̂��\����̃Z�~�i�[�̎��ɂ��ċc�_�͐i��ł������B���̖��ɑ��āA���m�̃p���_�C�������p���ē��{�Ǝ��̃p���_�C������邱�Ƃ͂ł���̂ł͂Ȃ��̂��A�܂��A�܂������[��������グ��͕̂s�\�ł��邵�A�s�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ̈ӌ������킳�ꂽ�B�����̃p���_�C���W�����A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�̌ŗL����Nj����ׂ��Ƃ̌��_�������o���ꂽ���A����A�������ׂ��_�Ƃ��ċ�̓I�Ɉȉ��̓_���w�E���ꂽ�B
���ɁA�|��A�|�Ẵe�N�X�g�̖������[���l����ׂ��ł���B�|��ƌ��T�Ƃ̊W�A�u�V�F�C�N�X�s�A�v���ЂƂ̊W�A�㉉�E���Z�Ɩ|��̊W�ɂ��č��コ��Ȃ錟�����K�v�ł���B�|��͓��{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�Ɏ��R��^����̂��낤���B�܂��A�|��Ɠ��{�̌���A�����A�Љ�Ƃ̊W�ɂ��Ă��l����ׂ��ł���B���Ƃ��A���{�̖|��͓��{�̕����f���Ă���̂��낤���B
���ɁA���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�Ɠ`�������̗Z���̖����ǂ��Ƃ炦��̂��B�`�������ƌ���̏㉉�̊W�ɂ��Ă̍l�@�́A�p�Č��̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����ɂ͂قƂ�ǂ݂��Ȃ����̂ł���B�G�O�����g���́A�`���ƃR���e���|�����[�̊W��C���^�[�J���`�������e�B�̖��͉��o�ƂȂǎ��H�̏�Ŋ���l�����̂������ł͂���ɐ[���c�_���i��ł���Ǝw�E���A��X�����҂͔ނ�̐���������ׂ��ł���Ƒi�����B
�����āA��O�ɁA�㉉�ƎЉ�I�E�����I�R���e�N�X�g�Ƃ̑����̌����ł���B����͋c�_�Ƃ��ē�����A��͂�A�����I�E�Љ�I�R���e�N�X�g�Ɠ��{�̏㉉���֘A�����Č��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���Ƃ��A�Ȃ��A����قǃV�F�C�N�X�s�A�����{�ŏ㉉�����̂��H�Ȃ��A���A�̕���V�F�C�N�X�s�A�Ȃ̂��H�\�V�F�C�N�X�s�A�Ȃ̂��H�`���|�\�ɗ����Ԃ�̂͂Ȃ����H�o�u���̕���A�o�ϕs���A�i���Љ�A�O���[�o�����Љ�A�|�b�v�J���`���[�̗����ȂǂƊ֘A�����Ę_����ׂ��Ȃ̂��낤���B����Ɗ֘A���Ď�e��ϋq�_�̖�����肠����ׂ��ł���B���Ƃ��A吐�K�Y���o�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�̗��s�����ꍇ�ɁA�ϋq�_���O���Č�邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��낤���B
�܂��A�X�̏㉉���P�[�X�E�X�^�f�B�[�Ƃ��Ē���̂ł͂Ȃ��A���炩�̃R���e�N�X�g�̂Ȃ��Ɉʒu�Â��Č��d�v�����Ċm�F���ׂ��ł���B�㉉�j�A�ق��̌��㌀�A�܂��A�ق��̃A�W�A�̏㉉�Ƃ̗��݂Ō�������͍̂���A�K�g�ł��낤�B
�f�B�X�J�b�V�����̌�A�t���A����l�X�Ȃ��ӌ��������������B�܂��A���{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����ۂɁA�����̊ϋq�������_��_����ׂ��ł���Ƃ̂��ӌ��������������B�܂��A���{�Ǝ��̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����̉\����T�����鎎�݂́A�G�X�m�Z���g���V�Y���Ɋׂ�댯�����������Ƃ��w�E���Ă��������������҂������B�����Ƃ��ł���B�����ۂ��A�`���|�\�ƃV�F�C�N�X�s�A�㉉�̗Z�����l����ۂɁA�V�F�C�N�X�s�A�����҂����ł͂Ȃ��A�`���|�\�����ґ�����̈ӌ����������Ƃ悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ̗L�v�Ȓ�Ă������������B
����̃Z�~�i�[�͏����i�K����`�[�����[�N���ǂ��A�����̃p���_�C����㉉�j�܂���Ƃ����c��ȍ�Ƃ����Ȃ��������ł͂Ȃ��A���[����̓��_�A�ł����킹�ł̓��_�A���ȉ�ł̊��k���������Ȃ��̂ł������B����́A����̊e�X�̔��\�W�����A�㉉�j��㉉�����̃}�b�s���O�A�ڍׂȎQ�l�������������_�W���o�ł���\��ł���B�������̎��݂����{�̃V�F�C�N�X�s�A�㉉�����p���_�C���͍��ւ̋M�d�Ȉ���ƂȂ邱�Ƃ�]��ŕ��ݑ��������ł���B
�i���ӁF���т�����j
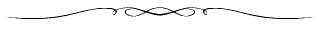
♠ PDF�t�@�C���������ɂȂ肽�����́A������ ��
