日本シェイクスピア協会会報
Shakespeare News
Vol. 47 No. 2
December 2007
学 会 特 集 号
| 第46回シェイクスピア学会を終えて | 楠 明子 |
学 会 特 集
パネル・ディスカッション(要旨)
Opening up Dialogues on Shakespeare in Asia:
Towards a Comparative Study of Shakespeare Performance in Asia
研究発表(要旨)
貧しい女性たちの結婚——『お気に召すまま』と結婚・離婚制度
Cleopatraを「勝利者」とするドラマツルギー ——エコフェミニズムの視点から読むAntony and Cleopatra ——
Shakespeare and the Idea of the Future
The “Demon” of Capital: Timon of Athens in Meiji Japan
King Lear あるいはエクソシズムの劇場 ——初期近代イングランドにおけるメランコリーと浮浪者問題——
『テンペスト』における衣服
The Court Secret の三つの異なるテキスト
A tragedy of false accusation: What makes Othello mistake Desdemona for ‘that cunning whore of Venice’?
1H6 に於ける英雄Talbot誕生の過程を探る
シェイクスピアの第1四部作 ——政治力学を見据えて
Henry V における軍人の表象
サミュエル・ダニエルとシェイクスピア ——欽定『説教集』と『ヘンリー四世・第二部』とをめぐって——
『ヴェニスの商人』再話物語におけるシャイロックの復讐の描かれ方
『夏の夜の夢』のメタモルフォシス ——王政復古期におけるセミ・オペラと『妖精の女王』(1692) ——
シェイクスピアと自由民権運動 ——北村透谷の場合——
セミナー(要旨)
Opening up Dialogues on Shakespeare in Asia:
Towards a Comparative Study of Shakespeare Performance in Asia
貧しい女性たちの結婚——『お気に召すまま』と結婚・離婚制度
Cleopatraを「勝利者」とするドラマツルギー ——エコフェミニズムの視点から読むAntony and Cleopatra ——
Shakespeare and the Idea of the Future
The “Demon” of Capital: Timon of Athens in Meiji Japan
King Lear あるいはエクソシズムの劇場 ——初期近代イングランドにおけるメランコリーと浮浪者問題——
『テンペスト』における衣服
The Court Secret の三つの異なるテキスト
A tragedy of false accusation: What makes Othello mistake Desdemona for ‘that cunning whore of Venice’?
1H6 に於ける英雄Talbot誕生の過程を探る
シェイクスピアの第1四部作 ——政治力学を見据えて
Henry V における軍人の表象
サミュエル・ダニエルとシェイクスピア ——欽定『説教集』と『ヘンリー四世・第二部』とをめぐって——
『ヴェニスの商人』再話物語におけるシャイロックの復讐の描かれ方
『夏の夜の夢』のメタモルフォシス ——王政復古期におけるセミ・オペラと『妖精の女王』(1692) ——
シェイクスピアと自由民権運動 ——北村透谷の場合——
第46回シェイクスピア学会を終えて楠 明子
第46回シェイクスピア学会は10月6日・7日の連休に、日本のシェイクスピア研究発祥の地ともいえる早稲田大学で開催された。早稲田大学は今年創立125周年を迎えた。学内で多くの記念行事が催されているなか、シェイクスピア学会の開催校をお引き受けくださった大学側のご厚意に心より御礼申し上げたい。大学の関係者や学生さんたちが一丸となって学会担当委員を支援してくださり、また連休であるにも拘らず多くの会員が参加してくださったおかげで、学会は成功裡に終わった。皆様のご協力に深く感謝する。
学会時の挨拶でも申し上げたが、現在の日本シェイクスピア協会の前身は1930年4月23日、市河三喜教授を会長に、そして坪内逍遥博士を名誉会長に発足した。その1年半前に早稲田大学では、坪内博士の「シェークスピヤ全集」全40巻の翻訳の完成を記念して、演劇博物館が創設されている。その後、世界の政治情勢が緊迫し、第二次世界大戦の勃発で協会の活動は中断されたが、1960年に三神勲教授と小津次郎教授を中心に協会の再発足が話し合われ、両教授はまず早稲田大学の飯島小平教授を演劇博物館に訪ねている。この年の12月に第一回世話人会が大隈会館で開かれ、1961年4月には現在の日本シェイクスピア協会は正式な活動を始めた。それから約46年後、早稲田大学で日本中のシェイクスピア研究者が一堂に会する機会を得たことは誠に感慨深い。
今回の学会の特徴は、海外からたくさんのシェイクスピア研究者や協会会員が参加してくださったことである。特に学会2日目には、アジアにおけるシェイクスピア上演をテーマとするパネルディスカッションが行なわれた。シンガポール、台湾、日本、米国で活躍しているさまざまな国籍のシェイクスピア研究者をパネリストに迎え、アジアにおけるシェイクスピア劇の翻案や上演が、英米の上演に対する「他者」の立場ではなく、世界のコミュニケーションの場となるための可能性が模索された。優秀な若手アジア人研究者や、日本におけるシェイクスピア上演を深く理解しているオーストラリア人学者による発表は、シェイクスピアが国境、民族、宗教の違いを超越する大きな力を私たちに与えてくれることを再認識させてくれた。
シェイクスピアを通してのコミュニケーションは、今や劇場やアカデミックな分野だけに限られない。イギリスでは、シェイクスピアの言葉のもつ力がビジネスプレゼンテーション等に利用されだしているそうである。この企画を始めたのは、なんとローレンス・オリヴィエとヴィヴィアン・リーの息子であるリチャード・オリヴィエの所有する会社であるとのこと。最近ではシェイクスピア学者が企業に依頼されて、作品のなかで描かれる「力」のメカニズムを講演しに行く機会が増えているのだそうだ。シェイクスピア劇のもつ国籍や文化、そして時代の違いも超えさせてくれる力が、混迷を極める現在の世界を少しでも平和に導く役割を担ってくれないものかと願うのは、私だけが抱く幻想であろうか。
第46回 シ ェ イ ク ス ピ ア 学 会 報 告
2007年10月6日(土)・7日(日)
会 場: 早稲田大学文学部(戸山)キャンパス
パネル・ディスカッション (要旨)
Opening up Dialogues on Shakespeares in Asia:
Towards a Comparative Study of Shakespeare Performance in Asia
 |
|
本パネル・ディスカッションの主な目的は、アジアで上演されるシェイクスピアの舞台について、個々のパネリストが研究発表を行うと共に、他の研究者が取り上げた作品について意見交換をすることを通して研究者間の対話の可能性を考えることにあった。当日は、海外より4人の研究者を招き、台湾、日本、シンガポールのシェイクスピアの舞台について、ビデオ映像を交えて発表を行った。残念ながら司会の不手際のため発表の時間が足りなくなり、発表者間の意見交換およびフロアの先生方との質疑応答の時間がなくなってしまったが、パネル終了後に、関心のある方々とパネル参加者とが直接意見交換をする時間が少しできたのは幸いであった。また当日、大変興味深い視聴覚資料を見ることができたのは、発表者の希望を聞きながら機器の操作等をしてくださった早稲田大学院生の方々のおかげである。この場を借りてお礼申し上げたい。以下に参加者から寄せられた発表要旨を掲げる。
“Romeo and Juliet EnCamped: Two Taiwanese Examples”
This essay examines two Taiwanese productions/adaptations of Romeo and Juliet—Huang Xianglian’s solo Romeo and Juliet and the Golden Bough Theatre’s Yu-Mi and Tien-Lai, both premiering in 2004. While loyalty is often an issue in producing/adapting Shakespeare, these two productions profess localism, anachronism, and eclecticism. Turning Shakespeare’s tragedy into near farce, the two productions can be analyzed in terms of Camp, the aesthetic famously described by Susan Sontag. Significantly, characteristics of the Camp style —“ostentatious, exaggerated, affected, theatrical, effeminate or homosexual” (OED)—have long existed in traditional Taiwanese theatre since the time of Japanese colonization. Chiang Kai-shek’s “Cultural Renaissance” as well as the Japanese colonizers’ “Kominka Movement” both suppressed Taiwanese opera. Excluded from high culture and left to its own, the folk art developed a casual style comparable to Camp. The aesthetic has persisted despite change of political atmosphere over the years, and the two performances are heavily indebted to this tradition. I will show video clips of the two performances to demonstrate their alliance to Camp and the implied political messages
“Whither East Asian Shakespeares? Politics of Exchange”
Every year, in East Asia, hundreds of Shakespeare adaptations emerge in a wide range of languages, performing styles, and genres. Outside the region, Asian theatrical idioms such as Peking opera and Kabuki are becoming more common in Shakespeare productions (e.g., Ariane Mnouchkine's works). International productions have also toured East Asia with increasing frequency and influence on local theatres.
This paper explores the localities of Shakespearean performance in East Asia and the cultural coordinates of the critics who study this phenomenon. It is striking, but not coincidental, that the viability of appropriations of both Shakespeare (such as Yukio Ninagawa's The Tempest) and non-Western theatre (such as Ariane Mnouchkine's Henry IV) have frequently been critiqued and defended on ethical grounds. The fields of Shakespearean performance and appropriation can be said to be informed by ethical questions.
“British and US scholars of Shakespeare turn to Asian Shakespeare with little knowledge of (the languages of) local theatre traditions”
This is where it starts, with misunderstanding and misrepresentation. However, when remarkable theatre productions first seen in Asia and reported at home are eventually seen in Europe and America by a broader theatre-going public, we begin to pass from the realms of fantasy projection indulged in by Manderville’s Tavels in one direction and Saiyuki (Journey to the West) in the other. Responsible cultural reportage develops sporadically, over a long time-span of first contacts, from as far back as Marco Polo to as recently as Fukuzawa Yukichi, among many others. In other words, the quality of insight has more to do with vivid individual experience than cumulative and formal national or institutionalised encounters.
The Japanese engagement with Western theatre (and Shakespeare) goes back at least 100 years to the beginning of Meiji with Tsubouchi Shoyo, Kawakami Otojiro and Sada Yakko. Euro-American theatre’s engagement with Japanese (and Asian) theatre also begins about the same time with late 19th century reports of Noh and Kabuki by Basil Hall Chamberlain, Ernest Fenollosa and others (though there is a fascinating Marco Polo phase in early Tokugawa Japan with Richard Cocks and John Saris reporting many Kabuki prostitute encounters and some Hideyoshi-style Noh). Yet significant recognition of Japanese (and Asian) Shakespeare by Euro-American Shakespeareans can only incontrovertibly be said to begin with Kurosawa Akira’s films of Kumonosujo in 1957 and Ninagawa Yukio’s Macbeth at the Edinburgh Festival in 1975. It is therefore hardly surprising if the enthusiastic but misinformed response of the British press to Ninagawa has been castigated by Kishi Tetsuo and others. A more informed engagement is still in the making; as yet few Western tertiary institutions systematically teach courses on Japanese Theatre, let alone Japanese Shakespeare or Asian Shakespeare, though some degree of reference to Kurosawa or Ninagawa at least can be expected.
Thankfully however, theatre artists still lead theatre critics in cultural exchange, rather than follow along dutifully in the wake of theorists, and, over the last two decades, some artists have become increasingly confident and playful. One has only to think of the tap dance finale to Beat Takeshi’s Zatoichi and Nomura Mansai’s crowning pop song solo in Kuni Nusubito. Some purists may not like this sort of playfulness, though I think it is best seen as a litmus test of whether one’s tastes are modernist or postmodernist. At any rate, I shall use James Brandon’s decade-old definitions of these stages of engagement (Some Shakespeares in Some Asias) in order to consider two generations of artistic intercultural playing with Shakespeare in Japan. The first is Takahashi Yasunari’s and Nomura Mannojo’s Hora Zamurai (The Braggart Samurai, aka The Merry Wives of Windsor). The second is Kawai Shoichiro’s and Nomura Mansai’s Kuni Nusubito (Richard III). I would also like to consider Shiraishi Kayoko’s collaborations with Suzuki Tadashi, Ninagawa Yukio, and Ryutopia Shakespeare in relation to her recent Setagaya performance in Kuni Nusubito to indicate further internal rings of growth.
Someone more knowledgeable than myself might compare these Kyogen Shakespeare productions with Ong Keng Sen’s Singaporean or Wu Xin Guo’s Taiwanese Shakespeare adaptations to see to what extent Brandon’s Modernist/Post-modernist distinction holds in different parts of Asia, but this is beyond my scope here. One thing I believe to be beyond dispute, however, is that, in the Kyogen Shakespeares I will consider, son and son-in-law have been less conservative with their Kyogen than father or father-in-law.
“Beyond Local Relevance—The Study of Shakespeare Performance in Asia”
Dr Robin Loon (National University of Singapore)
This paper addresses the question of the relevance of Asian Shakespeare performances to different audiences. The production of Shakespeare’s plays in Asian cultures has generally been presumed to arise from and be primarily understood through the needs and forms of a specific community, implied by the production as its target audience. However, current intercultural strategies, and the international circulation, of Asian productions highlights the need for new discourses to address the significance of productions that travel and are watched by audiences in different cultural contexts.
We argue that an auto-reflexive local-global binary framework limits the study of Shakespeare in Asia to a bilateral cultural and textual exchange, and propose instead that the performance of Asian Shakespeares is no longer bilateral but circulatory – that diverse “Asian Shakespeares” form a circuit of interconnecting textualities and influences, and a network of interfaces. As an example of how intercultural and technological transactions enable Shakespeare to not only be produced and adapted IN Asia, but allow productions to travel, we compare the performances of Ong Keng Sen’s Search: Hamlet at Helsingor and Copenhagen (2002). This paper concludes with a discussion of the challenges facing the study of Asian Shakespeare performance – specifically the development of a discourse and a methodology that would accommodate the mobility, circulation and interonnectivity of Asian Shakespeares, whereby the study of Shakespeare in Asia might analogize performance and production: as a network of scholarships and interfaces of exchange.
第47回 シ ェ イ ク ス ピ ア 学 会
2008年10月11日(土)・12日(日)
岩手県立大学(岩手県岩手郡滝沢村)
において 開催予定
研究 発 表 (要旨)
第1室
司会 九州大学教授 太田 一昭
貧しい女性たちの結婚 ——『お気に召すまま』と結婚・離婚制度神山 さふみ
Shakespeare の劇に登場する女性たちは、必ずしも経済的・社会的に恵まれている女性ばかりではないが、多くの場合、幸せな結婚を迎える。本発表では、喜劇 As Yu Like It の材源とされるLodgeの牧歌ロマンス Rosalynde から、人物像が大幅に書換えられたPhoebeと、新たに書き加えられたAudreyという二人の貧しい未婚勤労女性に光をあてながら、貴族の娘RosalindとCeliaとの階層格差に着目し、劇中の女性たちの結婚の成立過程を検証した。
16世紀において、「貧しき者」の観念が「神の定めた神秘」から「社会悪」へと変容し、貧困問題は法的措置にもかかわらず、一層深刻化していた。下層階級の未婚女性spinsterは生涯、肉体労働者として生計をたてなければならなかったが、その逼迫した経済事情は裁判記録から示唆される。さらに当時の政治的見解によると、貧しいspinster(未婚の母を含む)は忌み嫌われる存在にとどまらず、転覆の恐れのある魔女とみなされ、「魔術禁止令」に抵触する可能性もあった。イングランドではこの頃、修道女の選択は既になく、spinsterにとっての結婚は、covertureという身分を得、社会的に認められるだけではなく、転落の危機を回避するための一つの道であった。
国教会成立後、世俗権力が結婚制度に介入し、その法的枠組みは多様な問題を孕んでいたなか、劇中の貧しい娘たちは、ひたすら「貞節」な心を捧げて婚姻契約に至る。彼女たちが結婚制度に回収されていく姿は、劇外の社会を反映する。その一方で貴族の娘たちは、紆余曲折を経て、大団円で階層秩序を維持し、喜劇の目的も達成する。Shakespeareは、「貞節」に反牧歌的経済価値を付与しつつも、劇世界全体に牧歌的精神を偏在させ、野心を退け「まことの愛」で愛する人と結ばれる、という夢も織り込んでいるようにみえる。
Cleopatra を「勝利者」とするドラマツルギー
——エコフェミニズムの視点から読む Antony and Cleopatra ——朱雀 成子
PlutarchやDanielがCleopatra を倫理的な観点から批判的に扱っているのに比べ、Shakespeareは彼女をエコロジカルな視点から肯定的に描きながら、ふたつの点で「勝利者」としている。
1. Octaviaに「勝利する」Cleopatra:女王は水、土、食べ物などのエコロジカルな身体として表され、Antony はその魅力の虜となる。彼女を「大自然の生んだ驚嘆すべき傑作」と評するEnobarbusの言葉の背後に、女王を女のカテゴリを超えた自然そのものとするShakespeareの考えを読むことができる。「ナイルのへび」とも呼ばれる女王は、Egyptの風土に根ざした、いわば大地母神である。このような自然の具象としてのCleopatraの魅力は〈動〉によって表現され、Octaviaの〈静〉と対比される。Enobarbusが女王を〈走る女〉として称賛する箇所、および〈歩き方〉の威厳の有無を問う女王に、使者が「命なき物体」とOctaviaを揶揄する箇所には、Cleopatraの〈動〉を魅力と捉えるShakespeare の視線がある。
2. Caesarに「勝利する」Cleopatra: Cleopatra の「夢」を理解し、体制に絡めとられないDolabella は、女王の「従僕」としてその名誉を守り、彼女を「勝利」に導く役割を担う。Shakespeareは、ふたりの主人の相反する命令に従うDolabellaを造型することで、女王寄りの姿勢をとっている。また、Shakespeareは、ナイル河の氾濫がもたらすEgyptの死生観、すなわち死者の魂はやがて蘇り、再生するという円環思想を織り込んで、女王の再生を目論む。Cleopatraは最終場において、この世の有限を離れ、「新しい天地」ともいうべき無限へ、円のなかへと組み込まれ、「不死」と勝利を手にする。Rome からみるとCleopatraは敗北したのであるが、Shakespeareは歴史的事実とは異なるレベルの勝利をEgypt 女王に与えたといえるであろう。
司会 専修大学教授 末廣 幹
Shakespeare and the Idea of the FutureJames Michael Tink
This paper considers in what ways Shakespearean drama postulates an idea of the future. Whereas existing studies of Shakespeare have long explored ideas of temporality and historicity in the works, addressing in particular the aspects of a nascent modernity in the plays, there has been relatively less critical attention to actual concept of the future that is conveyed in the works. The notion of the future is addressed throughout Shakespeare, such as the themes of progeny and posterity celebrated in the sonnets, the anxious consideration of futurity explored in Macbeth or the ideas of wish fulfilment and providentialism in the romances. This paper, however, focuses on one particular form of imagining the future; that is the future as a possibility of contingency and hence potential difference from the present. It considers how the idea of the future as can be read in two plays; Henry V and Pericles. Both plays share the use of a choric figure as a commentator who uses the rhetorical figure of prolepsis —or the anticipation of future arguments—to frame or narrate the drama and illuminate one dramatic strategy for exploring an idea of the future.
In the case of Henry V, the chorus’s triumphant allusion to the imminent return to London of the Earl of Essex is read as a Machiavellian form of contingency, whereby the political realm of late Elizabethan London can be briefly re-imagined as a reinvigorated public body (a fraternal ‘band of brothers’) through the actions of the Earl of Essex. It is argued that the play envisages the future as a form of political potential. This is then contrasted with the use of the future in Pericles, whereby the audience is invited to speculate on the plot of the performance through the proleptic figure of Gower. The paper also considers the use of prosopopeia as a device for addressing the audience themselves as a form of futurity. The effect of this is to redirect the idea of the future from being a public experience of contingency and potentiality to an aesthetic condition in which potentiality is a source of narrative expectation and surprise. In conclusion, the paper speculates on the historical and cultural reasons for this changing idea of potentiality and futurity in the two texts and considers the implications for contemporary ‘presentist’ literary criticism.
The “Demon” of Capital: Timon of Athens in Meiji JapanMihoko Suzuki
Scholars writing about the introduction of Shakespeare in Japan have largely focused on Hamlet whose protagonist exemplified the plight of the alienated Japanese intellectual during the Meiji period. Yet Julius Caesar was adapted in 1886 to support the institution of a constitution for Japan; and the Merchan of Vnice was adapted in 1885 first as a Kabuki play and then as a novel, indicating its timeliness for contemporary Japanese culture that was preoccupied with the circulation of capital.
In this paper I focus on Hibiki, a seldom-noted example of a popular adaptation of Timon of Athens, which was performed in 1910 and published in 1912. The play features as the contemporary Japanese equivalent of Timon, Hozumi Morio, a viscount whose impecunious forebears amassed an inordinate amount of capital through money-lending. I suggest that this tale of money- lending demonstrates significant links with an extremely popular novel of this period, Ozaki Koyo’s Konjiki Yaha, published in 1906, which was dramatized as well. The juxtaposition of Hibiki and Konjiki Yasha reveals that Shakespeare’s entry into Japan coincided with the ongoing debate concerning modernization and the advent of Western capitalism. Capital is constructed as “lucre,” and both texts display a fascination with the ability of capital to reproduce itself and with the immense social power that capital can buy – exemplified in the characters of Takemura and Tsuzuki in Hibiki and Tomiyama in Konjiki Yasha. Capital also buys Western amenities (automobiles, travel by rail, ocean voyages from China to America, coffee, tea, and cake), as well as commodifies women: both texts critique the exchange of women by fathers and husbands for economic gain and social advantage (Significantly, actresses were introduced to the Japanese stage for the first time in 1891). Yet at the same time, the spirit of capitalism is projected onto women, who are blamed for choosing to marry more prosperous men.
The figure of the “demon” [yasha] in both plays represents the power of money as at once superhuman or magical in its force and subhuman in its effects. It affects not only those who seek to possess it, but also those whose lives are touched by it. Thus this adaptation of Timon focused on the pernicious effects of capitalism as a violently competitive and dehumanizing force, antithetical to what was nostalgically constructed as the sentiment of reciprocity underlying feudal social organization.
第2室
司会 筑波大学教授 加藤 行夫
King Lear あるいはエクソシズムの劇場
——初期近代イングランドにおけるメランコリーと浮浪者問題——
松岡 浩史
反エクソシズム・キャンペーンのパンフレットという極めて特殊なソースを用いて執筆された King Lear の劇世界においては、共同体からの追放という恐怖が塑像されるものの、エクソシストに相当する救済者は最後まで現れない。これは、同時代における説明原理をもたない狂気、老人差別、そして救貧法が対処し得ない貧困問題などの抜け道のない社会問題を考慮すると極めて象徴的である。突如「解雇」されるKent、私生児として相続権を得られないEdmund、嫡子であるにもかかわらず精神病患者に身を窶して彷徨わなければならないEdger、目をくりぬかれ身体障害者となるGloucester、そして追放のCordelia。King Lear が描き出す不安とは、家族という共同体、そしてイングランドの社会階層からドロップアウトしてしまうことに対する不安であり、そこには、Shakespeare時代の深刻な社会問題が顔を覗かせている。Learは二人の娘の間をたらい回しにされた挙句、物乞い同然に成り下がるが、高齢者もまた社会生活が営めないという点で完全に社会秩序からの逸脱者であったのだ。そう考えると、Learによるあの愚かな愛情確認ゲームはやがて共同体から爪弾きにされる老後に対する不安の裏返しであるといえるのかもしれない。
Shakespeareの時代に出された浮浪者取締法の恣意的な認定基準は性質としては全く魔女の認定と同じものであり、社会階層のグレーゾーンに位置する人間たちはいつでも犯罪者と認定されうる危険があった。King Lear の世界は、明日だれが浮浪者となってもおかしくない不安な世界であり、「主人を失い」(masterless)、社会との「つながりを失った」(vagabond)者たちに突きつけられる恐怖が徹底的に煽られることになる。そしてDoverへ向かう盲目のGloucesterが身をもって示すように、当時の社会史資料によると家族の崩壊、あるいは破産にともなう絶望は自殺の主要な動機であったらしい。 King Lear とは何よりもまず一家離散の物語であり、16世紀以降核家族化が進む中で、とりわけ社会不安が発展する源は家族制度にあったといえるのではないだろうか。
『テンペスト』における衣服
高森 暁子
衣服は『テンペスト』の政治劇としての側面を語るうえで、重要な示唆を与えてくれる存在である。劇中で展開される権力簒奪のドラマには、衣装の簒奪のイメージが繰り返し現れる。富と権力の象徴である宮廷人たちの高価な衣装は、その威厳とスペクタクル的な力によって、支配 / 被支配の関係性の強化に寄与している。しかしもう一方で衣服は、劇内部の政治ドラマの世界と市場社会とのつながりを垣間見せてくれる存在でもある。島の王を目指すステファノーは、階級上昇のしるしである豪華な衣装を手に入れようとするが、興味深いことに、トリンキュローはそれを「古着屋にある服」(“what belongs to a frippery”)と比較している。古着は当時、劇団の衣装の主な出所の一つであり、ヘンズローも演劇の興行以外に、古着屋兼質屋を営んでいた。初期近代において、衣服は社会的地位の象徴であると同時に、非常に貴重で高価な資産であった。となればミラノを追われる際、プロスペローの粗末な小船に「高価な服」が積み込まれたのも偶然ではあるまい。
また『テンペスト』には衣服の上での奇妙な異種混交の世界が展開している。中でも2幕2場でのキャリバンの衣服は、彼のアイデンティティにある特定の文化的意味を付与している。彼が纏 う “gaberdine”と呼ばれる上着は、その中にトリンキュローが潜り込むことを考えれば、ある程度丈の長い、マントのようなものを想定しているはずである。既に複数の研究者が指摘するように、キャリバンの原型は新世界だけでなくアイルランドにも見出すことができる。エリザベス朝、ジェイムズ朝において、頑丈なマントはアイルランド人を強く連想させるアイテムであった。キャリバンの奇怪な身体表象は、それ自体が一種の生身の「衣装」と言えるが、その彼が纏うマントの下に、さらにトリンキュローが潜り込んで作り出す「怪物」は、当時の観客たちにとって、幾重にも重なりあう他者性を帯びた奇怪なハイブリッドであったに違いない。
司会 東京大学准教授 河合 祥一郎
The Court Secret の三つの異なるテキスト
石原 万里
1642年の劇場閉鎖の年にJames Shirleyによって書かれた The Court Secret は、1653年にHumphrey Moseleyによって出版され、王政復古後の1664年にKing’s Companyによって上演されている。この作品にはmanuscriptが残されており、その筆跡から、The Earl of Newcastleの芝居 The Country Captain を清書したScribeによって書かれた清書原稿であると思われる。Manuscriptは、1653年版のテキストとは多くの異同があり、かつ加筆削除修正が行われている。
本発表では、R.G.Howarthの “A Manuscript of James Shirley’s The Court Secret ”に基づきながら、最初に、作家Shirley の動向、出版事情、演劇界から、作品を取り巻く外的事情を考察した。1653年は、ある期間の劇場閉鎖を経て「読むための芝居」が出版された年代である。王政復古以降、芝居の上演権を巡り、当事者間の思惑が交錯していたと思われる。
次に、1)manuscript 2)修正されたmanuscript 3)1653年版テキスト、の三つのテキストの比較を行った。reasonとtemperの単語が2回続く1653年版のテキストと、1回しかでてこないmanuscriptを比べると、 1653年版(の元になったテキスト)の方が、manuscriptよりも前に書かれたテキストである可能性もある。同じ語句を使いながら全く違うテキストが出来上がっていることから、この二つのテキストよりも前のヴァージョンから、この二つのテキスト書かれた可能性もある。修正されたmanuscriptは、登場人物が減らされたり名前が変えられたりしていること、入場の場所が変更されていることから、上演を意識していたことがわかる。
A tragedy of false accusation: What makes Othello mistake Desdemona for ‘that cunning whore of Venice’?
Angela Kikue Davenport(アンジェラ・ダヴェンポート)
The aim of my presentation was to investigate the underlying reason why Othello misinterprets Desdemona for ‘that cunning whore of Venice’ by placing the play in the social context of Shakespeare’s London and to look for the possible meaning of such a tragic misunderstanding.
By introducing the unique structure of prostitution in Shakespeare’s England (not Italy), I showed how abundant the play is in references associated with the sex trade in Shakespeare’s London. Shakespeare has added characters related to the underworld to his source (or enlivened some of the existing minor characters) to suit his purposes: Cassio is more involved in ‘whoring’ than his original character; the licentious Roderigo and the vulgar-mouthed Clown are introduced; a woman whom people believe to be a courtesan (Bianca) has a crucial role to play; and Iago and Roderigo are ‘night-walkers’ who trade sex (the merchandise being the unwitting Desdemona). What is particularly striking about Shakespeare’s Othello is that the heroine is effectively confused with the ‘courtesan’, and Othello himself goes so far as to arrange a brothel scene where he simulates a client, treats Emilia as a bawd and bewhores Desdemona verbally. Othello’s use of plurals for Desdemona’s imaginary sexual partners is also noteworthy (for instance, before he kills her, Othello laments ‘She must die, else she’ll betray more men’ [5.2.6]). I demonstrated that, in Othello’s exaggerated imagination, Desdemona is no longer merely an adulteress and that Iago has in fact succeeded in making Othello truly mistake his most innocent and chaste wife for ‘that cunning whore of Venice’.
In fact, such tragic misunderstandings (or false charges) were everyday affairs in the actual courtrooms of contemporary England. There were many defamation cases where women were slandered as a ‘whore’, etc. (and also men as a ‘cuckold’ or a ‘whoremonger’, etc.). There were also many other cases where people were unjustly convicted and sentenced to punishment. My suggestion was that the play is revealing the ironic fact that the social structure of the time made it possible for even a pure wife to be falsely misinterpreted as a prostitute, and the unique structure of prostitution (whereby virtually anyone in society had relatively easy access to the sex trade regardless of their social background), combined with the malfunctioning of the legal system, contributed to allow such tragic misunderstandings to occur. The play is thereby exposing the mechanism of false charges against innocent people that were actually occurring in Shakespeare’s England. My argument was that, seen in this light, the play is not a tragedy of the hero’s individual inability to make a proper judgment: it is not so much that Othello is credulous, but rather that society itself is ultimately responsible for such a tragic false accusation.
第3室
司会 広島大学教授 中村 裕英
1H6 に於ける英雄Talbot誕生の過程を探る
土井 雅之
1H6 を、a ‘Talbot’ playと解釈する試みは、既に、Cairncrossに誤りと指摘されて来た。それは尤もなことであるが、Nasheの讃辞が明らかにするように、我々の想像を遥かに超える、Elizabeth朝の観客の注目がTalbotに集まったことはどう解釈すべきであろうか。
当時の資料が明らかにするのは、Talbotの知名度の低さであり、1H6 に於いて取り上げられるまで、殆どの人がその活躍の詳細を知らなかったと思われるのである。しかしその状況でShakespeareは、Talbotを英雄化することに挑みそれに成功したのである。
それは恐らく、Armada海戦を経て、軍事への関心を高める観客に、Shakespeareが、彼らが求める理想的な軍人、Elizabeth朝のcontextから生まれた新しい英雄としてTalbotを提示したからであったと考えられる。本論では、Shakespeareがどのようにその英雄像を舞台上に現出させていくかを次の二点から検討することを試みた。
第一には、当時民衆の興味を引いた軍事の話題をtextに編み込みながら、それらに符号する優れた指揮官としてTalbotを描写したことである。そうして描かれるTalbotが民意を反映していたことは、同時代の出版物が裏付けてくれる。ShakespeareのTalbotは、民衆が期待した、外敵から自分たちの国を守ってくれる軍人に相応しい人物像を、充分に汲み取った上で造形された、時代の寵児なのである。
第二には、Tudor朝を通じ強固になりつつあった国家意識をTalbotに投影し、愛国心に溢れEnglandを表象する人物として創作したことである。Shakespeareはそうする過程でJoan of ArcにFrenchnessを体現させ、彼女とのrival関係の中でTalbotが象徴するEnglishnessを固有化したのである。Talbot親子の死後、Henry VIの求心力は更に弱まり、一つの共同体としてのEnglandが瓦解して行く姿が描かれることから、その死は共同体Englandの崩壊をも象徴すると解せるだろう。
民衆にはほぼ無名の将軍であったTalbotは、そうして作り上げられ、観客を熱狂させるに充分な魅力を備えていくのである。
シェイクスピアの第1四部作 ――政治力学を見据えて
徳見 道夫
シェイクスピアはホールやホリンシェッドの材源を丹念に読み、第1四部作を作り上げたと言えるが、彼は現実に目にしていた政治も冷静に見つめており、その視点も作品に反映していると考えられる。読書と現実の政治事象、これらがシェイクスピアの材源であると言える。そのような政治認識を有していたから、彼は政治の世界の非情性・残酷性を舞台上で描いたのであろう。本発表では、トールボット、グロスター、ヨークの悲劇を通して、シェイクスピアの政治認識を検証してみた。登場人物たちは、己の政治的鈍感・詰めの甘さなどにより悲劇的な状況に陥り、政治に関係する人間の悲劇を露わにしている。第1四部作では多くの人物がそのような状況に陥ることによって、政治悲劇の普遍性を獲得している。さらにシェイクスピアはリチャード三世にも言及し、政治的機械と化したリチャード三世でさえ「政治力学」の犠牲者であると規定する。マキアベリ的な発想で着実に王位に登っていくリチャード三世を政治の犠牲者と描くことによって、政治を超えたさらなる大きな存在を示唆する。ティリヤードの世界観はすでに否定されているが、ヘンリー七世による「和解=平和」へのシナリオは、シェイクスピアの頭の中に存在していたように思える。周知のように、シェイクスピアは一つの解釈を許さない作家であるが、ヘンリー四世がリチャード二世を廃位して王位についたという歴史的負荷を、イングランドが犠牲を払って消滅させようとしているという意識は存在していたと思われる。リチャード三世の悲劇もこの第1四部作に含めたシェイクスピアは、上記の点を考慮に入れていたに違いない。最後に、本発表では明確な視点を提供することは避けた。第1四部作が良い意味で「混沌」とした作品であるので、批評活動も作品にあわせて多面的なものとなる必要がある。第1四部作はそれほど多義性を含んだ作品であり、まだ研究の余地を多く残していると思われる。
司会 日本女子大学准教授 佐藤 達郎
Henry V における軍人の表象本多 まりえ
Henry V は従来、戦争による国家統一を描いた愛国主義的な作品と解されることが多かったが、本発表では、登場人物の様々な声をエリザベス朝の軍事書物と対照させながら検証し、本作品を当時の軍事的観点から考察した。軍事書物は、主にヨーロッパ大陸からの帰還兵によって書かれた戦術に関する指南書であり、Henry V にはこれら書物に記された問題と重複する点が多い。
国王Henryと民兵Williamsが戦争の大義を巡り論争する場面(第4幕第1場)は、材源とされるHolinshedの『年代記』などにはなく、シェイクスピアが創作した点で重要である。Williamsはフランスとの戦争に対し懐疑を持ち、戦争の大義が間違っていた場合、王が責任を負うべきと考えるが、Henryはこの戦争は正当なものと考え、たとえ大義が間違っていたとしても王は責任を取る必要はないと考える。戦争の大義や責任を巡る問題は、エリザベス朝当時、聖職者・人文主義者・退役軍人などの間で論じられており、当時の社会状況の反映と捉えられる。
職業軍人のFluellenとMacmorrisは、戦争の大義という内的問題よりも、戦術など表面的な問題について論議し、自己の地位や名誉のため従軍すると考えられる(第3幕第3場)。とりわけ軍法に固執するFluellenの台詞は、当時の軍事書物と重なる点が多く、Fluellenの軍法に関する滑稽な描写は、彼と同様に戦争に対し盲目的な情熱を抱いていた当時の職業軍人に対する揶揄と考えられる。
ごろつき民兵のPistolたちは、Williamsらと同様に戦争を厭うが、私益のために戦争を利用する。彼らの言動は退役軍人の困窮や逃亡兵の問題など当時の軍事問題を反映し、戦争の矛盾を示唆する。
以上の考察から、本作品は、愛国主義という統一見解の裏に潜む私欲や戦争の大義を問題視したアイロニカルで複雑な作品と解釈できるのではないだろうか。
サミュエル・ダニエルとシェイクスピア
——欽定『説教集』と『ヘンリー四世・第二部』とをめぐって——
郷 健治
まず、Samuel Danielがシェイクスピアの『ソネット集』に登場する(いわゆる)「Rival Poet」であり、A Lover’s Complaint の中のtalentsと呼ばれる贈り物が、ダニエルのThe Complaint of Rosamond(1592)で巧みに示唆されたtalentという言葉のウラの意味を下敷きにした、biblicalかつsexualな、極めて精巧な愛のエンブレムである、という本発表者の新説を紹介し、「A Lover’s Complaint は贋作で、本当はJohn Daviesの作である」と主張するBrian Vickersの新著と、このVickersの新学説をめぐるTLS誌投稿欄での夏以降のイギリスでの論争を説明。発表者もこの真贋論争に一石を投じた旨(10月12日号)を報告した後、ダニエルは、The Civil Wars(1595)のみならず、実はこの『ロザモンド』においても『ヘンリー四世』2部作に大きな影響を与えていた、という新説を提起。国王ヘンリー二世の愛人になれ、とロザモンドに諭す侍女らしき女が、その詭弁を弄する際に用いた恐ろしく狡猾な5つの言説を、シェイクスピアが『ヘンリー四世』二部作で自在に借用し、昇華させていた可能性を考察した。殊に、ダニエルが巧みに仄めかしたtalentという言葉のウラの意味が、occupyという猥褻な言葉にまつわる欽定『説教集』の一説教の文言のパロディに基づいていたのに対抗するかのように、シェイクスピアもまた、このoccupyという猥褻語にまつわる欽定『説教集』の文言のパロディを、2 Henry IV のQuarto版(1600)のDollの台詞で仄めかしていた可能性に注目。このドルの台詞が、『説教集』中のoccupyの不運な用例を物笑いの種にした無類のジョークであったため、教会への冒涜であるとみなされ、Quarto版 2 Heny IV が出版後検閲当局に問題視され、再版が許されなかった、という可能性を考察し、Folio版 2 Heny IV の印刷用原稿に関しての新説を提起した。
第4室
司会 拓殖大学教授 冨田 爽子
『ヴェニスの商人』再話物語におけるシャイロックの復讐の描かれ方
鈴木 辰一
本発表では、19世紀後半から20世紀前半に数多く出版された、子供向けのシェイクスピア劇再話 The Merchan of Veni を扱った。特にCharles and Mary Lamb のTales from Shake-speare (1807)、Mary Seamer の Shakespeare’s Stories Simply Told (1880)、Mary Macleod の Shakespeare Story-Book (1902)を取り上げ、Shylockがどう表象されているのか、どのようなShylock像が子供に提示されていたのかを考察した。
始めに、それぞれの物語の冒頭における、Shylockが抱くAntonioへの憎しみの描かれ方について分析した。LambやSeamerはShylockの悪の要素を強調して描いているのに対し、Macleodは悪の要素に加えて、不当なユダヤ人差別に対するShylockの怒りも憎悪の1つの要因として描いているのである。次に、Jessicaの駆け落ちとそれに対するShylockの反応の描かれ方を分析した。Macleodの物語ではこれらの出来事は大きく変更されることなく語られているのに対し、LambとSeamerではこれらの出来事が大きく改変されており、本来 Shakespeareの作品が持っていたような、Shylockの復讐の決意に妥当性を与えるという働きを持たないものとなっているのである。そして最後に、法廷の場面で判決を受けるShylockの描かれ方を分析した。この場面では、LambやSeamerがShylockの反応を簡潔に述べているのに対し、Macleodは、Shylockが同意に至るまでの様子や心情を詳細に描いているのである。
このように、LambやSeamerの描く単なる悪人としてのShylockと、Macleodの描く悲劇的な要素を持ったShylockという2つのShylock像が当時の子供には提示されていた。しかし、当時のLambの人気の高さを考慮すると、MacleodのShylockは、子供が初めて触れるThe Merchan of Vnice から遠ざけられる結果となり、子供に提示されたのは、悲劇的な要素を持たない単なる悪人としてのShylock像が支配的であったと思われる。
『夏の夜の夢』のメタモルフォシス
——王政復古期におけるセミ・オペラと『妖精の女王』(1692) ——
松田 幸子
A Midsummer Night’s Dream (MND) の改作であるオペラ The Fairy Queen (1692) (FQ)には、一見不可解な歌曲が存在する。FQ には恋人達の結婚を祝福する5幕のマスクの後に「中国風の庭」での中国人による歌と踊りが加わるのだ。ギリシア・ローマ古典を範とするオペラに、中国という記号が入り込むのはなぜか。中国の歌曲が劇中でいかなる機能を果たしているのかを検討し、1690年代イングランドにおけるオペラの受容の一形態を明らかにするのが本発表の目的である。
17世紀後半のイングランドでは、オランダ使節団随行員Johan Nieuhofによるものをはじめ、中国に関する多くの書物が出版された。その中で中国は長い歴史を持つ文明国とされ、時にはヨーロッパ文明の起源とされる。さらにWilliam TempleやJohn Webbはその著作の中で中国をancientとし、ギリシア・ローマ、キリスト教以前の知の源泉をみる。この起源への志向はオペラをルネサンス期イタリアに生じさせた衝動と呼応するものである。オペラはギリシア劇を復興する試みの中で生まれた上演形態であった。
イングランドでも同様にオペラはこの起源への志向を持つが、プロテスタント国家イングランドにとって、起源をカトリック国イタリアに持つオペラを受容することは容易ではなかった。Drydenらは、オペラのイタリア起源について極めて慎重に言及する。また FQ は舞台をアセンズに設定しない。Theseusはただ公爵と呼ばれHippolytaは登場すらしない。これらはancientの否定だろうか。そうではない。イングランドでオペラを受容するためには、イタリアとその起源のancientを消すことは不可能でも、ずらす必要があった。FQ は、カトリック国イタリア/古代ギリシア・ローマというラインからの逸脱としてギリシア・ローマ的ancientを排し、中国というancientを創出したと考えることが出来る。この時中国は新たなancientとして立ち現れる。ここに MND の変容を見ることが出来るだろう。
司会 鹿児島国際大学教授 小林 潤司
シェイクスピアと自由民権運動 ——北村透谷の場合——
吉村 愛里
本発表では、北村透谷の自由民権運動への関わりにシェイクスピアが与えた影響を、透谷の評論「真‐對‐失意」(明治25年7月10日『平和』第4号)に見られる彼のブルータス観を通して考察した。
わが国における『ジュリアス・シーザー』の最も初期の受容は、自由民権運動と密接に関わっており、この関連を示すものとして河島敬蔵の『欧州戯曲・ジュリアスシーザルの劇』(明治16年「日本立憲政党新聞」に掲載)や坪内逍遥の翻訳『自由太刀余波鋭鋒』(明治17年出版)がある。自由民権運動に参加した数少ない文学者としてユニークな地位を占めている透谷は、明治16年から19年にかけて東京専門学校の政治科と英学科で学ぶ中で、自然に『ジュリアス・シーザー』を自由民権運動と関連づけて理解するようになったと考えられる。
彼が自由民権運動を通して何よりも実現させたかったのは、「人間天賦の霊性である自由」を人々に勝ち取らせることであった。透谷によれば、より良い社会を実現させるために重要なのは、たんに共和制を奨励することではなく、封建的、独裁的な社会において自由が抑圧されていることを国民一人ひとりが意識していくことであり、それが、「沙翁羅馬史中に尤も沈厳なる豪傑として史家に評せられたるブルタス」、「偉大な士は常に世に逆ふなり」などの賛辞からも窺える、彼のブルータスに対する共感へと繋がっていく。
また、透谷が明冶18年の大阪事件で味わった苦しみと共通する、内面と外面の葛藤をブルータスが経験することも、透谷のブルータスへの共感を発動する契機となったのであろう。しかし、透谷はブルータスを賞賛すると同時に、ブルータスの無条件な理想化を阻む素因をも見抜いている。最善の策だと思ってシーザー暗殺を遂げたブルータスの行動は民衆の理解を得られず、ブルータスの破滅をもたらすことになる。「憐れむべし希世の豪傑も本質を得るには難しかりを」と、ブルータスの「偉業」も失意のうちに潰え去ってしまったことに注目している。透谷が『ジュリアス・シーザー』の中に見出したのは彼が実人生の中で追求した理想と挫折に伴い直面した現実との両方だったのである。

セミ ナ ー (要旨)
1. 歴史劇の面白さ
 |
|
「歴史劇の面白さ」というテーマで行われた本セミナーはメンバーそれぞれにとっての歴史劇の面白さを提示し、それらについて討論することで、各自の関心についての議論を深めると共に新しい面白さを発見することを目指した。メンバーは6月にセミナー・ペイパーで扱う予定の内容を提出し、この時点で「史実と虚構との関係」、「歴史劇のジャンルとしての地位」、という二つの大きな問題が浮かび上がった。各メンバーはこれらの問題意識に基づいて8月末にペイパーを回覧した。9月上旬には全員が集まって内容の確認と内容に応じたグループ分け、さらに一度目の討論を行った。その後グループごとに電子メールを通じて意見を交換した。学会当日は、各メンバーがそれぞれのペイパーを紹介した後、グループごとの討論を行い、これが一巡した後でフロアから質問やコメントを求める、という手順でセミナーを進行した。
グループ分けとペイパーのタイトル・概要は以下の通り。
第一グループ(歴史劇における時間の問題)
佐野 隆弥 「Hybrid Histories:歴史劇のジャンルをめぐって」
本発表では、歴史劇というジャンルに絶えず付きまとう、ジャンル区分上の不安定さを取り上げ、いくつかの初期近代イングランド史劇と、それに対する同時代の反応を拾いながら、その曖昧さを考えることが、歴史劇の面白さを追求する一つの助けとなるのではないか、あるいは、その多面性・雑種性自体が歴史劇という固有のジャンルの特徴なのではないか、という問題意識のもとに議論を行った。そこから以下の結論を提案した:歴史劇の面白さの一つは、受容者が、あるいは場合によっては劇作家が、自己の置かれた政治的文化的状況を作品の意味や内容として投影できるところ、つまり領有の容易さにある。もちろん悲劇や喜劇においてもこうした現象は起こり得るが、政治を中心とした歴史的事象を扱う歴史劇は、ジャンルという縛りの不確定さともあいまって、受容者のこうした解釈行為を誘いやすい。
森 祐希子 「歴史劇における「時の流れ」の意識」
『ヘンリー五世』のエピローグは、劇の終結時点以降に起こる歴史上の出来事を語り、しかも舞台上ではそれが既に演じられたと告げる。未来と過去が時間軸上で交錯し、しかもそのすべてが観客にとっては過去である。時の流れが、意図的に輻輳した形で提示されているのである。過去を舞台に乗せる「歴史劇」において、舞台上の時間と歴史上の時間の流れをどう意識するかは歴史劇の「面白さ」にかかわる重要な要素である。シェイクスピアは過去を振り返る視点を多用して歴史を長い「時」の流れの中で描く一方、時事をアナクロニズムに織り込むなど、同時代性への意識も強い。過去の未来化、未来の過去化など、過去・現在・未来を縦横に去来させることで、独自の融通無碍な時の流れを作り出しているのだ。すべてを過去形で語る歴史書とは一線を画するこのような世界の構築が、今日の上演・演出のあり方をも含め、歴史劇の面白さの一端を支えている可能性を提起した。
第二グループ(歴史劇における王、国家、臣民の問題)
勝山 貴之 「イングランド地図の成立と歴史劇」
イングランドにおいて、正確な土地測量がなされ、地図が製作されるようになったのはようやく16世紀後半になってのことである。測量技術の発達により、土地は市場経済において流通・交換可能な経済単位とみなされる商品となった。同時に、地主と借地人の関係は、従来の伝統的主従関係から法律上の契約によって縛られた貸借関係へと変化したのである。今回のセミナーでは、当時の社会における土地や地図の文化的価値に注目することにより、1590年代の歴史劇 Woodstock、Richard II、1Heny IV、2Henry IV などの再考を試みた。それぞれの作品の中で、国家としての威厳や統一はことごとく踏みにじられ、商品的価値を念頭においた土地への言及が繰り返しなされて、王国は分断されていく。土地をめぐる近代的経済価値が優先され、封建社会における伝統的価値の世界を崩壊させていく様が生々しく描き出されている。そこからは「土地」というものが「不動産」という新たな意味を持ち始めた時代に生きる人々の心性を読み取ることができるのである。
中野 春夫 「臣民の苦しみ―“grievous taxes”」
シェイクスピア劇では、「十分の一税」や「援助税」など課税に関する特殊な用語がいくつか登場している。ただしコンコーダンスが明らかにしてくれるのは、この種の課税用語が歴史劇に集中しており、悲劇や喜劇にはほとんど出てこないことである。その点王国統治の経済基盤となる課税制度の仕組みを教えてくれるのは歴史劇だけになり、シェイクスピア歴史劇の課税に注目してみれば、歴史劇独自の面白さを指摘できる可能性がある。本セミナーのペイパーでは、シェイクスピア歴史劇において言及される課税およびその制度にかんして分析をおこなった。その過程で、シェイクスピア時代の現実世界における課税制度を引用しつつ、歴史劇における課税がしばしば(現実にはありえないほど)重税化され、時には意識的なアナクロニズムが導入されている現象を指摘した。今後の課題として、この課税の誇張やアナクロニズムが当時の観客にとってなにを意味するのか、この究明が歴史劇の面白さを解く一つの鍵になるのではないかと考えている。
住本 規子 「Westminster Abbey とシェイクスピア」
アジンコートの戦い前夜、Richard IIの再埋葬をもちだして父の罪を今日一日だけは問わずにおいてほしいと神に祈る若き王Henry V。セミナー・ペイパーでは、知られている最古のガイドブックが1600年に出版されていることなどからして、そのHenryもRichardも眠るWestminster Abbeyは、修道院解体と偶像破壊の嵐から半世紀を経てロンドンの観光名所のひとつになっていたことを指摘した。その上で、破壊の爪痕を曝すものもあった一方、目を見開き、彩色を施され、まるで生きているかのようであったともいうeffigiesは、訪れた人々にどのような歴史的想像力を喚起する国王表象であったのか、また、公式ガイドブックには保存されない、ガイドたちの口上文学が、どのような「歴史ものがたり」を紡いで歴史劇の観客の想像力を刺激ないしはフォローしたのか、を考えることも、歴史劇の面白さを解明する糸口のひとつになるのではないか、との問題提起を行った。
第三グループ(歴史劇と他ジャンルとの関係)
由井 哲哉 「事実と物語の接点」
一口に歴史劇と言っても、シェイクスピアのQuarto作品には必ずしも歴史劇というジャンルに属さなくとも、タイトルにHistoryとついている作品がいくつか見られ、この単語に「歴史」と「物語」の二重の意味が(現代以上に)鮮明に刻まれていたことは容易に想像がつく。このことをシェイクスピアに代表される「年代記的歴史劇」とは別の流れである「伝記風歴史劇」のジャンルに注目し、特にMunday & Chettleの Downfall and Death of Robert, Earl of Huntingon を取り上げて検討してみた。
バラッドや散文ロマンスの影響を受けたこのジャンルは、主人公を国王ではなく、国王周辺の名の知れた人物に設定し、権力奪取やその維持よりもむしろ、臣下が王への忠誠とその他のしがらみの間で板挟みになる状況を描いている。権力闘争を表向きの枠組として利用しながらも、事実と虚構の危ういグレー・ゾーンを探る試みの中に、歴史劇の面白さを探る糸口が見出せるのではないかと思われる。
廣田 篤彦 「リチャード二世と「猿真似の国民」」
イングランド人が服装において独自性に欠け、大陸諸国の服装を無原則につぎはぎして身に纏っていることは16世紀を通じてしばしば風刺の対象となり、「独自性の欠如こそイングランド人らしい」という逆説が繰り返されているが、たとえば Woodstock ではこうしたつぎはぎの服装がリチャード二世の非イングランド性を表すことでイングランド(人)という概念が持つ脆弱性が示されている。一方、リチャード二世と対立し、イングランドらしさを体現するグロスター公トマスが身に纏うフリーズ地は、ほかのテクストではウェールズ、さらにはアイルランドを表すものとして使われており、やはりイングランドらしさの不安定さが示されている。歴史劇は過去を扱いながらも、その性格上同時代性の強い風刺の要素を取り込みながらエリザベス朝のイングランド(人)像の不安定さを探求しているのである。
もとより本セミナーは歴史劇のあらゆる面白さを検討することは目的としておらず、フロアから質問があったエリザベス朝の観客にとっての面白さの探求など、十分に扱いきれなかった問題は数多く残されている。しかしながら、各メンバーはシェイクスピアの歴史劇を中心に、シェイクスピア以外の歴史劇や歴史劇以外のテクストを論じることで歴史劇の様々な面白さの可能性を提起した。このセミナーを通じて議論された多様な面白さや意見交換の中で指摘された問題が、メンバーそれぞれの問題意識を整理、再確認し、今後の考察を進める上で大きく役に立っているという意味で実りの多いセミナーであった。
2. ミドルトン ——マネー・セックス・ゲームの劇空間——
 |
|
およそ120年ぶりに刊行される新ミドルトン全集は、この作家のキャノンの大胆な再編を試みている。それが主として文体解析などの内的根拠に依存することをいくつかの具体例とともに紹介することで、司会者としてはその編集方針について問題提起ができればと考えた。当日の議論は、authorshipの安定した作品群に集中し、この作家の作風を確認する好機となった。メンバー諸氏の発言要旨は以下のとおり。
ミドルトン劇は16−7世紀に経済的に急成長をとげた大都市ロンドンが「生産した」商業演劇である。宗教・政治色の強い大衆教化のための演劇が都市生活者に娯楽を提供する演劇へと変化する転換点は、1576年の常設劇場の設置であった。これは、治安上の理由から俳優がパトロン(王族・有力な宮廷貴族)に仕えている形をとらせることで職業上の身分を保障する制度とあいまって、レベルの高いプロの演劇制作集団がロンドンで組織化されることにつながっていく。ミドルトンの都市喜劇と都市型家庭悲劇が17世紀初めのロンドンで観客をあつめられたのは、商業資本主義経済の爆発的な成長という人類が初めて経験する状況のなかで、金欲と性欲にとりつかれた男と女が生きる姿を描くことに作者が強い意欲をもっていたからである。
たとえば『ミクルマス開廷期』(Michaelmas Term)の舞台の上に観客が見ることを期待したのは、主役としてのロンドンとそこで生きている自分たちと同じような等身大の人間の姿だった。娼婦や人妻相手のセックスと、市民の娘(持参金1000ポンド)や土地持ち未亡人(年収400ポンド)との結婚を求めて上京してくる田舎のジェントリーたち。彼らが持っているマネー(地代収入)とその金を産む土地をまき上げようと、手ぐすね引いている都市居住者たち(商人・職人・犯罪者)。経済の急成長にともなう個人資産の奪い合いとモラルの喪失。このようにきわめて現代的なテーマが、ほとんどそのままミドルトン劇の主要なテーマでありえたのだ。
当時のロンドンでは、多少の資本と才覚を持ち、法を犯すことを怖れない図太さがあれば、土地資産を手に入れ紋章をつけられる身分にのしあがることは、さほど困難ではなかった。このようにして、低いタイトル保有者(knight, gentleman, citizen) の身分の流動化が急速に進み、中世からつづく共同体の秩序とその慣行が、なし崩し的に変わろうとしていた。そこから生じる家族・主従の身分関係の混乱がもたらす悲劇が、たとえば『チェンジリング』(The Changeling, 以下CH)のような都市型家庭悲劇のテーマになるのである。
ミドルトンがセント・ポール少年劇団に提供した初期の都市喜劇は、土地とエロスが結びついた連作喜劇といえる。『おかしな世の中ですよね、旦那方』(A Mad World, My Maers)を取りあげ、17世紀初頭のロンドンを表象するため、この作家がいかに<少年劇団>を活用したかを考察した。
この戯曲では、都会の人間は皆流動的な経済活動の中で生きており、田舎は彼らが搾取する富の源泉として描かれている。<田舎の老人>(サー・バウンティアス)を騙す<都会のトリックスター>(フォリーウィットとガルマン)という図式は、レイモンド・ウィリアムズが『田舎と都会』で述べた搾取の構図を浮き彫りにしている。特に、祖父の財産の相続が確定しているフォリーウィットには、いずれ自分のものになるカネを前倒しで受け取るという手前勝手な自己弁護があり、それだけ彼のトリックは、純粋なゲーム性が高い。だが、もう一人のトリックスター、ガルマンは、フォリーウィットとは異なり、より深刻な生活手段として日々の詐欺行為を行っている。ガルマンは、ヘアブレインを易々と出し抜くのみならず、策士気取りのフォリーウィットも彼女が育ちの良い処女だと思いこんでしまう。彼女だけは常に<騙す側>であり、騙されることはない。ある意味で、この芝居は彼女の一人舞台なのだ。
こうした<騙し>のゲームには、「策士は策におぼれる」というルールが付随しているが、「今までの私のことは、もう過ぎたことよ」という終幕のガルマンの台詞は、フォリーウィットの結末と真っ向から対立している。この戯曲には、主筋・脇筋ともに、風刺が風刺として効かなくなっている瞬間がある。本当の処女でなくとも処女に見えれば<処女性>が商品として流通するような経済社会では、既に ‘Tricks are repaid’ という保守的なモラルが力を失いつつあったことを示している。そして、それこそが、タイトルである ‘A Mad World’ が示唆するmadnessなのかもしれない。
こうしたホッブズ的な世界に生きる劇中人物の中で、異彩を放っているのがサー・バウンティアスである。その名前が示す通り<寛大>な彼は、散々に騙されながらも全てを笑いに流して芝居の大団円を生み出す。彼は<尽きぬ富の源泉>として、都会のペテンを完全に無効化してしまう一種の理想人として描かれている。
しかし、ここでこの芝居が少年劇団向けに書かれていたことが問題になる。ロイ・フィッシャーは、ルネサンス演劇における「髭」の表象と男性性の問題を論じながら、フォリーウィットの付け髭に言及しているが、ここで注目すべきは、変装して男性性を装ったフォリーウィットのみならず、本物の成人男性であるはずのサー・バウンティアスも、舞台上では付け髭をつけていただろうということだ。
理想の郷士である筈のサー・バウンティアスが、舞台上では「付け髭の少年」であるというギャップは、彼自身が孫について語る「髭も生えてない若造」という台詞によって強調されている。こうした倒錯的な笑いにより、この作品は、尽きぬ富の源泉、理想のカントリー・ジェントルマンとは、即ち虚構でしかあり得ないことを暗に示しているのではないだろうか。サー・バウンティアスの付け髭こそ、<カントリー>の理想化に対する自虐的な冷笑を示す、作品が観客にしかけた最大のトリックだったのかもしれない。
『フェアな決闘』(A Fair Quarrel)においては、「名誉」という言葉にのみ寄りかかった観念がエイジャーと大佐を決闘に駆り立てる。舞台上の身体が内実を伴わない空疎な言葉に翻弄され続けると、身体とことばの一体感がおぼつかなくなるような瞬間—演劇にとっては危険な瞬間—が生起する。他方、唐突なひとことによるプロットの急転に翻弄される人間の運命を描くミドルトンの劇作法は、ことばの圧倒的な重みの上に成立してもいる。言語に過剰に反応する決闘(高貴を装う野蛮)が、言語本来の機能を無化するゲームである “roaring”(文化のなかの猥雑)によってパロディ化されるとき、その間に浮かび上がる医者とジェインによる、「愛」を僭称する欲望のプロットは、抽象概念をもてあます身体を舞台上に提示する。「ことばにできぬ程の感謝」を金銭に換算しようとする女と、その打算を糾弾しつつ「金銭に換算しえぬ愛」をみずからの欲望にすり替える男の関係は、そのまま悲劇 CH でも反復される。感謝や謙譲をマネーとセックスに変換する過程で、それらの美徳を媒介することばをも格下げしてみせるこの瞬間—近代にとって危険な瞬間—は、悲劇と喜劇を相対化しようとするタイプのジャンル論に揺さぶりをかける、すぐれてミドルトン的な劇空間といえるのではないか。
ミドルトンの都市喜劇の中心は、金欠のジェントルマンと成金商人が繰り広げる騙し合いのドラマで、そこには、階層社会における市民の上昇願望を背景に、 “land(土地資産)”と “money(金)”を巡る争奪戦が、戯画的現実として描かれることが多い。資産の相続・訴訟ゲームに登場するのは、たとえば市民階級を体現する父・母と息子・娘、叔父と甥、さらに、階級間縁組のターゲットになる没落貴族などであるから、その世界は<血>族の磁場の中で展開しているとも言える。だが、喜劇のテクストに潜在する<血(blood)>の要素は、“land” と “money”の背後にあって、ドラマを直接動かすモメントとはなっていない。この<血>が顕在化したとき、劇世界はどのように変貌するのだろうか。CH を中心に“blood”と “place”(とりわけ前者に着目)という視点から、ミドルトンの悲劇の特質を考察してみた。
ジャンルの違いを考えればむしろ当然のことかもしれないが、しかし、ミドルトンの悲劇には、あたかもそれが悲劇の指標であるかのように、“blood”の一語が頻出する。その執拗な反復が、「血族」、「高貴な身分」、「憤怒」、「欲情」、「流血」といった意味の場を移動しつつ、濃密な<血>のドラマの変奏を創り上げているように見える。それは、階級社会の身分を定位し、個々の居<場所(place)>と秩序を保証するはずの<血>が、同時に他方で、「憤怒」や「欲情」や「流血」に変容し、<場所>の揺らぎや喪失——ビアトリスとディ・フロリーズの主従関係の逆転、処女ビアトリスから淫婦ビアトリスへの転落、お嬢様ビアトリスから殺人者ビアトリスへの変貌など——を紡ぎ出すドラマと言い換えることもできるだろう。CH の終幕で、ビアトリスがその身から流れ出た血に瀉血のイメージを重ね、この病んだ血は “common sewer”に飲ませてしまえと語るとき、社会的身分(高貴)の証として身体の中を流れていた血は、誰のものとも区別のつかない(common)<場所>に吸い込まれてしまうのだ。たとえば、ここに、チャールズ一世処刑の模様を伝える一枚のイラスト——断頭台に突っ伏した首から血が迸り出ている——を並べてみるのは、唐突に過ぎるだろうか。ミドルトンの悲劇に偏在する<血>のドラマは、清教徒革命から国家の瀉血に至る時代のエトスとも、広く深く繋がっているようにも見えるのだが。
二つの悲劇(『女よ女にご用心』WBW とCH)を「都市悲劇」として解釈する。WBW の舞台は、実質的にロンドンである。「雇われセールスマン」であるリアンショーは近代市民の典型。それに対して、リヴィア、ヒッポリート、イザベラはジェントルマン階級。公爵によるビアンカのレイプが階級間の性的搾取の象徴であることは、ジェイン・ショア伝説との類似によって示される。レイプの場面をトマス・ヘイウッド作とされる『エドワード四世』第一部(King Edward IV, Part I)での国王によるジェイン誘惑の場面と比較すると、WBW が芝居として持つ近代的性格が浮き彫りになる。場面のほとんどが「家」の中に設定されていることにも注目。そこではリヴィア、ヒッポリート、イザベラの濃密な「血」の関係が芝居を推進する。不倫の妻の夫殺しは、『フェヴァーシャムのアーデン』(Arden of Faversham)など家庭悲劇で常套的なテーマである。
CH でもまた、ディ・フロリーズとビアトリスの階級差が芝居の推進力である。共作者ローリーによる副筋でジェントルマン階級の男たちが市民の妻を誘惑しようとするコメディーは、『無頼の女』(The Roaring Girl)でも用いられた慣習的な筋立て。こうしたことから、この悲劇もまた「都市悲劇」としての本質を備えていることが分かる。場所が「家」に限定されていることも WBW と同様。アロンゾ殺しの場面は、「砦」がいかに狭い「家」であるかを如実に示している。
「都市悲劇」では、「都市喜劇」よりも、セックスをゲーム化(文明化)する危険性がさらにあらわになっている。文明のシステムに人間の本源的部分をからめとろうとする企ては、最終的に失敗する。それは、WBW の最後で性欲のみの存在であるウォードがトラップ・ドアの下に隠れていること、CH でのビアトリスの最後の台詞、「我が身の虚飾(distinction)を下水の中に失わしめよ」に表現されている。
3. 『アントニーとクレオパトラ』を読む
 |
|
複数の視点からの鑑賞に堪える壷に喩えられる『アントニーとクレオパトラ』を、初演当時の文化的・歴史的文脈を共通の基盤としつつ、各メンバーの切り口で眺め、新たな模様を浮かび上がらせたいというのがセミナーの目的であった。打ち合わせの段階で、メンバーの関心は、ローマとエジプトの時間・歴史観、クレオパトラとエリザベスの母性表象、建築のイメージ、新プラトン主義とエロスの愛、クレオパトラの自己劇化と多岐にわたった。意見交換をすすめるなかで、コメンテーターの村井氏より、作品の二極構造、すなわちローマ/エジプト、歴史/神話、政/性、悲劇性/喜劇性、現実原理/快楽原理、言葉/行為、男性性/女性性などこれまで指摘されてきた二項対立に、各メンバーの視点がどのように関わるのか、それによって作品構造の変容をどのようにあぶり出せるのかという問題意識を共有しては、という提言があった。その結果、それぞれ異なった角度からの発表ではあったが、共通の関心として、作品に流れる時間観、歴史観の特徴を浮かび上がらせることができたと思う。以下、メンバーからよせられた要旨に基づき、発言順に紹介する。
西出 「クレオパトラの自己劇化とノスタルジア」
ジェイムズ一世即位後、一連のエリザベス追慕劇があらわれたが、クレオパトラのエジプト世界がオクテイヴィアスのローマ世界に取って代わられる時代変化を描くAC も、1606当時のノスタルジックな風潮と無縁ではなかった。急激な環境変化に際し、無意識のうちに過去を理想的な形に再構築しようとする心の働きをノスタルジアと呼ぶなら、アクティウム敗戦後のアントニーの台詞には、ノスタルジアが顕著である。しかし、アントニーの死後、クレオパトラがドラベラに語る夢のアントニー像には、単にノスタルジックな回想というにはあまりにもラジカルな主張が含まれている。夢のアントニー像を虚構と認めた上で、虚構の中ではじめてとらえられるアントニーこそが真のアントニーだと開き直るからである。彼女はみずからの自殺さえ、シドナスの再現として自己劇化する。そもそもシドナスの出来事自体、神話化が施された人工的パジェントであったので、クレオパトラが後世に残そうとしたアイデンティティーは、二重の自己劇化によって作り出されているといえる。クレオパトラの創造する「虚構」は、二人の恋愛を「娼婦と道化」の愛欲として封じ込めようとするローマの歴史観にたいするエジプト世界の最後の抵抗に、シェイクスピアが形を与えたものだ。
大島 「『アントニーとクレオパトラ』における時間・歴史観のインターテキスチャリティ」
アントニーとクレオパトラの私的・公的な愛が、ローマの政治世界に端的に見られる西洋的な直線的時間観・歴史意識と、エジプトの循環的な時間観・歴史意識とが対峙する中に置かれていることを指摘した上で、プルタークとシェイクスピアとのインターテキスチャリティに注目しながら、劇の深層に埋め込まれた時間観・歴史意識を検討した。とくに、ローマ的な時間・歴史意識を凝縮した場面として、二幕七場ポンペイ船上祝宴の場が挙げられる。事実を簡潔に述べるプルタークと比べると、シェイクスピアは、プルタークの言葉をかなり忠実にひろいながらも、歴史の不条理を見つめたマキアヴェリに通じるアイロニカルな視点からこの場を劇的に描いている。シェイクスピアの描く船上祝宴の場は、ローマ世界の歴史生成の危うさを示すとともに、最終的勝者たるシーザーの理知的な理解をも超えた歴史のメカニズムを見据えている。一方、劇中人物も常に歴史を意識している。ローマ人として高貴な自害を選択するアントニーや、シーザーの凱旋の見世物としてローマの歴史に取り込まれること拒否し自害するクレオパトラたちが提示する歴史観には、プルタークの書を机上に置き、主人公の英雄的姿を描き出そうとしたシェイクスピアの史劇への自負を読み取ることができる。
三浦 「クレオパトラとエリザベス−母性表象と自殺を巡って−」
クレオパトラにエリザベス女王を投影する批評家は、種々の類似点を認めながらも、シーザーやアントニーとの間に幾人かの子供をもうけたクレオパトラと、処女王表象を政治的に利用したエリザベスの間に差異を読み込んできた。だが、クレオパトラの母性表象と、ペリカン・ポートレイトに端的に見られるエリザベスの比喩的母性表象との間には近接性が見いだせる。観客は母としてのクレオパトラを見ることはなく、子供たちは「語り」の中で言及されるにすぎない。そこでのクレオパトラは、豊穣と受胎の女神・アイシスに扮して玉座に座り、その足下に子供たちを従える。ここでの母子関係は、地位を与える君主と臣下という政治的関係に還元される。クレオパトラの比喩的母性は、Janet Adelmanが指摘するように、死を前にローマ的アイデンティティーを失ったアントニーをもその胎内に埋め込む。使者が伝える虚報において、死に際のクレオパトラの口にした彼の名は「彼女の中に埋葬」されるからだ。さらに、終幕のクレオパトラは、自殺を、赤子ならぬ毒蛇への授乳にたとえることで、比喩的母性を印象づける。Thomas Byngのエリザベス哀歌(1603)は、「母」なるエリザベスの死への悲しみから「父」なるジェイムズを迎える喜びへのシフトをあらわすが、クレオパトラの比喩的母性表象は、エリザベスの死を周辺化するこうした動きに対抗するものであった。
中村 「『アントニーとクレオパトラ』における建築とローマ」
16世紀後半以降、イタリアの建築理論がイギリスに流入し、演劇においてもその用語と知識が援用されていたこと、また、イタリア建築学の祖ウィトルウィウスが初代ローマ皇帝にその書を捧げていることを考慮した場合、シェイクスピアが帝政の始まりを示唆する AC を執筆するに際してイタリア建築理論を参照したと仮定するのは不自然ではないと思われる。イタリアでの復興運動の後、ウィトルウィウスの建築書はジョン・ディーなどによってイギリスに紹介され、ベン・ジョンソンら作家にも影響を及ぼしていた。AC において、ローマの動向と登場人物の行動は建築の観点から比喩という表現形式において描き出されていく。劇冒頭のアントニーの台詞“the wide arch / Of the ranged empire fall”によって<ローマ=建造物>という比喩的関係がまず提示され、ローマの拡大と発展はローマを要石とする門を作っていく建築的行為として示される。また、オクテイヴィアスとアントニーの帝国建設のための活動は、 “our great designs”という言葉が表すように<図面作成→施工>という建築的手続きとして語られるのである。しかし、帝国の “pillar” たるべきアントニーは、“measure”などの語が示す幾何学的・道徳的な秩序性・規則性を違反して帝国建設の作業から逸脱していった結果、最終的には “ruin”として自らが建造物と化す。終幕におけるクレオパトラの台詞が喚起する大地を股にかけたアントニーのイメージを巨大な凱旋門と捉えるなら、地上で帝国完成を祝う凱旋式を敢行するオクテイヴィアスを眼下に見下ろし、その卑小さを嘲笑するアントニーの姿が目に浮かんでくることになるのである。このアントニーのイメージを積極的に評価するか、あるいは否定するかは私たちの歴史観にゆだねられることになる。
石橋 「『アントニーとクレオパトラ』における新プラトン主義とエロスの愛」
クレオパトラとの愛を通して「新しい天と地」を希求し、新しい生命のありようを生み出そうとしたアントニーの精神と行動の原理には、根源的一者たる「善」(One)に含まれている霊魂が「流出」「充満」「帰還」の三段階を経て、永遠回帰するという新プラトン主義の思想が色濃く影響している。三世紀のギリシアの哲学者プロティノスによれば、霊魂が「善」を離れ、回帰する遍歴の旅を支えるのは、天上界の神的な純粋美であり、低次の物質世界において他者を求めるエロスにほかならない。世界を世界としてあらしめるものが神ではなく人間だとするプロスティノスやイタリア・ルネッサンス期の哲学者フィッチーノの世界観は、クレオパトラの愛にも描かれている。アントニーの死後、彼女は「あの人の顔は天のようであった。そのなかに太陽や月が懸かり、それぞれの軌道を巡り、この小さなOの字型の地球を明るく照らしていた」と追慕し、彼を天上界のコンテクストに位置づける。アントニーのローマ的な愛とエジプト的な愛とは、入り混じって解け合い、両国の政治的混沌に向き合って呈示されるが、そうした混沌から生まれる新しい生命こそ、17世紀初頭のイングランドが近代化へ向かう途上の精神史を表している。
休憩後の討論では、時間観、歴史観、エリザベス表象、ネオプラトニズムについて意見を交わした。そこで村井氏より、クレオパトラがアントニーとのつり遊びを回想しながら述べる “That time? - O times!” に見られる、time → timesの跳躍が、この劇の時間観を解くキーになるのではないかという意味深いコメントが出された。その他、瀕死のアントニーが魚のようにモニュメントに引き上げられる悲劇性・喜劇性の融合の問題など、多くの問題を積み残したうらみは残るが、対立する見方をも含みつつ、一つの作品を皆で議論する楽しさを味わえたセミナーだった。
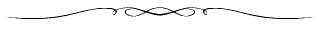
♠ PDFファイルをご覧になりたい方は、こちら へ
